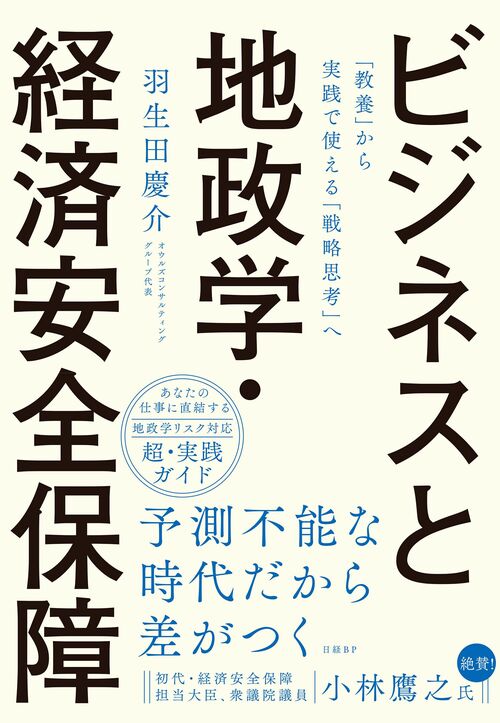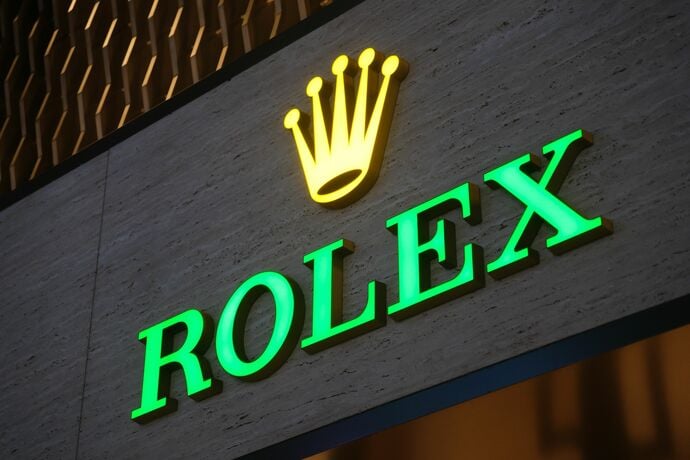写真提供:共同通信社
写真提供:共同通信社
トランプ政権の不透明な関税策、ロシアによるウクライナ侵攻、米国による対中半導体規制、台湾有事リスク、欧州の気候変動規制──。地政学・経済安全保障に関するリスクが拡大・深刻化する中、企業の事業活動が危ぶまれるケースが年々増えている。こうしたリスクによるビジネスへの悪影響を最小限に抑えるべく、企業はどのように向き合い、備えるべきか。本稿では『ビジネスと地政学・経済安全保障』(羽生田慶介著/日経BP)から内容の一部を抜粋・再編集。国家間の政治力がぶつかり合う現代の国際経済社会において、ビジネスパーソンが押さえておくべき地政学・経済安全保障リスクと対応策を考える。
2025年1月、米大統領令によって禁じられた日本製鉄のUSスチール買収。対米外国投資委員会(CFIUS)でも意見が割れたという本件の背景にあった、米政府の狙いとは?
※本記事は、2025年1月時点の情報に基づいています。
10大リスク_M&Aの阻害
安全保障を理由にしたM&A不承認
クロスボーダーの企業買収(M&A)では、関係する国の当局による独占禁止法上の審査・承認が大きな課題だ。近年では、これに加えて安全保障上の理由から、当局の承認が得られない事例や、審査長期化により企業側が断念する事例が増えている。
日本では、2019年の外為法改正により、「国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応していく」ため、外国投資家による「指定業種」に属する上場会社について株式取得時の事前届け出の対象が、従来の10%から1%に引き下げられた。
また、役員就任や「指定業種」事業の譲渡・廃止を株主総会に提案するなど、外国投資家による経営に影響を及ぼす行為についても事前届け出の対象とされた。加えて、安全保障の観点から、サイバーセキュリティーに関連する情報処理・情報サービス業種が「指定業種」に追加された。
「指定業種」とは、「国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがある対内直接投資等に係る業種」などで、インフラ関連に加え、「半導体製造装置等の製造業」や「工作機械・産業用ロボット製造業等」などが指定されている。
財務省の「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届け出該当性リスト」には約2000社が「指定業種」の事業を営む企業として掲載されている。最近では、セブン&アイ・ホールディングスが「指定業種」に該当していることが、同社に対するカナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタールによる買収提案の際に話題となった。