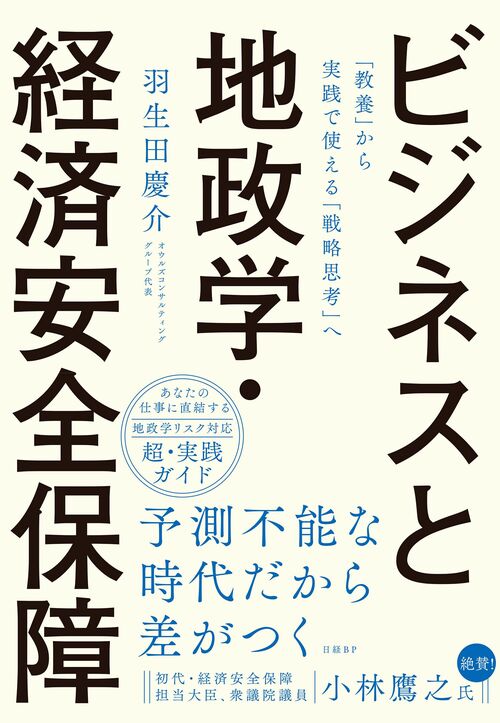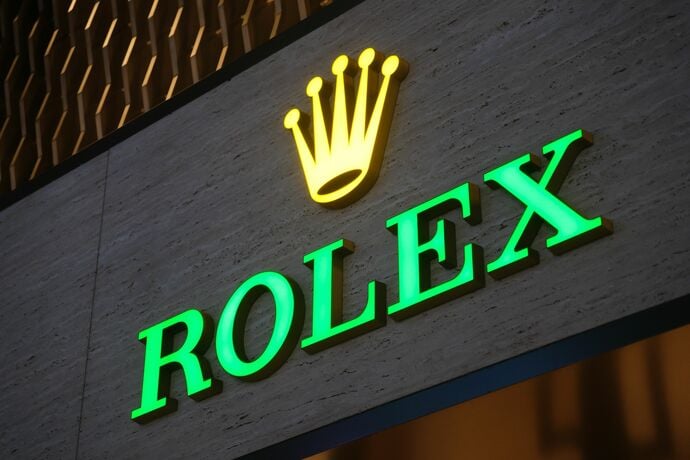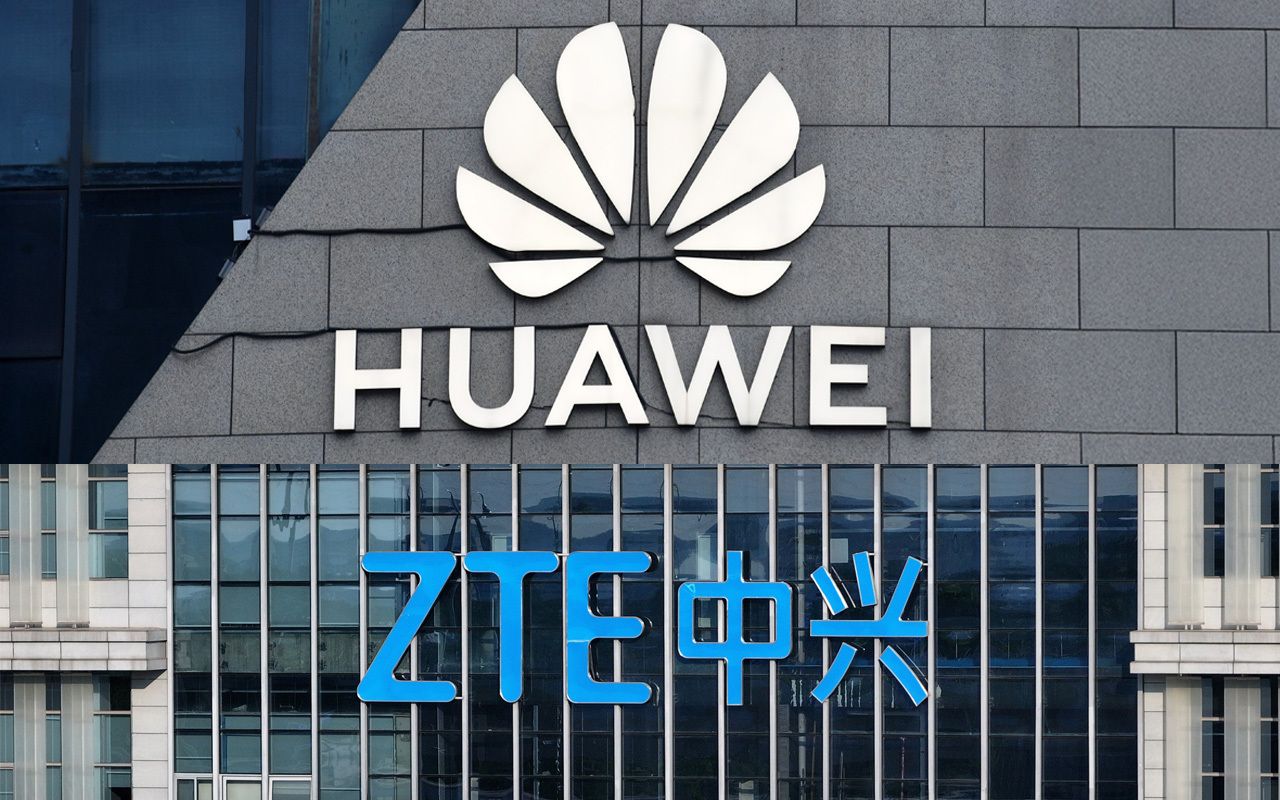 写真提供:CFOTO/共同通信イメージズ
写真提供:CFOTO/共同通信イメージズ
トランプ政権の不透明な関税策、ロシアによるウクライナ侵攻、米国による対中半導体規制、台湾有事リスク、欧州の気候変動規制──。地政学・経済安全保障に関するリスクが拡大・深刻化する中、企業の事業活動が危ぶまれるケースが年々増えている。こうしたリスクによるビジネスへの悪影響を最小限に抑えるべく、企業はどのように向き合い、備えるべきか。本稿では『ビジネスと地政学・経済安全保障』(羽生田慶介著/日経BP)から内容の一部を抜粋・再編集。国家間の政治力がぶつかり合う現代の国際経済社会において、ビジネスパーソンが押さえておくべき地政学・経済安全保障リスクと対応策を考える。
企業や教育機関で活発に行われている国際共同研究開発。技術流出を防ぎながらイノベーションを起こすために、現在どのような施策が講じられているのか。
※本記事は、2025年1月時点の情報に基づいています。
10大リスク_研究開発・技術管理の制約
多様化する技術流出リスク
日本企業がイノベーションを促進し、技術力を向上させるために、外国企業・研究機関との共同研究開発は重要だ。中国との間でも、自動車、情報通信、医薬・バイオなど、多方面で共同研究開発が実施されている。しかし、地政学・経済安保リスクが高まる中で、こうした国際共同研究開発では、これまで以上に技術流出への警戒が必要だ。
公安調査庁作成の『経済安全保障の確保に向けて2022』は、日本国内でも懸念国企業などが適正な経済活動や研究活動を装って企業や大学などに近づき、自国の製造能力や技術向上に必要な技術やデータ、製品などを入手する事案が発生しているため、「こうしたリスクを正しく認識した上で、官民が連携して経済安保の確保に向けた取組を実施し、技術・データ・製品等の流出を未然に防止することが何よりも重要」だと警鐘を鳴らしている。
同文書は、技術流出の経路として、①投資・買収、②不正調達、③留学生・研究者の送り込み、④共同研究・共同事業、⑤人材リクルート、⑥諜報活動、⑦サイバー攻撃を挙げている。
日本政府も、外為法改正による輸出管理の拡充や対内投資審査の強化、経済安全保障推進法の施行、経済安保分野におけるセキュリティー・クリアランス制度の導入などによって、技術流出防止のための法規制の整備を進めてきた。