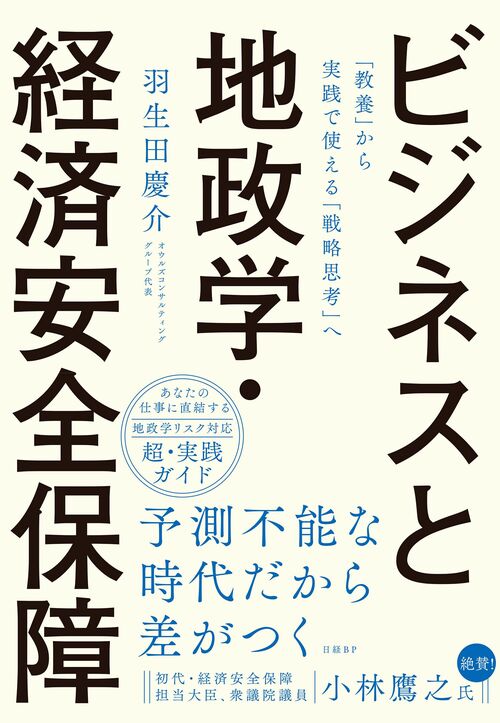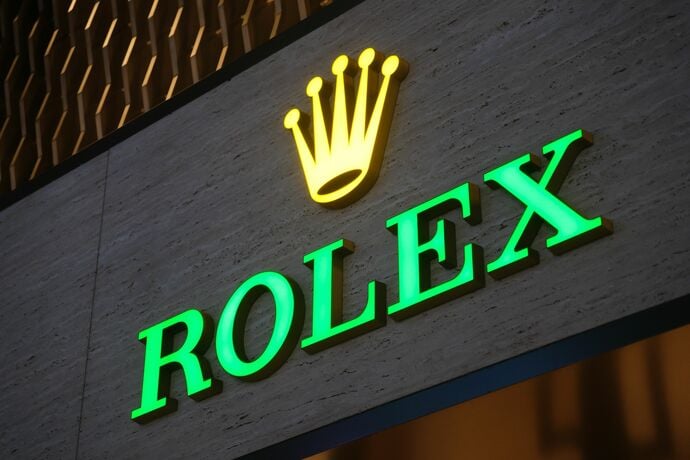写真提供:共同通信社
写真提供:共同通信社
トランプ政権の不透明な関税策、ロシアによるウクライナ侵攻、米国による対中半導体規制、台湾有事リスク、欧州の気候変動規制──。地政学・経済安全保障に関するリスクが拡大・深刻化する中、企業の事業活動が危ぶまれるケースが年々増えている。こうしたリスクによるビジネスへの悪影響を最小限に抑えるべく、企業はどのように向き合い、備えるべきか。本稿では『ビジネスと地政学・経済安全保障』(羽生田慶介著/日経BP)から内容の一部を抜粋・再編集。国家間の政治力がぶつかり合う現代の国際経済社会において、ビジネスパーソンが押さえておくべき地政学・経済安全保障リスクと対応策を考える。
常態化する国家間対立により、日本のサプライチェーンには今どのような影響が生じているのか。また、特定国への過度な依存がもたらす経済安保上のリスクとは?
※本記事は、2025年1月時点の情報に基づいています。
10大リスク_サプライチェーンの混乱
地域紛争や制裁による供給途絶
地政学・経済安保リスクといえば、サプライチェーンの混乱が最初に思い浮かぶだろう。
1973年に第4次中東戦争を契機に生じた石油危機は、その典型例だ。ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ自治区ガザでの武力衝突などの中東情勢の悪化を見て、エネルギー供給が不安定化することを懸念した人も多いだろう。
実際、2022年2月のロシアのウクライナ侵攻後には、西側諸国による対ロ制裁の影響もあり、石油や天然ガスの価格は一時大きく上昇した。
また、ロシアやウクライナが主要供給国であるネオン(半導体製造用ガス)やパラジウム(自動車排ガス触媒、半導体メッキ)などの調達に支障が出ることが懸念された。住友電気工業などは、ウクライナでのワイヤハーネス生産を停止し、輸出も途絶えた。それによって、欧州での自動車生産が減産や停止に追い込まれた。
2023年11月には、ガザ情勢が飛び火した紅海で日本郵船の自動車輸送船がイエメンの反政府武装組織フーシ派に拿捕(だほ)され、乗組員25名が拘束された(2025年1月解放)。フーシ派による紅海を通航する船舶への襲撃が続き、これに米英軍がミサイル攻撃などで反撃したため、欧州からスエズ運河・紅海を経てアジアへ向かう航路は安全な運航が不可能になった。