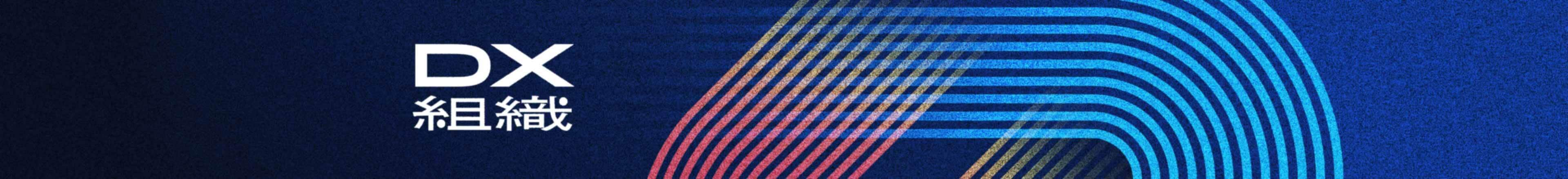出典元: yu_photo / Shutterstock.com
出典元: yu_photo / Shutterstock.com
イオングループがデータ活用を本格化させている。本部直結の「データイノベーションセンター」(DIC)では、グループ各社が保有するデータの内容やデータ活用状況を集約・分析して、グループ全体でのベストプラクティスの共有を図る。イオン チーフデータオフィサー(CDO)兼DICセンター長の中山雄大氏に、同センターの設立の狙いや活動内容について話を聞いた。
DIC設立の背景とは
──イオングループでは2021年3月に本部直結の「データイノベーションセンター」(DIC)を設立しました。DICとはどのような組織で、どんなミッションを掲げているのでしょうか。
中山雄大氏(以下、敬称略) DICは、イオングループのデータ活用のポテンシャルを最大限発揮するために設立された専門組織です。食品スーパーや金融サービス、アパレル、娯楽など、さまざまな事業を営むグループ会社と連携し、それぞれが保有するデータを分析しています。
分析結果を基に各事業会社が現場で打つべき最適な施策、つまりベストプラクティスを生み出すことが、DICの大きなミッションです。
──イオンがDICを設立した背景にはどんな問題意識があったのですか。
中山 イオンとしては、データの利活用の巧拙が、企業の競争力を左右する時代になったという強い認識があったのだと思います。
例えば、食品スーパーの年間の商品政策(MD)に「52週MD」というものがあります。メーカーや生産者と協力し、年間のMDのスケジュールを年始に決め、その計画通りに進めていくのですが、これは時代の変化とともに見直しが必要になってきています。
インターネットやSNSが普及しておらず、どの家庭の食卓も季節ごとに大体同じようなメニューを並べていた時代においては食品スーパーは基本的に52週MDを遵守することで売り上げを確保できていました。
ところが現代は家族の形が多様化し、消費者の嗜好(しこう)も細分化しています。加えて食品スーパーの競合もECサイトやドラッグストアなどに広がっています。こうした環境では、小売業は「どれだけ商圏の顧客を細かく理解し、彼らに対して訴求力のあるMDを打てるか」が結果を左右するのです。では、イオンはどうやって“真の顧客理解”を実現するのか──。