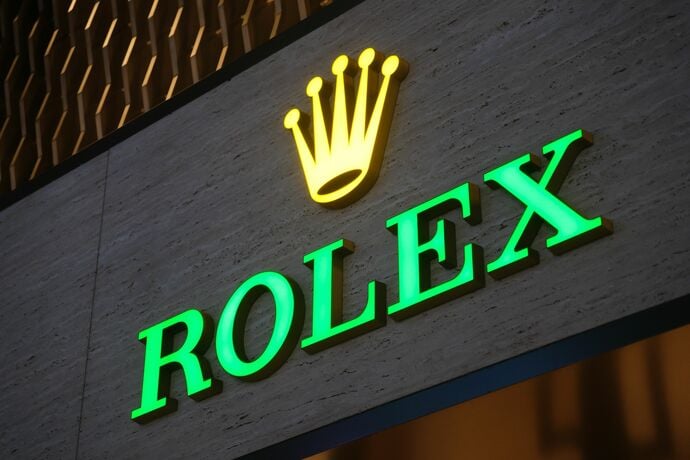東証がプライム、スタンダードの上場企業に「資本コストや株価を意識した経営」を要請したことを受け、自社の資本コストを開示する企業が増加。
東証がプライム、スタンダードの上場企業に「資本コストや株価を意識した経営」を要請したことを受け、自社の資本コストを開示する企業が増加。写真提供:共同通信社
近年のアクティビストの活発な動きに代表されるように、企業支配権が市場原理の下で売買される「企業支配権市場」に注目が集まっている。本連載では『アクティビストと企業支配権市場 日本企業に変革と再編を迫るマーケットの猛威』(大熊将八著/金融財政事情研究会)から、内容の一部を抜粋・再編集。上場企業がアクティビストと向き合うための実践的対応法を考えていく。
今回は、資本コストを意識した経営、投資家との対話に欠かせない情報開示のポイントについて解説する
企業価値向上プランと「資本コストを意識した経営」
 『アクティビストと企業支配権市場: 日本企業に変革と再編を迫るマーケットの猛威』(金融財政事情研究会)
『アクティビストと企業支配権市場: 日本企業に変革と再編を迫るマーケットの猛威』(金融財政事情研究会)
東京証券取引所が2023年3月にプライム市場及びスタンダード市場の全上場企業に「資本コストや株価を意識した経営」を要請したことを受けて、自社の資本コストを開示する企業が増加した。
こうした取り組み自体は望ましいものの、会社側が算出した資本コストが投資家の実感と乖離する水準であった事例や、ファイナンス理論を通り一遍に当てはめただけの現状分析にとどまる事例なども散見された。
この点、資本コストは特定のアプローチにより一意に定まるものではなく、同業他社との比較や投資家との対話の結果も踏まえ、おおよその水準感を正しく把握することが自社分析の前提となる。
また、適切な資本配分が行われているかという点は投資家にとって大きな関心事であり、昨今はキャピタルアロケーション方針を開示する上場企業も多い。特にキャッシュリッチ企業であれば、手元現預金の水準の考え方についても、開示資料や投資家との対話のなかで明示することが望ましい。加えて、成長投資への分配について、資本規律を欠いた投資計画は後述のケーススタディが示すように、株主からの信任を失う可能性が高い。
資本規律の有無はガバナンスの良し悪しに直結する問題だからである。経営計画の背後にある意思決定プロセスやストーリーについて、投資家と共通の言語でコミュニケーションを行い、長期的な信頼関係を構築する必要がある。