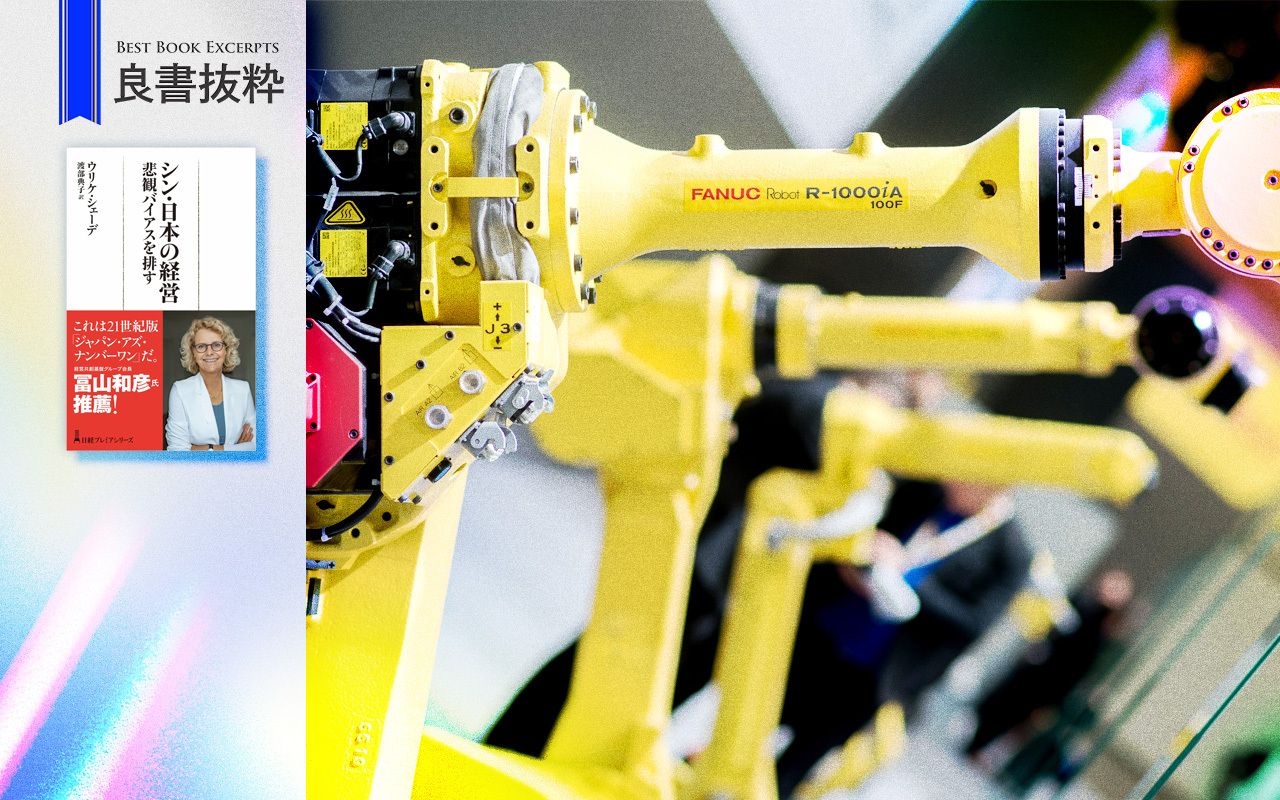 写真提供:DPA/共同通信イメージズ
写真提供:DPA/共同通信イメージズ
今や「衰退するかつての先進国」と語られる日本。「失われた30年」を経て、少子高齢化、政府の債務、賃金水準の低迷といった厳しい現実に直面している。とはいえ、人口が世界12位なのにGDPは世界4位の経済大国だ。ということは、日本には独自のビジネスの強みがあるに違いない――。本連載では、一橋大学経済研究所や日本銀行、経済産業省、財務省で研究員・客員教授を歴任したウリケ・シェーデ氏(現・カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル政策・戦略大学院教授)の著書『シン・日本の経営 悲観バイアスを排す』(ウリケ・シェーデ著、渡部典子訳/日経BP日本経済新聞出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。「変貌を遂げ再浮上する日本」にスポットを当て、その立役者である成功企業の強みを分析し、学びを得る。
第2回は前回に続き、日本経済が低迷していた2000年代初めに高収益を上げた企業を分析し明らかになった「7つの特徴」のうち、残りの5つを解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 キーエンス、ファナックなど優れた「シン・日本企業」に共通する7つの「P」とは?
■第2回 市場変化の「不意打ち」に備え、キーエンスとファナックが取っていた共通の対策とは?(本稿)
■第3回 富士フイルム、AGC、イビデン…「シン・日本企業」は、なぜ中核事業の再興を継続できたのか?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
⑶ 危機意識(Paranoia)
 『シン・日本の経営』(日本経済新聞出版)
『シン・日本の経営』(日本経済新聞出版)
1996年、インテルのCEOを長年務めたアンドリュー・グローブは著書『パラノイアだけが生き残る』(日本経済新聞出版、2017年)の中で、企業が長期にわたって成功し続けるためには、名声に安住することはできず、常に危機意識を持って、新技術や新しい競合に目を光らせなければならないと論じた。
同様に、私が話を聞いたシン・日本企業は、急速な市場変化に不意打ちを食らうことをしきりに心配していた。技術的な破壊や新市場の発展を見通そうとするほか、極端に競争的で、新製品開発、顧客との関係性、戦略策定に多額の資金を投じていた。
今日でも、上位2社となったキーエンスとファナックはこうした行動で知られている。しかし、他の企業も、常に先に進まなければならないという危機感を持っている点で共通していた。
また、この「後を追われる」感覚によって、依存関係を弱めることにも非常に熱心だった。こうした企業の大半は系列の中核メンバーではなく、メインバンクにもほとんど依存しない。複数の顧客企業を持ち、グローバルで販売する傾向が見られた。特定の取引パートナーと緊密な関係が維持されるかぎり、通常は排他的ではなく、細心の注意を払って展開していた。
⑷ 効率性(Parsimony)
Parsimonyは倹約や節約を意味する言葉だが、コスト低減は通常、利益を増やすための第一歩となる。日本企業がコスト削減について語るときには、生産工程の効率化と、おそらく人員削減を指すことが多い。しかし、そこで終わりがちで、伝統的な慣行である報連相(報告、連絡、相談)、永遠に続く会議、見るからに意味のない報告書の提出など、事務レベルではどちらかというと非効率的なやり方を続けている。
ランキング上位企業の多くは、こうした事務的な非効率性をなくすことを狙った経営慣行を整備していた。「物事を完了させる」ことが善しとされ、可能なかぎり手続きを省く。その一例として、私が気づいた点を挙げると、彼らは短い言葉のほうが速いからという理由で、常に丁寧ではあるが、過度に敬語を使わないようにしていた。
話を聞こうとアポイントをとる場面でも、すぐに日程調整ができた。電子メールは、少なくとも日本の標準からすれば、端的で短かった。第7章で詳しく見ていくとおり、企業カルチャーを変革するマネジメントは難しいが、やってやれないことではない。リーダーが日頃の社内手続きの効率化に向けて企業カルチャーを変えようと取り組む要素がいくつも見られた。
倹約と集中の別の側面はスピードだ。意思決定のスピードが速い中小企業、特にオーナー系企業は簡単に見つかるが、私が研究したのはほとんどが大企業だ。それでも多くの場合、従業員は明確で広く共有された目標に集中しているように見えた。自社がどこに向かっているのかを心得ており、繰り返し質問する必要はない。それどころか、担当範囲内であれば自分で意思決定できるので、いちいち確認する必要が減って、全員が集中しやすくなっていた。









