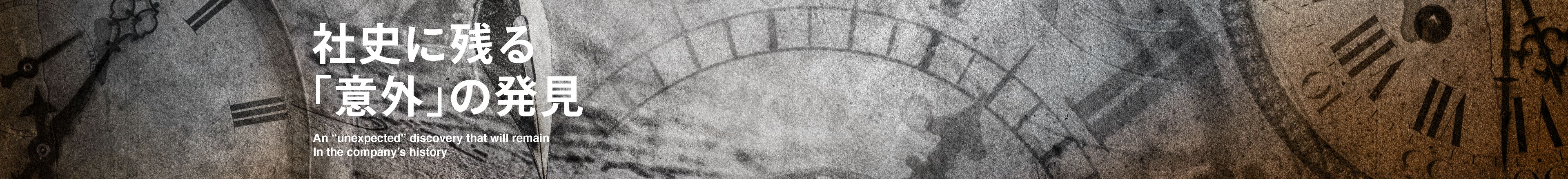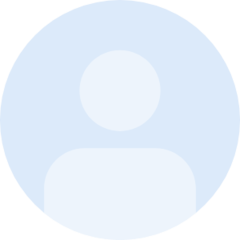レンゴー 創業者・井上貞治郎(画像提供:レンゴー)
レンゴー 創業者・井上貞治郎(画像提供:レンゴー)
数多くの転職と長年の放浪生活の末に再出発を決意
段ボール箱の誕生以来、1世紀以上の歴史を歩んできたレンゴー。創業者・井上貞治郎(ていじろう)は、1909年4月12日、東京・上野公園の満開の桜の下で、持ち金の十銭玉を握りしめ、「これまで、偉うなったろという気概だけで40回近くも職を変え、14年間も放浪生活を送ってきた。しかし、俺は今27歳。裸一貫から再出発だ」と、決意を固めた。その時、具体的な事業の計画や確たる技術があったわけでもない。しかし、後に、この4月12日を同社の創立記念日と定めた。
井上は1881年、兵庫県揖保(いぼ)郡上余部村(かみあまるべ)(現・姫路市郊外)で、農業を営む長谷川家の三男として生まれたが、2歳の時、同じ村の農家・井上家に跡目相続人として入籍、姓を井上ととなえた。14歳で、神戸きっての商家「座古清(ざこせい)」に丁稚奉公に出たが、仕事は雑用ばかり。将来独立をと思っていたが、別家を許されるには20年もかかると分かり、神戸市の洋紙店に移った。
しかし、主人が病気がちで店が陰気くさく、商売も覚えられず、1年で店を辞めた。次に住み込んだ回漕店(船による運送業)では、夜、店員たちが博打や郭(くるわ)通いばかり。「こんな所にいたら身の破滅だ」と思った。ある休日「お伊勢参り」を思い立ち、伊勢に向かったが、途中で懐具合が寂しくなって、帰りの汽車賃が足りない。しかし、横浜までの船賃ならある。「よし、東京へ出て一働きしよう」――これが、その後の長い放浪生活の始まりだった。
活版屋の住み込み店員、中華料理屋の出前持ちや皿洗い、銭湯、パン屋、散髪店の小僧・・・、職を転々と変えたのは「商売で偉うなるには、雑用ばかりではダメだ」と思ったからだ。いったん関西に戻ったが、砂糖屋、洋服屋、材木屋と、どれも3日と続かない。唯一、石炭屋で、談合無視の大量落札をやったり、仲買人に転じてかなり稼いだりもしたが、放縦な生活がたたって、結局失敗に終わった。
日露戦争後、人々の目は満州(現・中国東北地方)に向いていた。一旗揚げたいともくろむ井上は、25歳で新天地・満州へ渡った。しかし、もともと当てがあったわけではない。雑貨屋、砂利取りの監督、豆腐屋、餡巻売りと、飛び込みやヒョンなきっかけで仕事を得ても報酬はわずか。心身両面疲れ果て日本へ帰ることにしたが、カネがない。ある日、宿の隣部屋の客の本業が人身売買だと知り、半ば脅して、神戸に連れ帰ってもらった。帰国後、東京・上野まで同行した件の男は、別れ際に10銭玉1個と古毛布をくれた。それが4月12日だった。
東京で心機一転を図って、紙箱や大工道具の販売店「中屋」の外交員の口を見つけ、住み込みでない代わりに1日10銭の宿賃が支給された。昔、大阪で石炭の外交で腕を振るった経験が物をいい、稼ぎも増えて、間もなく店の近くに2畳間を借りた。「人間、起きて半畳、寝て1畳あれば生きられる」。ここで探り当てた思索は、後年「金(きん)と間(ま)(好機)は握ったら離すな」という「きんとま哲学」の原点になった。
独立の契機になったのは、中屋の店の片隅にあったある機械に目を留めたことだ。主人に尋ねると「段ロールといって、ボール紙をグネグネと曲げる道具だ。電球や瓶などを包む緩衝材になる」という。井上はその機械に強く引かれたが、全く新しい“紙を扱う商売”より、パン屋でもやる方がいいか…。迷って稲荷降(いなりおろし)で占ってもらうと、白髪の巫女が「紙じゃ、紙じゃ、紙の仕事は立て板に水じゃ」と叫んだ。