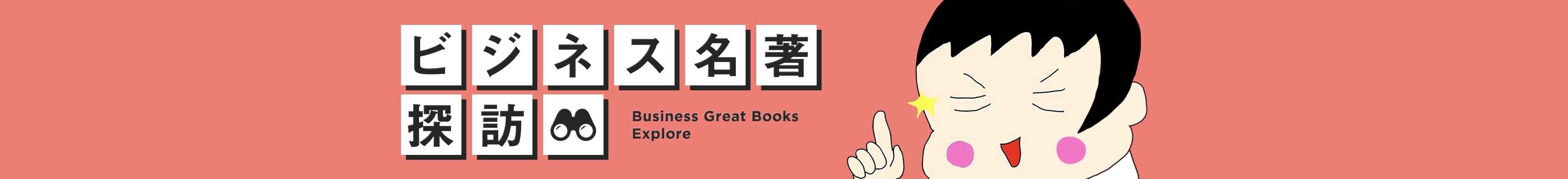ビジネス書の名著・古典は多数存在するが、あなたは何冊読んだことがあるだろうか。本連載では、ビジネス書の目利きである荒木博行氏が、名著の「ツボ」を毎回イラストを交え紹介する。
連載第10回は、世界屈指のビジネススクールINSEADの著名教授が新市場を創造する戦略を体系化し、世界350万部43カ国語で出版されたベストセラー『ブルー・オーシャン戦略』(W・チャン・キム、レネ・モボルニュ著/入山章栄監訳/有賀裕子訳、ランダムハウス講談社、『[新版]ブルー・オーシャン戦略』は著訳者同、入山章栄監訳/ダイヤモンド社)を取り上げる。
「レッド・オーシャン」のマインドセットとは?
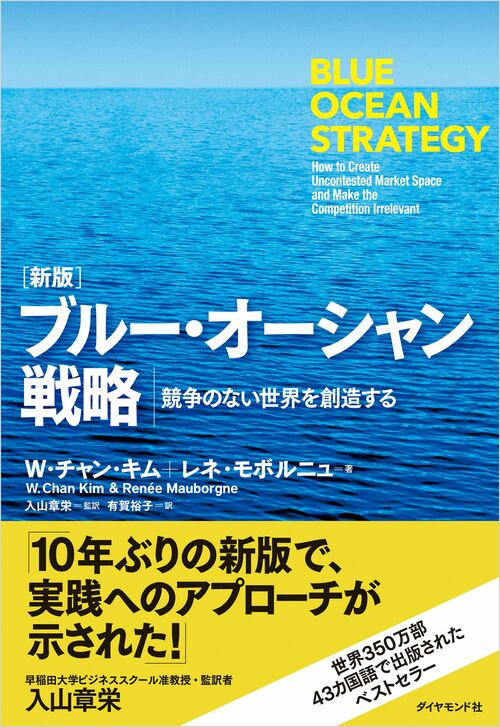 『[新版]ブルー・オーシャン戦略』(W・チャン・キム、レネ・モボルニュ著/入山章栄監訳/有賀裕子訳、ダイヤモンド社)
『[新版]ブルー・オーシャン戦略』(W・チャン・キム、レネ・モボルニュ著/入山章栄監訳/有賀裕子訳、ダイヤモンド社)
以前、とある大企業の役員と話している時のことだ。あまり利益率が上がらないことを嘆いて、その役員は半分冗談混じりで、私にこんな愚痴をこぼした。
「うちの業界なんて、血みどろのレッド・オーシャンのようなもんですわ。競合がわんさかいて、殴り合いをしている。うちはまだ強力な武器があるので、何とか業界2〜3位にいられてますけどね。競合がいないブルー・オーシャンなんてもんはなかなか見つかりはしないもんですな。がはは」
皆さんは、ここで語られている「レッド・オーシャン」や「ブルー・オーシャン」という言葉の意味は理解できるだろう。
もう既にビジネスの日常用語となっているこの言葉の原典は、ハーバードビジネスレビューで2004年に発表された『ブルー・オーシャン戦略』にさかのぼる。
20年前の論考ではあるが、いまだに全く色あせないメッセージがある。読んだことがない人はもちろん、かつて読んだ方も改めて目を通してほしい。単なる「ブルー・オーシャン」や「レッド・オーシャン」という言葉以上に、いろいろな発見に溢れているはずだ。
例えば、冒頭のとある役員の愚痴を見てみよう。この発言だけを取り上げてとやかくいうのもどうかと思うが、このような発言をしている限り、この会社はレッド・オーシャンに居続ける可能性が高いことが推察される。なぜならば、この発言は、「レッド・オーシャンのマインドセット」にどっぷり浸かっているからだ。

では、その「レッド・オーシャンのマインドセット」とは何か? それは、「業界意識の強さ」と「好戦的態度」だ。つまり、「自分たちは◯◯業界にいる」という強烈な刷り込みがあり、そしてその中で競合を倒して順位を高めることが大きな価値判断になってしまっていることだ。
そして、「武器」に代表されるような戦争用語は、そのようなレッド・オーシャンのマインドセットを助長させる(その他にも、ビジネスで使われる戦争用語には例えば「ゲリラ戦」「戦犯」「兵站」といった言葉がある)。
とくに、「武器」という言葉を多用する企業は多いはずだ。「武器」とは、一般的には「他社と比較して優れている(競争力のある)プロダクトや技術」という意味で使われる。しかし、この「武器」という言葉に暗黙に含まれる「競争優位性」という発想が間違っているのだと本書は以下の通り指摘する。
「ブルー・オーシャンを創造する企業は、レッド・オーシャンで競争する企業とは対照的に、自社の競争力についてベンチマーキングなどしない。むしろ自社と顧客双方の価値を飛躍的に高めることで、競争とは無縁の存在になっている」