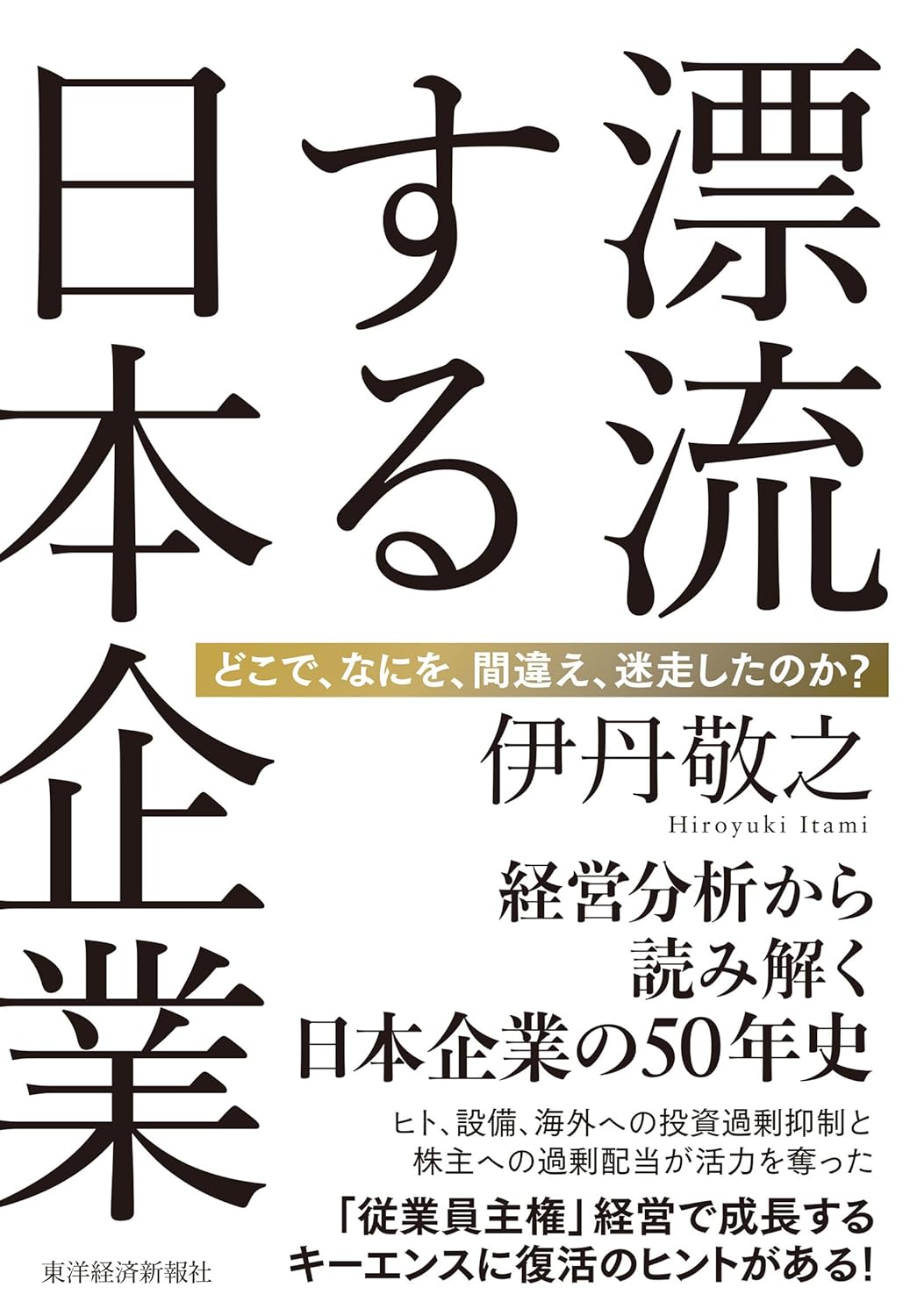一橋大学名誉教授 伊丹敬之氏(撮影:今祥雄)
一橋大学名誉教授 伊丹敬之氏(撮影:今祥雄)
日本の大企業は、従業員よりも株主を偏重し、本来必要な投資を怠る経営に変わってしまった──。一橋大学名誉教授 伊丹敬之氏は、2023年12月に出版した『漂流する日本企業:どこで、なにを、間違え、迷走したのか?』(東洋経済新報社)において、バブル崩壊以降「漂流」を続ける日本の大企業に警鐘を鳴らしている。日本企業は「失われた30年」で何を見誤ったのか。その結果、どのような事態をもたらしたのか。前編となる本記事では、伊丹氏が問題視する日本企業の行き過ぎた投資抑制や、それによって引き起こされた「負のサイクル」について話を聞いた。(前編/全2回)
■【前編】一橋大・伊丹名誉教授が日本企業に警鐘、配当重視経営の恐るべき副作用とは(今回)
■【後編】キーエンスの強さの秘密、「従業員主権」経営を徹底実践する3つのポイント
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
日本企業は「潮の流れに受け身で流されてきた」
 伊丹 敬之/一橋大学 名誉教授
伊丹 敬之/一橋大学 名誉教授1945年愛知県豊橋市生まれ。一橋大学商学部卒業。カーネギーメロン大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。一橋大学大学院商学研究科教授、東京理科大学大学院イノベーション研究科教授を歴任。2017年から2023年まで国際大学学長を務める。2005年11月紫綬褒章を受章。2023年10月、経営学の分野で初の文化功労者に選ばれる。主な著書に『日本企業の多角化戦略』(共著、日経・経済図書文化賞受賞)、『日本型コーポレートガバナンス』(以上、日本経済新聞社)『経営戦略の論理〈第4版〉』『中二階の原理』『経営学とはなにか』(以上、日本経済新聞出版)、『場の論理とマネジメント』『経営を見る眼』『経済を見る眼』『直感で発想 論理で検証 哲学で跳躍』(以上、東洋経済新報社)、『人本主義企業』(筑摩書房)、『本田宗一郎』(ミネルヴァ書房)、『高度成長を引きずり出した男』(PHP研究所)がある。
――著書『漂流する日本企業:どこで、なにを、間違え、迷走したのか?』では、「失われた30年」の日本企業の姿について、さまざまな統計データを交えながら解説しています。「漂流」とは、具体的に何を意味するのでしょうか。
伊丹敬之氏(以下敬称略) 本書に記した「漂流」は2つの事柄を指します。
第1の漂流は、企業が成長を目指す上で重要な「3つの投資」を増やす、という考え方が無意識に忘れられ、株主配当ばかりを増やしてしまったことです。3つの投資は「設備投資・海外展開投資・人材投資」を指しますが、いずれも過度に抑制されていたことが統計データから読み取れるのです。
第2の漂流は、第1の漂流の背後にある「原理の漂流」を指しています。かつての日本企業は、従業員を大切にする経営原理、いわゆる「従業員主権経営」によって高度成長期や安定成長期を支えてきました。しかし、アメリカのアクティビストや機関投資家からの圧力を受け、日本企業の経営原理が揺らぎ、流されるように配当ばかりを増やしてしまったのです。
日本企業は30年間、荒波にもまれながらも懸命に、さまざまな対応をしてきました。しかし、自分の確固たる意志で何かに向かって動いているのではなく、潮の流れに流されてきたように感じます。本書では、その状況について、統計データの分析を交えながら考察しています。