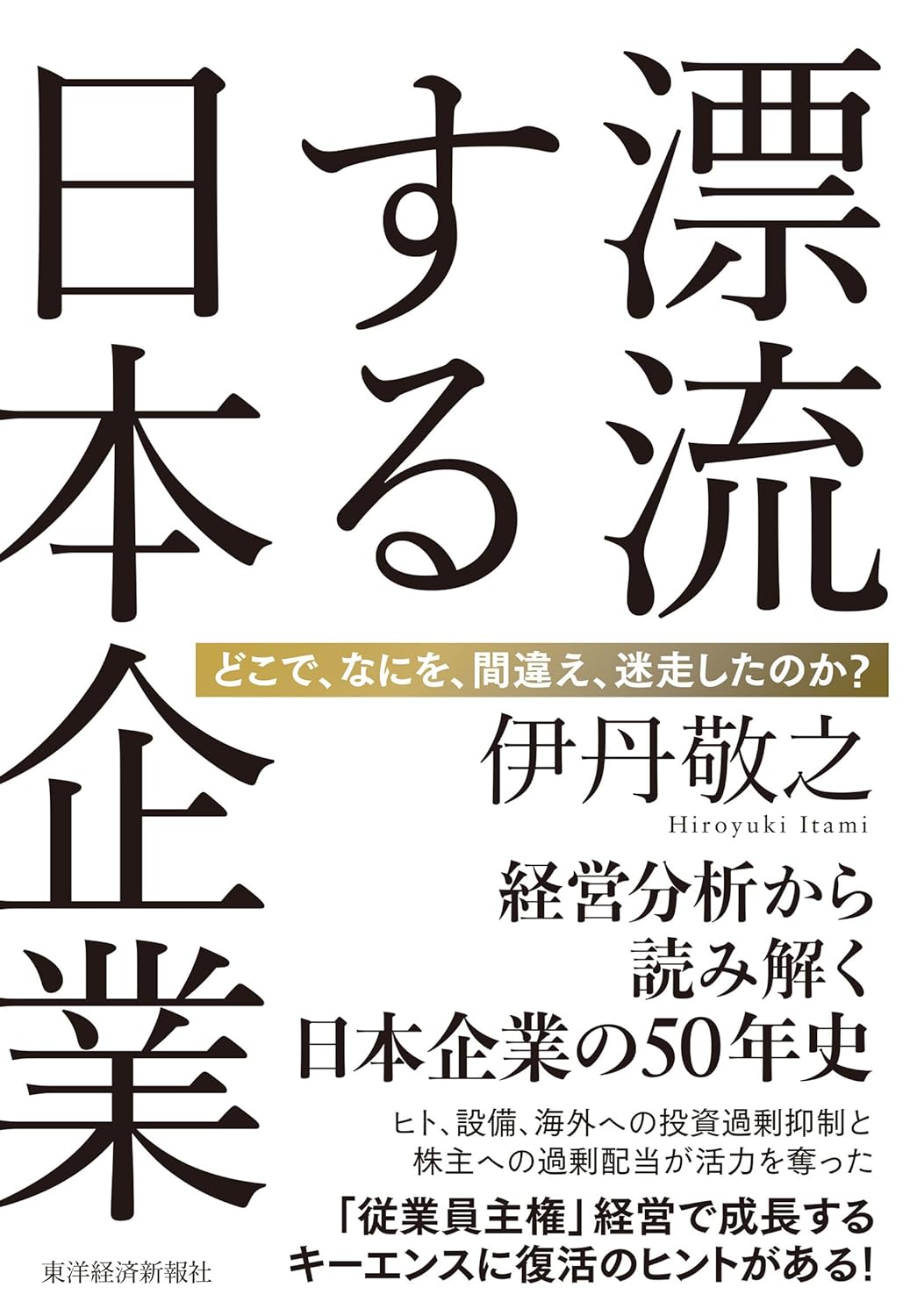一橋大学名誉教授 伊丹敬之氏(撮影:今祥雄)
一橋大学名誉教授 伊丹敬之氏(撮影:今祥雄)
日本企業は21世紀に入り、「アメリカ型資本主義こそグローバルスタンダード」とする空気に流され、その経営原理を“漂流”させてしまった――。一橋大学名誉教授の伊丹敬之氏は、著書『漂流する日本企業:どこで、なにを、間違え、迷走したのか?』(東洋経済新報社)において、日本企業の成長が停滞した根本的な原因を指摘する。前編に続く本記事では、日本企業が忘れ去ってしまった従業員主権の原理と本質、そのモデルケースとなる高収益企業「キーエンス」の経営手法について聞いた。(後編/全2回)
■【前編】一橋大・伊丹名誉教授が日本企業に警鐘、配当重視経営の恐るべき副作用とは
■【後編】キーエンスの強さの秘密、「従業員主権」経営を徹底実践する3つのポイント(今回)
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
株主傾斜によって起こった「従業員主権からの漂流」
 伊丹 敬之/一橋大学 名誉教授
伊丹 敬之/一橋大学 名誉教授1945年愛知県豊橋市生まれ。一橋大学商学部卒業。カーネギーメロン大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。一橋大学大学院商学研究科教授、東京理科大学大学院イノベーション研究科教授を歴任。2017年から2023年まで国際大学学長を務める。2005年11月紫綬褒章を受章。2023年10月、経営学の分野で初の文化功労者に選ばれる。主な著書に『日本企業の多角化戦略』(共著、日経・経済図書文化賞受賞)、『日本型コーポレートガバナンス』(以上、日本経済新聞社)『経営戦略の論理〈第4版〉』『中二階の原理』『経営学とはなにか』(以上、日本経済新聞出版)、『場の論理とマネジメント』『経営を見る眼』『経済を見る眼』『直感で発想 論理で検証 哲学で跳躍』(以上、東洋経済新報社)、『人本主義企業』(筑摩書房)、『本田宗一郎』(ミネルヴァ書房)、『高度成長を引きずり出した男』(PHP研究所)がある。
――著書『漂流する日本企業:どこで、なにを、間違え、迷走したのか?』では、リーマンショック以降の大企業の経営を「従業員主権からの漂流」と表現されていますが、これはどのような状態を指すのでしょうか。
伊丹敬之氏(以下敬称略) 企業が従業員のベネフィットを考え、人が育つことを中心に考える経営が「従業員主権経営」です。
戦後の日本企業の成功の多くは、企業が「従業員のための経営」をすることで達成されてきたと考えています。しかし、昨今の大企業は株主の方を向き過ぎており、相対的に従業員を軽視しているのです。こうした状態を「漂流」と表現しています。
もちろん、資金がなければ株式会社は成立しませんから、株主は必要です。一方、そこできちんと働く人や経営する人がいなければ企業は成立しません。「カネも必要、ヒトも必要」ということです。
しかし、株式会社制度においては、企業の方向性を決めるような経営決定は「株主が行う」とされています。この制度の中では、資本多数決の法則、つまり「株式資本をどのくらい出したか」という量的指標を基に、議決権の大きさが決まります。BさんがAさんの10倍資本を出したならば、BさんはAさんの10倍、権力を持っていることになります。人と人の間で意見の対立があった場合でも解決しやすいシンプルなルールです。
私は経営上の意思決定を「株主が行う」という制度自体には賛成です。しかし、株主「だけ」が主権を持つ、というわけではないはずです。
先進国の中でも日本とドイツは、従業員も実質的に経営決定に参加するスキームを実践してきた国です。それぞれやり方は違いましたが、戦後、この2つの国の経済は急成長を果たしました。しかし、昨今の日本企業を見ると、株主にばかり目が向いている状態です。