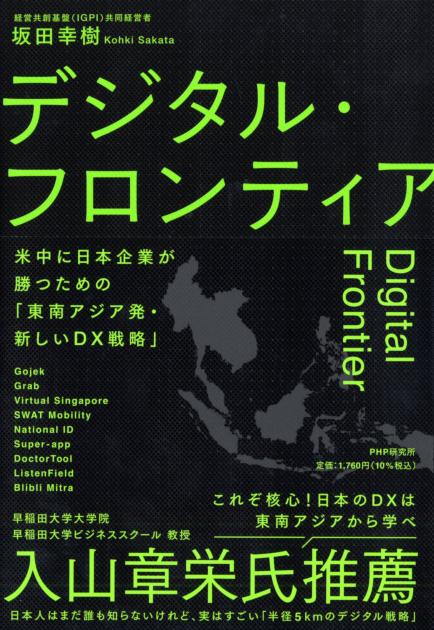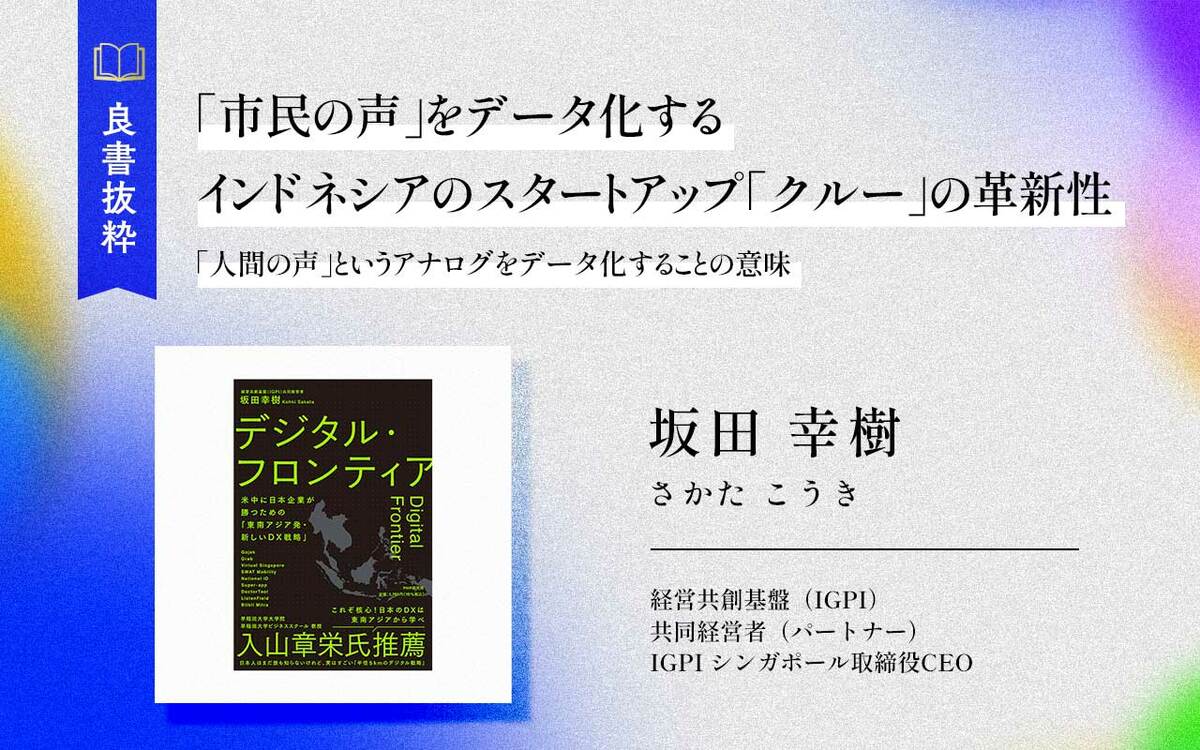
シンガポールに在住し東南アジアに精通したコンサルタント・坂田幸樹氏が、東南アジアと日本社会の共通点を紐解きながら、日本企業のDXやイノベーションにどう生かすかを解説した書籍『デジタル・フロンティア 米中に日本企業が勝つための「東南アジア発・新しいDX戦略」』(PHP研究所)から一部を抜粋・再編集して掲載している本連載。
第3回となる本稿では、インドネシアのジャカルタで州政府とともにスマートシティ構想の実現に向けた取り組みを行っているスタートアップ「クルー」の事例を紹介。同社では、市民にスマホアプリを提供し、交通渋滞やごみ問題などを市民が州政府に報告できるような仕組みを構築している。同社の具体的な取り組みと、「市民の声」というアナログをデータ化することの意味を見ていこう。
<連載ラインアップ>
■第1回 インドネシアのユニコーン企業・ゴジェックに見る、日本と東南アジアの共通点
■第2回 既得権益でがんじがらめの日本、デジタルで既得権益を乗り越える東南アジア
■第3回 「市民の声」をデータ化するインドネシアのスタートアップ「クルー」の革新性(本稿)
■第4回 タイと日本の地方都市でSWAT社が推し進める、DXの新しい方法論
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
 ■坂田氏が登壇するLIVEウェビナーの配信が決定!詳しくは公式サイトをご覧ください。
■坂田氏が登壇するLIVEウェビナーの配信が決定!詳しくは公式サイトをご覧ください。※外部配信先でご覧の方にはリンクが有効ではない場合がございます。その場合、以下のURLにアクセスしてください。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/76801
知らないところで進むデータ化
世界では私たちが気づかないところで、日々さまざまなものがデータ化されている。
たとえば、消費者がファストフード店のドライブスルーで注文した内容は、音声認識技術によって自動的にデータ化されている。このことで、人間が対応するよりも正確に消費者の注文を把握し、効率的な注文管理を実現している。
また、スーパーマーケットなどのショッピングカートにはRFID(Radio Frequency Identification。電波を用いて情報を非接触で読み書きするシステム)が搭載されていて、消費者の店舗内での移動履歴が記録されている。このデータを店内のカメラやPOSデータと合わせて活用することで、商品の需要予測や、棚割りの最適化が行われている。
こうした取り組みはまさにDXの本流とも呼べるもので、あらゆるところでさまざまな取り組みが行われている。しかし、私が注目するのは、東南アジアにおける「半径5キロ圏内の問題解決」におけるデータ活用である。
市民の声をデータ化する「クルー」の斬新さ
一例を挙げよう。クルー(Qlue)というスタートアップは、2016年からジャカルタ州政府とともにスマートシティ構想の実現に向けた取り組みを実施している。具体的には、クルーは市民にスマホアプリを提供し、交通渋滞やごみ問題などを市民が政府に報告できるようにしている。そして、その報告内容は関連する地方公共団体に自動的に転送され、その後の対応状況を追跡することができる。
たとえば、破壊された道路を見つけた市民は、クルーのアプリに画像をアップロードして州政府に報告することができる。それに対して州政府の担当者は対応状況を画像とともにシステムにアップロードすることが求められ、その対応状況は他の市民もモニタリングすることができる(図4-1)。
日本では行政に何らかの問題を報告したところで、それがどのように処理されたかを知ることはなかなか難しい。しかし、この仕組みならそれが可能になるし、他の市民の目が入っている以上、行政も放置することができない。
そもそも日本では、問題を発見したとしてもどこに通報していいかわからない人も多いだろう。このアプリは気軽な通報を促すことができる極めて優れた仕組みといえる。クルーの創業者によると、日本の愛知県南知多町で住民活動の促進に向けた実証実験を開始しているそうだ。
そして、より重要なのは、クルーは「市民の声」をデータ化している、ということだ。クルーはこうして収集したビッグデータを解析し、都市のさまざまな問題を可視化するための「スマートシティダッシュボード」も開発している。これは、地方公共団体や民間企業による意思決定をデータ・ドリブンにし、ジャカルタなどの都市がスマートシティとして成長するのを支援している。
たとえば、スマートシティダッシュボードではリアルタイムな渋滞情報を可視化している。このデータを基に配送業者が配送計画を作れば、より効率的な配送を実現することができる。また、人流データを基に小売りチェーンが出店計画を作れば、より効果的な立地に出店をすることができる。
こうして、埋もれがちだった「市民の声」や情報が、社会を変えるための貴重なデータとなったのである。