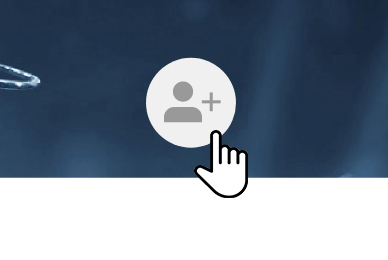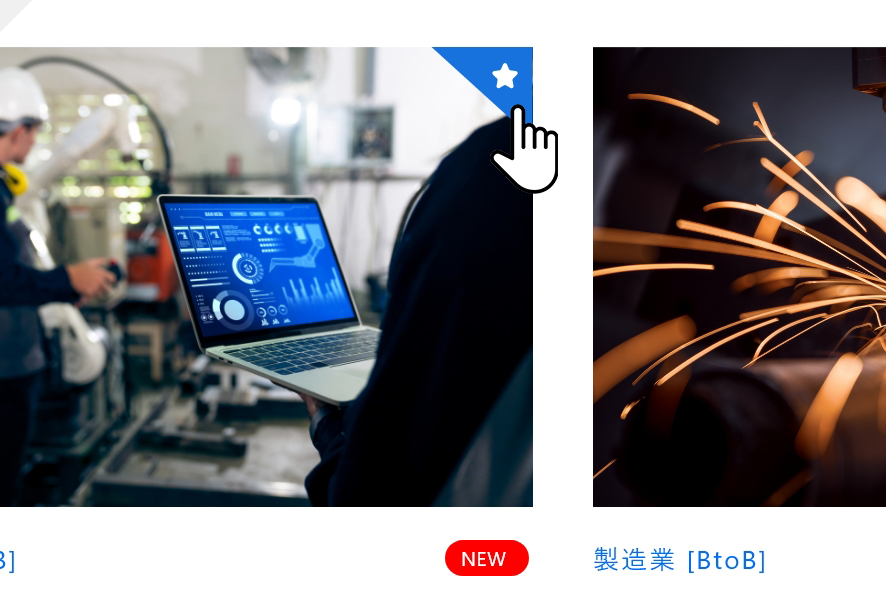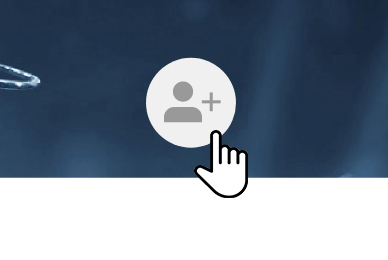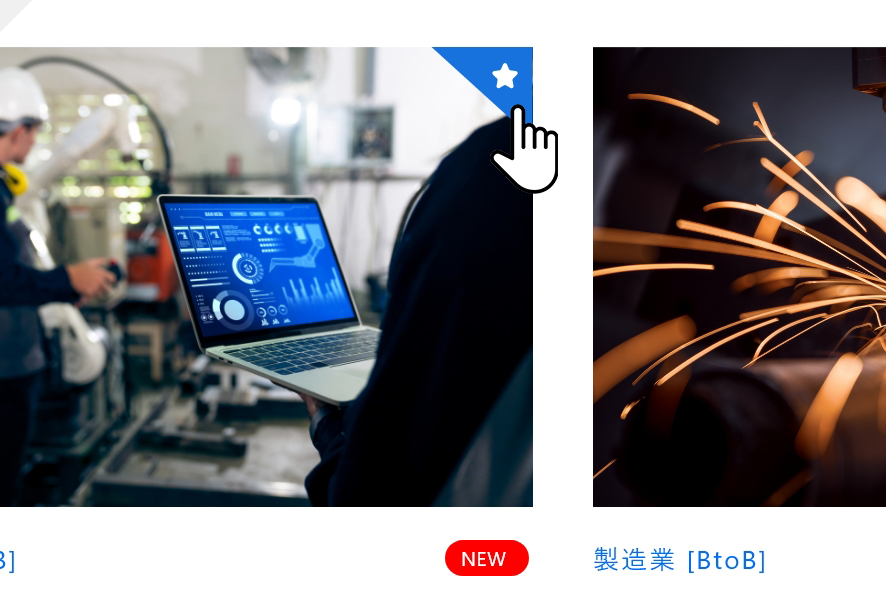ライター/エディター。主に技術系の書籍を中心に企画・編集に携わる。2013年よりフリーランス。技術と人、社会との関わりについての視点から書籍企画、および執筆に携わる。「ビジネス+IT」「日経クロステック」「CodeZine」などに寄稿。著書に『ハッカソンの作り方』(BNN新社、2015)、編著に『オウンドメディアの作り方』(BNN新社、2017)、『エンジニアのためのデザイン思考入門』(翔泳社、2017)、企画編集として『+Gainer』(オーム社、2008)、『ユメみるiPhone』(ワークスコーポレーション、2009)、『iOS×BLE Core Bluetoothプログラミング』(ソシム、2015)、『融けるデザイン』(BNN新社、2015)、『消極性デザイン宣言』(BNN新社、2016)、『エンジニアのためのデザイン思考入門』(翔泳社、2017)、『DevRel エンジニアフレンドリーになるための3C』(翔泳社、2019)、『人工知能のための哲学塾』シリーズ(BNN新社、2016〜2020)などがある。