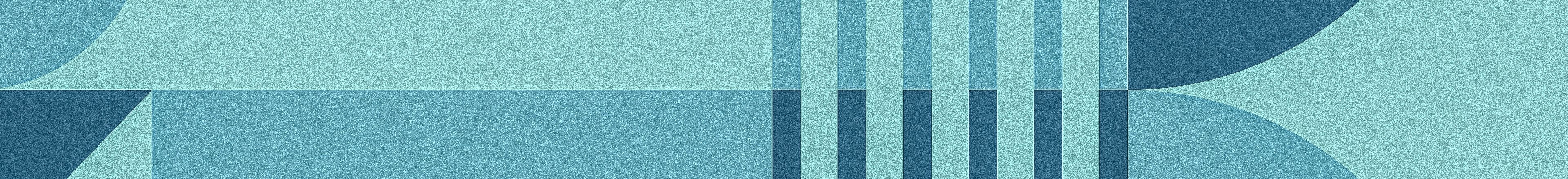データ連携/集約/分析基盤を整備して「息をするようにデータを使いこなす」
冒頭で述べた通り、日清食品グループの全社DX活動であるNBXは、効率化・生産性向上のステージから、ビジネスモデル変革のステージに移ろうとしている。この新しいステージでIT部門が目指すことは何だろうか。
その点について成田氏は、「データ連携/集約/分析基盤の構築」と「データドリブンのカルチャー醸成」の2つを挙げる。

日清食品グループは、2015年に基幹系システムを刷新し、2019年にはサーバーもオンプレミスからクラウド基盤上に移行した。経済産業省が「DXレポート」で指摘したITシステム「2025年の崖」は既に克服している。
しかし、「複数あるシステム間のデータ連携ができていないため、各システムのデータを横断的に分析・活用することができていませんでした」。成田氏は今、この課題を解決しようとしている。
オンプレミスでもクラウド上であってもシステム間のデータを連携できるiPaaS(Integration Platform as a Service)や、各種のデータを一元的に保管・管理できるクラウドベースのデータレイクなどによって構成されるデータを連携/集約/分析する基盤を、現在構築中だ。
また、データドリブンカルチャーの醸成に向けては、まずデータを分析・可視化できるBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを整備した上で、「BIを用いて、社内各所でデータを自由に扱えるリテラシーを高めていきたい」と考えている。
これまでも、一部の部門ではBIツールを使っていたが、全社で見れば活用している社員はわずかで、多くの社員は従来通り、表計算ソフトなどに頼っているのが現状だ。社員にとって使い勝手のいいBIツールを全社レベルで活用し、ツールを使いこなせるようにIT部門がサポートすることで、全体的なリテラシーを底上げしていく方針だ。
さらには、データサイエンティストのような高度な専門知識がなくても、業務に適したアルゴリズムの選定や、AIモデルの構築、ビジネスへの実装ができるオートML(機械学習自動化)ツールの利用も検討している。
ローコードツールなどを使ってさまざまな業務がデジタル化されてきたことで、デジタルデータを取得できる範囲は着実に広がっている。データ連携基盤とBIツール、オートMLを使って、それらのデータを部門横断的に分析・可視化したり、活用したりできるようになれば、ビジネスプロセスやビジネスモデルも自ずと変わっていくはずだ。
例えば、営業部門とマーケティング部門が協働して消費者理解を深める、あるいは、AIによる需要予想に基づいて商品納入先の企業にソリューション提案を行うといったことも可能になる。
「誰もが息をするような自然さでデータを使いこなし、それに基づいて意思決定や価値創造を行うデータドリブンな企業に、日清食品グループを変えていきたい」。それが成田氏の目標である。