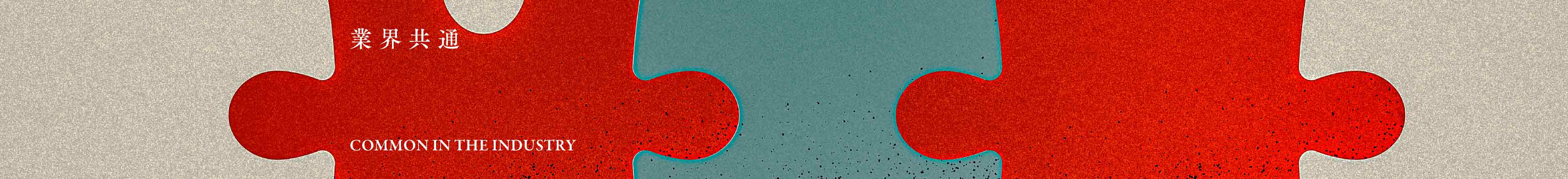また、COVID-19は、人間同士がリアルに会うことで得られる情報や体験、偶然の出会い(セレンディピティ)などの貴重さを再認識させるものでもありました。しかし、そうしたせっかくの機会を紙やハンコとの格闘に費やしているのは、もったいない話です。
ハンコの法的根拠は?
ビートたけしさんは、「離婚体操」というネタの中で、「ハンコ、ポン! シャチハタ、ダメ!」と歌っています。しかし、よくよく考えると、どこでも購入でき、本人写真とも紐付けられていない認印に、IDの役割は期待できません。本人確認はパスポートや運転免許証などの写真付きIDで別途行われるわけですので、むしろ「そもそもなぜハンコが要るのか」、「認印は良いのにシャチハタはなぜダメなのか」のほうが謎といえます。
より広く、取引や契約を考えても、欧州大陸法を継受した日本法では、意思の合致があれば契約が成立し、ハンコは求められません。私は以前、紙やハンコの法律上の根拠がどの程度あるのかを学者の方々と調べたことがありますが、とりわけ「ハンコ」を明示的に要求している法律は、じつはかなり少ないのです。
「紙」については、法律上の記述が散見されます。例えば、民法550条の「贈与」(書面の有無により解除を行えるかどうかが変わる)、民法467条2項の「確定日付のある証書」、2005年に新設された書面による保証契約などです。しかし、例えば「確定日付のある証書」については、電子的な情報に電子署名をすることで、この条件が満たせるようになっています(民法施行法第5条第1項及び第2項)。また、「書面による保証契約」については、電子的方式も認められています。
有価証券は、もともとは紙であることが前提でした(だからこそ、「持参人払い」や「呈示」といった言葉が使われています)。しかし、金融取引の高速化にともない、実務レベルではかなり昔からデジタル化が進んでいますし、近年では有価証券のデジタル化を前提とする法整備も行われました。
「ハンコ」については、法律上の記述はさらに少なく、民法にはハンコに関する記述はありません。他の法律を細かく見ていくと、民事訴訟法228条4項、商法369条3項(取締役会議事録)、刑法159条(有印私文書偽造)などがありますが、2001年に成立した「電子署名法」などにより、「法的に絶対にハンコがなければいけない」という取引は、今ではほとんど無いはずです。