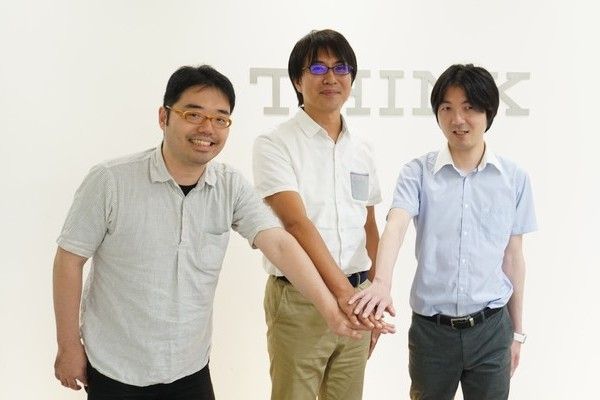 3者の強固なパートナーシップからうまれた、次世代の災害対策
3者の強固なパートナーシップからうまれた、次世代の災害対策
ドローンが被災地を自動管制で飛び回って情報を収集し、ブロックチェーンが自治体や政府機関を結ぶ情報共有基盤に――防災の新たな可能性を示したメジャー企業・スタートアップ・大学の「共創」に迫った。
災害大国日本でブロックチェーンを活用していくために
2019年3月28日、滋賀県甲賀市。公民館の駐車場から1台のドローンが飛び立った。しかし、付近に操縦者の姿はない。自らルートを見出し、自動航行していく機体は河川、そして市内の状況が確認できる画像を逐次送信。市長、消防本部長、危機管理監といった甲賀市危機管理の中枢が模擬的災害対策本部で見守る中、飛翔したドローンが得た情報はブロックチェーンによって速やかに共有されていった――。
自動航行して情報を速やかに入手するドローン、被災情報を自治体間で共有する情報基盤としてのブロックチェーン。2つのテクノロジーによって防災、減災を目指すための第一歩が、ここに踏み出されたのである。
この実証実験は、ブロックチェーンの活用を探るための実証事業の一つとして総務省が主導したもの。日本アイ・ビー・エム(以下IBM)が請け負い、スタートアップのトラジェクトリー、慶應義塾大学大学院が参画。産学官が強固に連携して行われている。まずは、プロジェクトを進めた日本IBMの岡村健一氏に流れを振り返ってもらった。
「総務省の募集に応札したIBMがブロックチェーン基盤の開発と提供を担当し、トラジェクトリー社のドローン技術との組み合わせで進めたかたちになります。ただ、実験では災害時に孤絶するであろう孤立集落の課題を抱える自治体とのマッチングが必須でした。そこで、私が以前在住し、地勢をよく知っていた甲賀市に打診しました。甲賀市は市長が『ビジネスフレンドリーな市でありたい』と宣言し、先進テクノロジーの活用に積極的な自治体です。中山間地域ならではの課題を抱えていたこともあり、前向きに取り組んでいただけました」(日本アイ・ビー・エム グローバルビジネスサービス事業部 ブロックチェーンソリューションズ シニアマネージングコンサルタント 岡村健一氏)
 日本アイ・ビー・エム グローバルビジネスサービス事業部 ブロックチェーンソリューションズ シニアマネージングコンサルタント 岡村健一氏
日本アイ・ビー・エム グローバルビジネスサービス事業部 ブロックチェーンソリューションズ シニアマネージングコンサルタント 岡村健一氏
空にドローン、サイバーにブロックチェーン。新システムの真価とは
実証実験のキーテクノロジーであるブロックチェーンは、仮想通貨をはじめとする金融分野で認知度が高まってきたが、信頼性の高い情報共有システムを低コストで構築できるのも特徴の一つである。様々な分野で実証実験、サービス化が進められているが、今プロジェクトでは災害対策の基盤としての活用を目指した。慶應義塾大学で公共政策のルール形成、ドローンの社会実装などを研究する高橋伸太郎氏は、災害対策へのブロックチェーン活用の意義を力説する。
「災害が発生した時には、災害対策基本法という法律に従って政府機関や自治体が取り組むのが基本です。しかし、広域に渡る災害では都道府県、市町村といった様々な機関が連携して対処していかなければなりません。さらに、政府機関でも警察や消防、海上保安庁、自衛隊といった様々な機関が動きます。これらの多くの機関が正確に、そして速やかに情報を共有しなければ効果的な対処はできません。復旧・復興のフェーズに移ると、さらに建設会社、土木会社、保険会社などの民間企業も加わってくるでしょう。
しかし、これらの機関、企業が災害情報を一元的に共有し、連携するための基盤はいまだにありません。災害情報を共有し、多くの組織が連携していくための基盤としてブロックチェーンに大きな期待がかかるゆえんです」(慶應義塾大学 SFC研究所 ドローン社会共創コンソーシアム事務局長 政策メディア研究科特任講師 高橋伸太郎氏)
 慶應義塾大学 SFC研究所 ドローン社会共創コンソーシアム事務局長 政策メディア研究科特任講師 高橋伸太郎氏
慶應義塾大学 SFC研究所 ドローン社会共創コンソーシアム事務局長 政策メディア研究科特任講師 高橋伸太郎氏
情報を収集する「目」となるドローンは、オペレーターを必要としない自動航行技術がキーになる。システムを担当したのはトラジェクトリー。長年にわたって有人機の航空管制システム開発に携わり、ドローン自動航行システムを主事業として起業した小関賢次氏が率いるスタートアップだ。
「甲賀市の防災担当者は『人が行かなくても被災情報が集められるのは大きい』と口々に感想を述べていました。甲賀市は圏域が広く、被災時の状況確認は職員が車で回って行っています。そこで問題になるのが即時対応の体制です。山間部の孤立集落に職員を派遣した場合、往復1時間はかかってしまいます。避難勧告を出すにしても、消防の緊急出動を仰ぐにしても、1時間というタイムロスは大きい。その点、災害が発生したらすぐに飛ばせるドローンは、画像・動画をタイムリーに得ながら検討、判断ができます。災害対応へのスピード感が格段に違ってくるのです。法規制や管理面など、実用化にはまだいくつかの課題がありますが、ゴールイメージを自治体の担当者に体感していただけたことには、大きな意味がありました」(トラジェクトリー 代表取締役社長 小関賢次氏)
 トラジェクトリー 代表取締役社長 小関賢次氏
トラジェクトリー 代表取締役社長 小関賢次氏
機動力だけではない。無人航行もドローンの大きな強みだ。災害対策にドローンを活用する動きは全国の自治体で始まっているが、人員不足が深刻化する中、長期継続的にオペレーターを育成し、活用していく体制づくりは難しい。その点、無人航行システムはオペレーターを育成するコスト、時間も不要で導入がスムーズ。また、航行はシステムが制御するため、オペレーターの経験、技量に依存することもない。
「有人操縦が前提になっていたドローンと、仮想通貨の技術だと認識する方がまだまだ多いブロックチェーン。この2つのテクノロジーの常識を覆し、災害対策のシステムとして統合できたことには、大きな意義を感じています。ご存じの通り、我が国は規制が大変厳しく、前例がないとなかなか物事が進められない、という一面もあります。しかし、これを逆手に取って考えると、前例があったら進められる、とも言えないでしょうか。
今回の実証実験は総務省の予算を使い、総務省担当官の監督の下、滋賀県甲賀市に協力をいただいて実現しました。つまり、これは国レベル、市町村レベルに同時にアプローチできたことになります。この前例を基点にして全国の市町村、そして500~700程度あるとされる全国の消防本部に横展開ができれば、災害への備えを充実させることができます。現場の最前線で働く消防、警察、海上保安庁、自衛隊の方々の生命を守る可能性を高めることもできるでしょう」(高橋氏)
2019年3月に行われた実証実験だが、総務省に採択されたのは2018年11月のこと。日本IBMは実験フィールドを確保すべく甲賀市にコンタクトしつつ、慶應義塾大学・高橋氏と実証実験の要件、内容をすり合わせた。コア技術になるブロックチェーンの基盤、ドローン自動航行システムの開発もIBM、トラジェクトリーが同時並行で行った。
 模擬訓練実施風景(画像は日本IBM提供資料より引用)
模擬訓練実施風景(画像は日本IBM提供資料より引用)拡大画像表示
全体をマネジメントしつつ、ブロックチェーンを開発したIBM、ドローンの自動航行技術に秀でたトラジェクトリー、そして防災へのマッチングを提案し、社会ソリューションとしての実装実現性を高めた慶應義塾大学。4カ月という短期間で実証実験をゴールさせたのは、3者それぞれが発揮する強みのマッチングがあってこそである。
では、「共創」の妙味をいかんなく発揮したこの陣容はどのようにして生まれたのだろうか。時計の針を2018年3月に戻し、IBMとスタートアップの連携が始まった経緯にフォーカスしてみよう。
グローバルに、そしてローカルに。新オープンイノベーションへの期待
2018年3月14日。日本IBMによるスタートアップとの共創プログラム「IBM BlueHub」第4期採択スタートアップのデモデイが開催された。2014年に第1期がスタートしたIBM BlueHubは、参加した多くのスタートアップと大手企業との事業提携を実現させてきた実績がある。スタートアップを支援し、さらに日本発でオープンイノベーションを活性化させようとする意欲的なプログラムなのだ。
 多くのスタートアップが参加し、新規事業を生み出してきたスタートアップとの共創プログラム「IBM BlueHub」。2019年8月現在、プログラム第6期の募集中。(画像は「IBM BlueHub」第4期募集プレスリリースより引用)
多くのスタートアップが参加し、新規事業を生み出してきたスタートアップとの共創プログラム「IBM BlueHub」。2019年8月現在、プログラム第6期の募集中。(画像は「IBM BlueHub」第4期募集プレスリリースより引用)
「3.11の苦しみを二度と繰り返したくない。そのためにもドローンをもっと簡単に飛ばせるようにし、多くの現場で多くの人を助けられれば――」
ステージの上には、災害救助でドローンを活用するための自動航行支援システムをプレゼンするトラジェクトリー・小関氏の姿があった。
「前述の通り、ドローンの飛行ルートを自動で生成する『航行支援』が私たちトラジェクトリーのコア技術です。それによってルート設定時間の大幅な短縮を実現し、迅速な救助や支援を可能にするのです。甲賀市での実証実験では、このコア技術がストライクゾーンになる取り組みができました。
しかし、今になって振り返ると、自治体と折衝を重ね、プロジェクトを進めることは私たちのようなスタートアップが単独で行うのは困難だったでしょう。課題の解決で自治体に応えようとしても、持っている武器は『ドローンを無人で飛ばす』という1つの技術しかありません。しかし、IBMとのコラボでブロックチェーンという武器が加わり、スタートアップが持てる力以上の取り組みができました。あのデモデイからフルパッケージまで…IBM BlueHubを経由したからこそ、初めてたどり着けた地平です」(小関氏)
スタートアップをバックアップし、実証実験を下支えして成功に導いたIBMも大きな手応え、そして未来への広がりを感じている。
「ブロックチェーンをはじめとして、IBMは様々なテクノロジーを持っていますが、ドローンのプロジェクトはありませんし、知見を持つ者も多くはありません。しかし、今回トラジェクトリーとのパートナーシップにより、新たなシーズ、ビジネスの可能性を感じることができました。とんでもない技術を持っているスタートアップと組むことで、IBMが持っている広範な技術がきちんと生かせる。そんな可能性を感じたのです。実証実験には様々な業界の企業に視察していただき、災害対策をテーマにした新たな共創も始まりつつあります」(岡村氏)
オープンイノベーションは、多くがメジャー企業とスタートアップの共創によって課題解決に向けた革新を狙うものだ。しかし、今回のプロジェクトには慶應義塾大学の高橋氏が加わっている。高橋氏がもたらした視座により、次世代を見すえた取り組みをしていくことの重要性を認識した、と岡村氏、小関氏は口を揃えた。
「技術を組み合わせだけではソリューションの域を脱することはできません。もちろん、目の前の課題を解決するのは重要です。しかし、ムーンショット――困難ではあるものの、実現によって社会に大きなインパクトをもたらすことができる壮大な目標――のような、次世代を見据えた課題に取り組むこと。ここにこそ、オープンイノベーションの意味があるのではないでしょうか。この実証実験はベストなケーススタディになりましたが、今後もIBM BlueHubでは日本発のオープンイノベーションを推し進めて
「たとえば、グローバルな問題として深刻さを増しているマイクロプラスチックごみ問題がありますよね。これも、海洋でどう浮遊し、漂流していくかを多くの国で把握していく情報共有基盤が求められています。そこにはブロックチェーンが存在感を持って活躍できる余地があるでしょう。もちろん、グローバルだけではありません。ローカルでも地域差に即した、きめ細かい災害対策が必須です。今回の実証実験は国レベルの展開も見据えたものでしたが、ローカル版の課題解決を図るオープンイノベーションとして、ローカル版のIBM BlueHub、といったアプローチもあり得るのではないでしょうか」(高橋氏)

スタートアップならではのエッジの効いたテクノロジーを生かし、大企業ならではのマネジメント力・推進力をマッチングさせる。本プロジェクトはスタートアップとの共創プログラム「IBM BlueHub」の理想形として結実した。実証実験としてはピリオドを打ったが、3者の強固なパートナーシップと確固たるビジョンに導かれたプロジェクトとして、さらなる発展を目指している。







