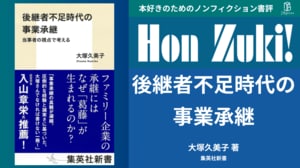中国・北京で、民主化運動が軍によって武力弾圧された「天安門事件」の際に群衆に燃やされた約20台の装甲車(1989年6月4日撮影)。(c)AFP PHOTO / Manny CENETA〔AFPBB News〕
日本列島がバブル景気に沸いていた1989年4月。中華人民共和国では学生たちが「変革の夢」を胸に、天安門広場へと集まっていた。およそ1カ月半後、世界を震撼させる大弾圧の舞台になるとも知らずに――。事件から30年目の今年(2019年)、天安門事件に関わった60人以上を取材した大型ルポルタージュが話題を呼んでいる。この度、大宅壮一賞を受賞したノンフィクションライターの安田峰俊氏が、2011年より足かけ8年を費やし完成させた『八九六四』。同書から、事件の当事者の生々しい証言を2回にわたってお届けする。(JBpress)
(※)本稿は『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』(安田峰俊著、角川書店)の一部を抜粋・再編集したものです。
双方を理解できる稀有な存在
魏陽樹(仮名) 事件当時19歳、某警察系大学学生、取材当時44歳、投資会社幹部
「八九六四」当時の所在地:中華人民共和国北京市郊外
取材地:中華人民共和国 北京市 亮馬橋付近のレストラン
取材日:2015年4月
「あの春の天安門広場はお祭りだったなあ。大学の授業は休みばかり。友達みんなと、太陽の下でご飯を食べてタバコを吸っておしゃべりをして、テントやバスのなかで寝る。今と比べて娯楽が少ない時代に、考えられないほど刺激的だった。とくに18歳や19歳の学生だとね、とにかくそのことが面白くて来ていた連中が全体の5割・・・。いや、8割だったかもしれない。僕自身もそうだったんだ」
遠い目をして当時の広場内部の状況を語るのは、私が北京滞在中に会った魏陽樹(ウェイヤンシュー)である。
彼は陝西(せんせい)省出身で、北京市内の大学に進学。1年生の19歳で「八九六四」を迎えた。事件後の1990年、大学を中退して日本に留学した後、財閥系の大手商社に就職。日本での生活は20年以上に及び、やがて友人数人と投資会社を立ち上げた。取材時点から1年ほど前に北京へ居を移した。奥さんは年下の日本人女性で、魏本人も非常に流暢な日本語を話す。
私との待ち合わせ場所も、市内東北部の日本人街・亮馬橋(リヤンマアチャオ)のレストランだった。魏陽樹とは数年前に、日本での友人との飲み会の席で1度挨拶を交わしたことがあったが、いざ連絡を取ってみると先方はこちらの記憶がなかった。むしろ私が魏を覚えていたのは、あのときに酔っ払った彼が、若き日に見た広場の様子をちらりと口にしていたからである。
「デモ隊の主張への共感は・・・。当時はそりゃあ、明らかにあったね。党幹部の息子みたいな特権階級じゃなくても、公平なチャンスがもらえる社会が来たらいいよなあと思っていた。広場で熱く語る別の大学の先輩や友達がすごくカッコよく見えて、演説に『なるほど』って頷いていた。リーダーの柴玲(ツアイリン)の演説も自分の耳で聞いた。本当に感動したこともあったんだ」
とはいえ、魏の立場はちょっと複雑でもあった。
「天安門は、1人の大学生としては広場に遊びに行く立場だったんだけど、当時の自分の学校の性質上、デモ隊を抑える側でもあってさ――」
彼の母校は、天安門広場から約20キロほど郊外にあった。警察官僚を養成する大学のひとつだったのである。もとは一般の大学が1980年代前半に警官養成用の大学に変えられた経緯を持ち、校風は「お上」の教育施設としてはかなり自由だった。だが、一応は公安部の下部機関であった。