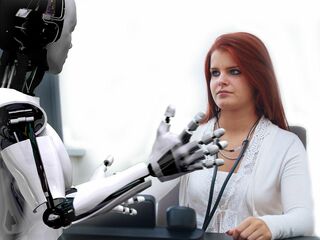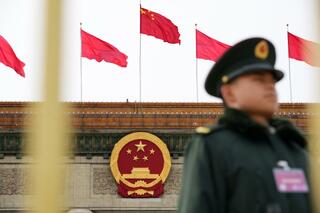村木厚子・元厚生労働省局長事件が冤罪という最悪の結末を迎え、証拠偽造までが明らかになった今、日本の報道が21年間依存してきた「報道と検察の共存共栄モデル」も終わってしまった。
前回は、報道と検察が取材情報や捜査情報を分かち合うことで、お互いの目的を達するという共存共栄の構図を説明した。
今回は「報道と検察の共存共栄モデル」で、検察と報道が共有しているもう1つの利益について書こうと思う。
記者の立場から言えば、検察ほど心強い「権威付け機関」はない。なにしろ、人を逮捕して閉じ込め、犯罪者として刑務所に入れてしまうだけの強制力を持った「最強の国家権力執行者」なのである。
権力が強大であるがゆえに、その執行は「慎重なうえにも慎重である」建前になっている。その捜査機関が報道を追認した=「報道内容は限りなく真実に近い」という「日本最強の裏付け」なのだ。
また「報道が検察の捜査を動かした」という事実そのものが、報道にとっては最高の勲章でもある(しかも地方公務員の警察官とちがって、検察官は国家公務員であり司法試験に合格した法曹職だ)。
1つ注意してほしい。こうした「官の権威依存型調査報道」は「ワシントンポスト」紙によるウオーターゲート事件報道のような、「報道した内容には報道機関が自分で責任を取る」(=捜査機関など他者の追認がなくても、自分たちの調査だけで真実性を保証する)という内容ではない。アメリカ型調査報道とは異なり、他者の追認によって(=特に公的機関の「権威の保障」をもらうことで)真実性を担保するという発想である。
意識的なのか無意識的なのかは分からないが、日本報道各社はこうした「報道するという行為そのもの」にも「官庁依存」の傾向が見える。
検察官に「当てて」さえいれば「書き捨て御免」
検察という「調査専門組織」が高い確度で「事実だ」と推定していることは、確かに他にはない重みがある。しかし、この「真実性の担保を検察に委ねる手法」は、リクルート事件以降、次第に少しずつ逸脱した形跡がある。
記者は、「裏付けを取る」ために、どんな情報も報道前に検察官に「当てて」みる。自宅でも通勤電車での飲み屋でもいいからネタを話してみて、相手の反応を見る、という作業である。
その反応によって「記事にしても大丈夫だ」と感触を得れば「Xも把握している」「Xも関心を持って推移を見守っている」「Xも立件を視野に情報を収集している」と、主語Xを「特捜部」「検察当局」「検察関係者」(地検以上の高検や元検事のOBに当てることもある)などと描写し、述語を変えていくのだ。この辺の「厳密さ」「いい加減さ」は記者、新聞社によって差がある。
検察官に当ててさえいれば、立件されそうにない情報でも、「検察が『把握』していることは間違いないから、そう書いておけば間違いではない」と、だんだん横着になっていく。