すでに転居は4回、けれども南相馬には戻れない
3年目の原発難民(その3)
2014.4.17(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
本日の新着

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に
広尾 晃

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖
「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費
森田 聡子

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】
若月 澪子
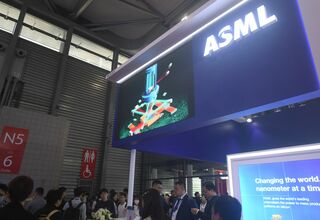
「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?
莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方
湯之上 隆
ウオッチング・メディア バックナンバー

「エモグラム」記事盗用問題、1年前の毎日新聞に学べなかった産経新聞、経営難の2社で続いた不祥事は偶然ではない
西田 亮介

自民・維新連携を「連立政権」と無批判に報じたオールドメディアの失墜、政治家の思惑通りなら信頼回復は遠い
西田 亮介

「支持率下げてやる」で大炎上、通信社カメラマンの“職場の愚痴”より深刻な、大手メディアの時代錯誤と特権意識
西田 亮介

多くの冤罪を生んだ「揺さぶられっ子症候群」、正義を掲げる検察やメディアに欠けている「人は間違える」という前提
砂田 明子

「テレビ離れ」が間違いなく加速度的に進むと言えるワケ…「新聞離れ」に負けず劣らず、TVer・ABEMA伸長の意味
西田 亮介

虐待か冤罪か─異色の「弁護士記者」が追及し続けた刑事司法と事件報道の罪
西岡 研介



