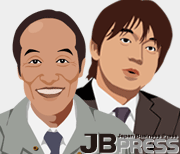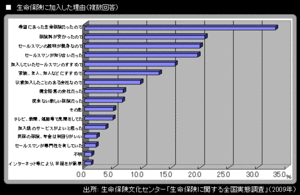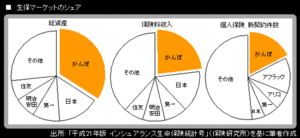サウジアラビアなどの陸上油田や大陸棚にある比較的水深の浅い油田は、下半分のリンゴである。もはやそれを採り尽くしつつあり、現在では深海や極地など採掘のより困難な油田を必死に開発している。今回事故を起こした油田は、メキシコ湾の深海約1500メートルにある。上半分のリンゴを採ろうとして木から落ちてしまい、重傷を負ったのが今回の事故なのだ。
過去、人類は採掘しやすい石油から採掘してきた。後に残るものほどそれが難しくなり、EPRの値も低くなる。米国の経験によると、1930年代の油田は穴を掘るだけで勢いよく原油が噴き出したため、EPRは100以上を示した。ところが70年代には30程度、現在では11~18程度まで低下していると推計される。
ニューヨーク州立大学のホール教授(Charles A. S. Hall)らの試算によると、全世界規模でのEPRの概算は1992年で26だったが、99年には35まで上昇した。しかしその後は減少に転じ、2005年時点では19にまで低下しているという。今後さらに「上半分のリンゴ」に頼らざるを得なくなれば、EPRは一段と低下することになる。
ホール教授らは2008年の論文でEPRの視点から経済モデルを作成し、コンピューターを使ってシミュレーションを発表。その際、EPRが2030年に10、2050年では5程度にまで低下すると仮定している。そして、コンピューターは次のような近未来図を描き出した。
これからはエネルギー取得のための投資が増大し、社会が「自由裁量」で使える消費が極端に少なくなっていく――。つまり、対策を先延ばしにすればするほど裁量の余地は狭まり、その段階で「石油後」の世界を構想しようにも身動きが取れなくなるのだ。
このシミュレーションの結果は、石油をベースとして築き上げてきた現代の社会システムの崩壊を予兆しているのではないか。
ハーバード大学のファーガソン教授(Niall Ferguson)は歴史学者としての視点から、過去の帝国主義や現在のグローバル経済のような「複雑系」社会に内在するリスクを分析している。
1粒の砂が砂山全体を崩すことがあるように、ほんの些細な歯車の軋みがきっかけとなり、一気に崩壊へと向かう恐れがあるという。世界的なEPRの低下が、ある時点で特定の社会の崩壊を引き起こすほどの決定的な影響を与える可能性は十分に考えられる。
また、ユタ州立大学の考古学者であるテインター教授(Joseph A. Tainter)は、ローマ帝国を含む過去に崩壊した24の社会を分析した上で、たいへん興味深い考察を示している。教授によると、「文化的複雑性の歴史は、人類の問題解決の歴史」であり、「歴史を通して、人類が直面したストレスと挑戦は往々にしてより複雑になる戦略によって解決されてきた」(下線筆者)
そして、「社会という問題解決のためのシステムは、長期間、複雑性とコストを増しながら発展し、やがてシステムは補助的なエネルギーの増加を必要とするようになるか、あるいは崩壊する」という。