 JHVEPhoto/Shutterstock.com
JHVEPhoto/Shutterstock.com
面接で良い人材に出会えない、欲しいターゲットから応募が来ない――採用に関する悩みが、日本企業の競争力をじわじわと削っている。一方で、欧米の企業では2000年代から“採用そのものを戦略と捉える”発想が主流となり、「TA(タレントアクイジション)システム」と呼ばれる新たな人材獲得手法が広がっている。本稿では、『世界標準の採用』(小野壮彦著/日経BP)から内容を一部抜粋・再編集。採用を「人事の一機能」ではなく「経営の意思決定」と捉えるTAの発想と、その実践方法を読み解く。
企業が新たにTA業務部門を立ち上げる際、どのような人材で構成するのが効果的だろうか。グーグルのアプローチを例に紹介する。
TA人材は、どこにいる?
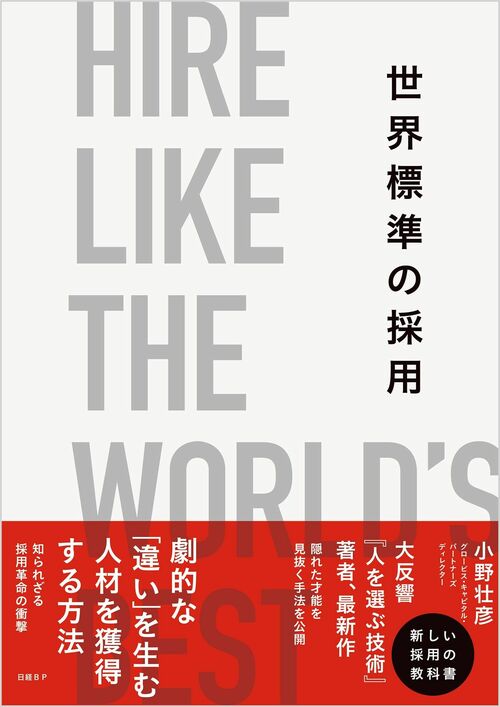 『世界標準の採用』(日経BP)
『世界標準の採用』(日経BP)
「採用のプロを採用する」――これは採用の変革を目指すとき、多くの企業が直面する新たなチャレンジです。
優秀な人材(タレント)を自社の力で探し出し、魅了し、獲得(アクイジション)するTAシステム。その戦略的価値と効果については、すでにご理解いただけたことと思います。
しかし、この新しい採用システムを実装するには、重要な前提があります。それは、TA業務を専門とする社内人材の存在です。外部の採用エージェンシーに依存していた採用活動を、自社の強みとして内製化するには、その担い手となるプロフェッショナルの獲得が不可欠です*1。
ここで企業は、冒頭に掲げた皮肉な課題に直面します。「採用のプロフェッショナルを、どのように採用するのか?」。日本ではTAの歴史がまだ浅く、専門性を持つ人材の層は決して厚くありません。多くの企業が、この人材獲得の課題に明確な解を見出せていないのが現状です。
もちろん、TA業務の経験者を外部から採用するという選択肢はあります。前述のように、グーグルやアマゾンの日本法人から、日本企業に移籍したTA人材は実際に存在します。また、楽天やメルカリのように、国内企業で先行してTAシステムを実装した企業からの経験者採用ができるならば理想的かもしれません。しかし、そのような人材は数に限りがあります。
*1. とはいえ、インハウス化によって、外部の採用エージェンシーが不要になるわけではなく、むしろ効果的な活用が求められる。また、RPO(リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)という、TA業務をアウトソースするサービスの利用も広がっており、これらについては後述する。








