 写真提供:Guerin Charles/ABACA/STR/NurPhoto/ロイター/共同通信イメージズ
写真提供:Guerin Charles/ABACA/STR/NurPhoto/ロイター/共同通信イメージズ
面接で良い人材に出会えない、欲しいターゲットから応募が来ない──採用に関する悩みが、日本企業の競争力をじわじわと削っている。一方で、欧米の企業では2000年代から“採用そのものを戦略と捉える”発想が主流となり、「TA(タレントアクイジション)システム」と呼ばれる新たな人材獲得手法が広がっている。本稿では、『世界標準の採用』(小野壮彦著/日経BP)から内容を一部抜粋・再編集。採用を「人事の一機能」ではなく「経営の意思決定」と捉えるTAの発想と、その実践方法を読み解く。
マッキンゼー・アンド・カンパニーが打ち出した「ウォー・フォー・タレント(War for Talent)」を源流とする「TA」。その概念が人材獲得競争にもたらした劇的な変化とは?
才能を獲得せよ——TAシステムの源流
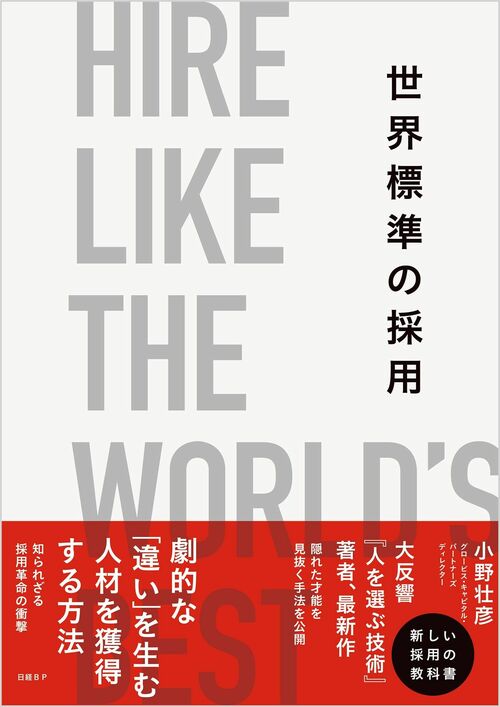 『世界標準の採用』(日経BP)
『世界標準の採用』(日経BP)
米国において、いわゆる新卒ではない「経験者採用」が活発化したのは、1980年代の不況で人員整理がなされ、終身雇用が終わりを告げた後でした。景気が回復するにつれて、欠員を補充するための経験者採用の重要性が高まり、そのオペレーションも進化していきます。この傾向は、東西冷戦終結後の経済のグローバル化を受けて加速し、1993年のワールドワイドウェブ(WWW)の開放によるインターネット時代の始まりへと続いていきます。
TAの概念が世界に登場したのは、その少し後、1990年代後半のことでした。一つのきっかけとなったのは、マッキンゼー・アンド・カンパニーが1997年に打ち出した「ウォー・フォー・タレント(War for Talent)」という概念です。日本語にするなら「タレント獲得戦争」とでも呼ぶべきでしょうか。その後2001年に刊行された同名の『ウォー・フォー・タレント*1』は、ベストセラーとなりました(日本では2002年に刊行)。
マッキンゼーがここで企業に説いたのは「才能ある人材=タレント」を集めることの重要性ばかりではありませんでした。そのために、「常に優秀な人材を追跡」し、「求職中でない人にもアプローチ」をかけなくてはいけない、と呼びかけ、「継続的に人を雇う体制」をつくろうと提案したのです。
これは、まさに「タレント」の「獲得=アクイジション」に特化したチームを正式に組織化せよ、というメッセージにほかなりません。こうして「ウォー・フォー・タレント」は、TAシステムの確立に至る、一つの明快な流れを生み出したといえます。
*1. エド・マイケルズ、ヘレン・ハンドフィールド・ジョーンズ、ベス・アクセルロッド、渡会圭子(訳)(2002)『ウォー・フォー・タレント』翔泳社








