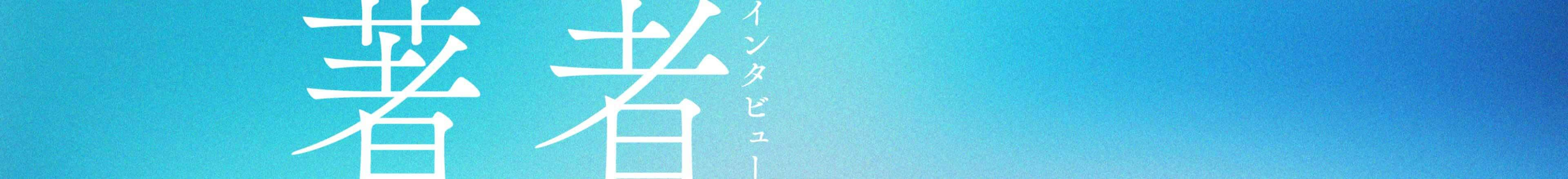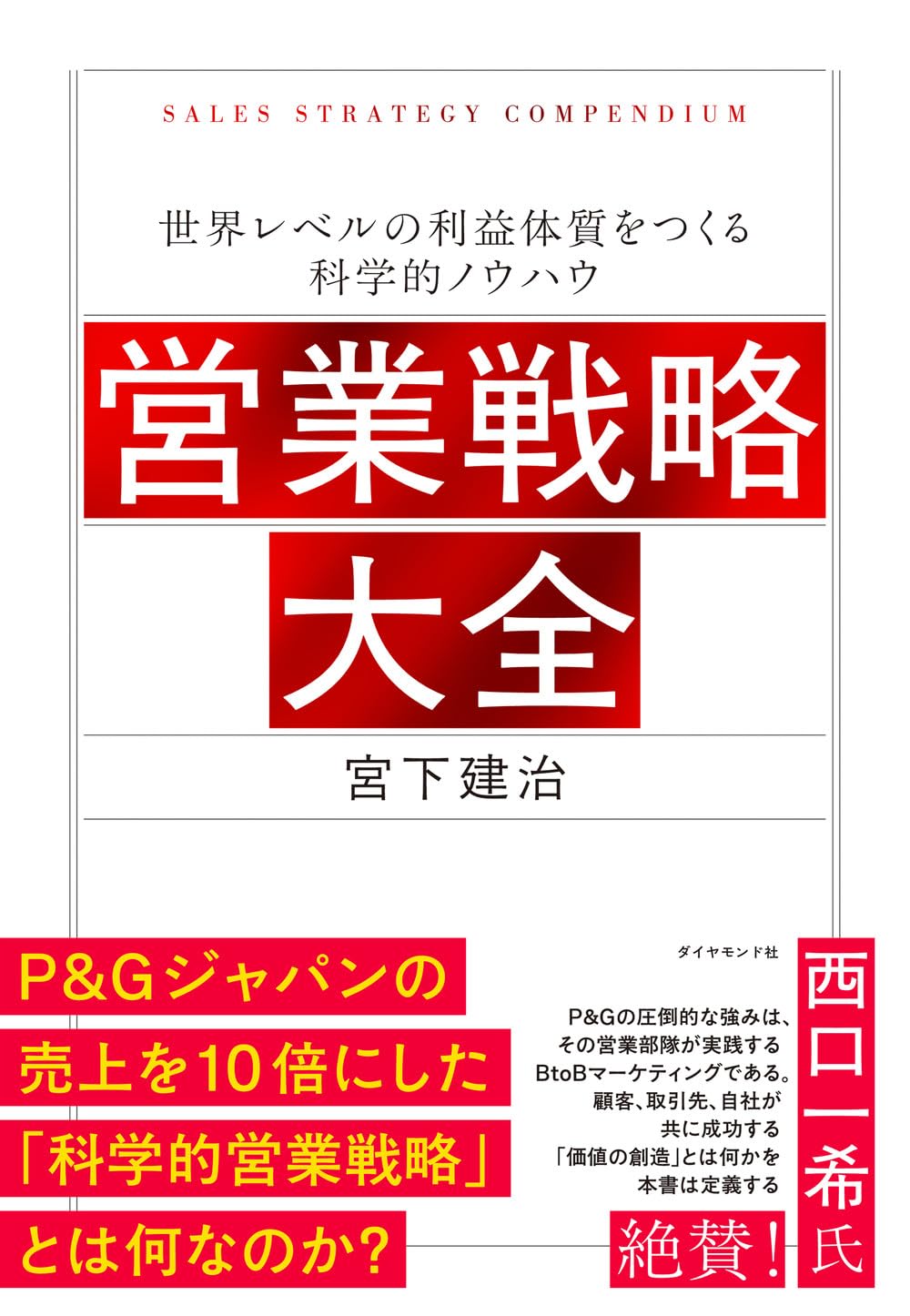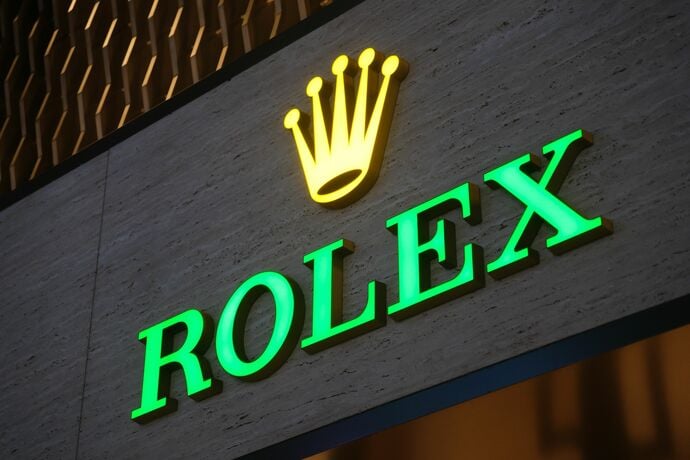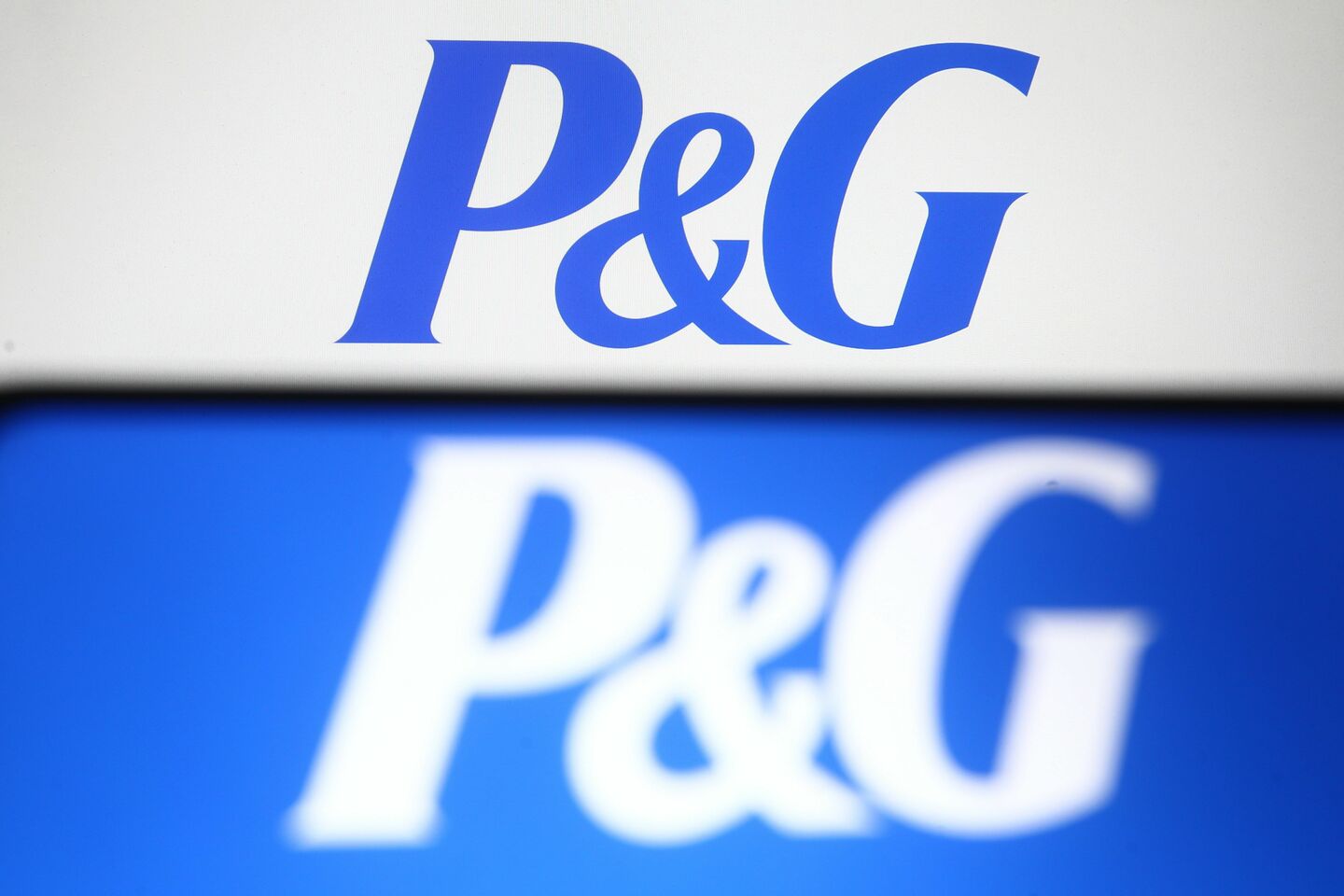 出所:©Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/共同通信イメージズ
出所:©Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/共同通信イメージズ
「失われた30年」と呼ばれる日本経済の低迷期に売上規模を10倍以上に伸ばした数少ない企業の一つ、P&Gジャパン。その成功の秘訣(ひけつ)として同社の営業改革を挙げるのは、元P&Gジャパン取締役営業本部長の宮下建治氏だ。宮下氏は、2025年2月出版の著書『営業戦略大全 世界レベルの利益体質をつくる科学的ノウハウ』(ダイヤモンド社)で、P&Gジャパンと日本マクドナルドでの実体験をもとに、科学的な営業改革の手法を解説している。P&Gジャパンにおける営業改革の舞台裏と、同社が採り入れた営業手法について同氏に話を聞いた。
消費財業界に残っていた「前近代的な営業」の中身
――著書『営業戦略大全 世界レベルの利益体質をつくる科学的ノウハウ』では、P&Gジャパンで行われた営業改革について解説しています。同社ではかつて「前近代的な営業」が行われていたとのことですが、どのような商慣習が残されていたのでしょうか。
宮下建治氏(以下敬称略) 私がP&Gジャパンに入社した1980年代、メーカーと小売企業との間に位置する卸店(卸売会社)が商流の中で大きな影響力を持っていました。そのため、P&Gに限らず多くの消費者メーカーの営業担当者は「卸店の仕入れ担当者」との関係づくりが重要なミッションになっており、営業の評価指標も「卸店への納品売上(納品した売上金額)」がベースとなっていました。
月末が近づくと、営業担当者の卸店への訪問頻度が増加し、「できるだけ多くの商品を仕入れてもらう」ということに注力していました。しかし、小売店で消費者に商品が購入されなければ、卸店で商品の在庫が滞留することになります。それでも卸店に商品を購入してもらうために「P&Gが近隣の営業倉庫を借り、そこに商品を一時的に保管する」といった手法を採ることもありました。
この頃、P&Gの売上規模は大手競合他社の10分の1程度に過ぎませんでした。強力な自社ブランドを多数抱えているわけでもなかったため、小売企業との交渉は価格訴求が主体になってしまいます。その結果、特売条件が整った時だけ商品が売れて、平常時には売れない、という状況が繰り返され、ひたすら商品を押し込む営業スタイルが常態化していました。
押し込み販売には、特別な条件提示や支払期限の延長などが伴います。結果として、メーカー側のキャッシュフローや利益も圧迫されます。また、月末に売り上げを押し上げた営業担当者は評価されるものの、翌月の初旬には売り上げが伸びづらくなるため、また月末に押し込み販売をかける、という悪循環が常態化していたのです。