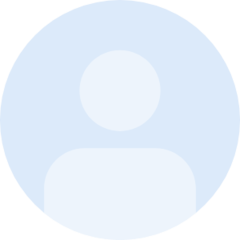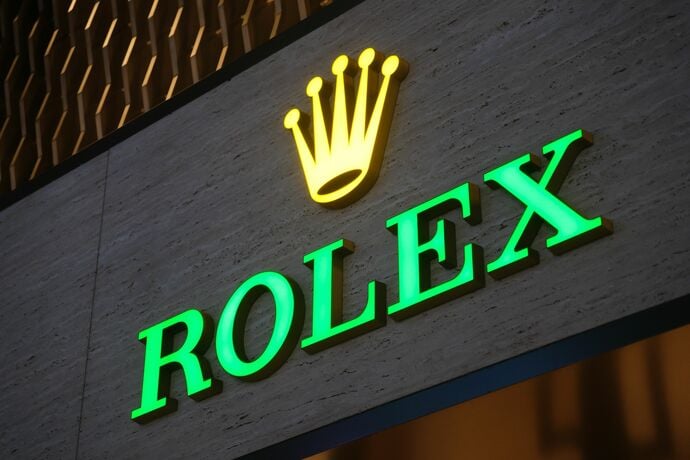トヨタ自動車の生産ライン
トヨタ自動車の生産ライン写真提供:共同通信社
「失敗は成功の母」とは言われるものの、実際には、失敗の危険性の高いことに挑むのは勇気がいる。特に減点主義が蔓延している日本企業では、あえてリスクを冒さない“無難”志向が強く、それがイノベーションを阻害する要因とも指摘される。そうした中、グローバルで成功している優良企業の事例を交えながら、失敗を類型化し、失敗を通じて生産性を向上させるためのフレームワークを提供しているのが、『失敗できる組織』(エイミー・C・エドモンドソン著、土方奈美訳/早川書房)だ。同書の内容の一部を抜粋・再編集し、そのポイントを紹介する。
世界の自動車産業をリードするトヨタグループの源流となった豊田自動織機で行われていた「アンドン・システム」は、ミスを早期に発見する品質管理手法としてだけでなく、経営手法としても注目に値する。
ミスに気づく
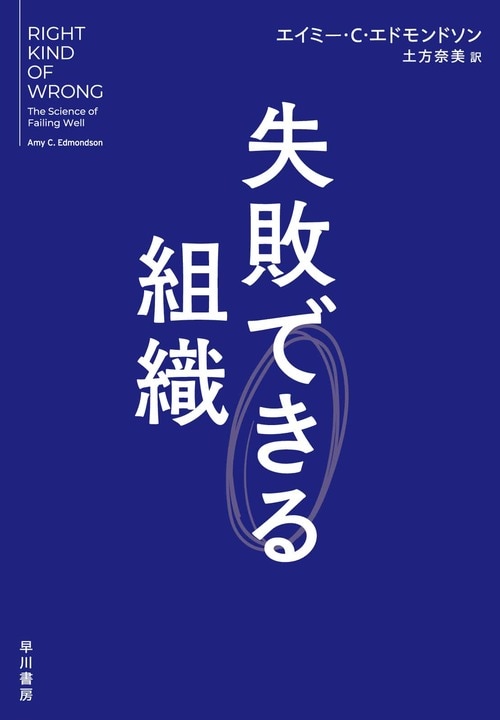 『失敗できる組織』(早川書房)
『失敗できる組織』(早川書房)
佐吉少年は1867年に日本の農村で生まれた。母は地域で栽培された綿花ではた織りをしていた。佐吉は父親から大工の技を学んだが、発明家らしい探求心や好奇心があり、賢い失敗の大切さもわかっていた。
古い納屋で木材を加工するのが好きで、初めてはた織機の改良版を作ろうとして失敗したときには躊躇(ちゅうちょ)せずに壊した。
24歳のときに木製織機で初めての特許を取得すると、すぐに織機製造の会社を設立した。1年後、工場は倒産した。だが佐吉はくじけずに織機の発明、革新、改良を続けた。30歳までには日本初の蒸気を動力とする織機を発明した。このとき興した会社は成功した。
1920年代には、豊田自動織機は日本の織機の90%を製造し、1929年にはイギリスの大手紡織機械メーカー、プラット・ブラザーズに特許権を売却した58。佐吉は息子の喜一郎に、会社の未来は自動車製造にあると言い続けた59。喜一郎は特許の売却益を元手に、のちのトヨタ自動車を設立した。
ただ、豊田佐吉が残した最も重要なレガシー(遺産)は、織機のエラー管理技術だった。縦糸が切れるアクシデントが起きたら、機械が自動的に停止するようになっていた。貴重な材料をムダにしないように、誰かが糸の状態を整えるまで機械は稼働しない。
58. “The Story of Sakichi Toyoda,” Toyota Industries(2021年11月11日に閲覧), https://www.toyota-industries.com/company/history/toyoda_sakichi/. 以下も参照。Nigel Burton, Toyota MR2: The Complete Story (Ramsbury, Marlborough, UK: Crowood Press, 2015).
59. Satoshi Hino, Inside the Mind of Toyota: Management Principles for Enduring Growth (New York: Productivity Press, 2006), 2.