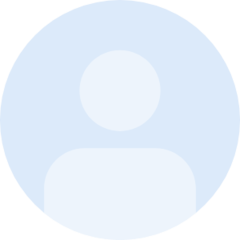写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
「失敗は成功の母」とは言われるものの、実際には、失敗の危険性の高いことに挑むのは勇気がいる。特に減点主義が蔓延している日本企業では、あえてリスクを冒さない“無難”志向が強く、それがイノベーションを阻害する要因とも指摘される。そうした中、グローバルで成功している優良企業の事例を交えながら、失敗を類型化し、失敗を通じて生産性を向上させるためのフレームワークを提供しているのが、『失敗できる組織』(エイミー・C・エドモンドソン著、土方奈美訳/早川書房)だ。同書の内容の一部を抜粋・再編集し、そのポイントを紹介する。
失敗は改善の機会なので「称えるべき」とよく言われるが、人間の心理としてはなかなか難しい。武田薬品工業で行われているのは、無理に称えるのではなく、「方向転換」するという方法だ。
方向転換を称(たた)える
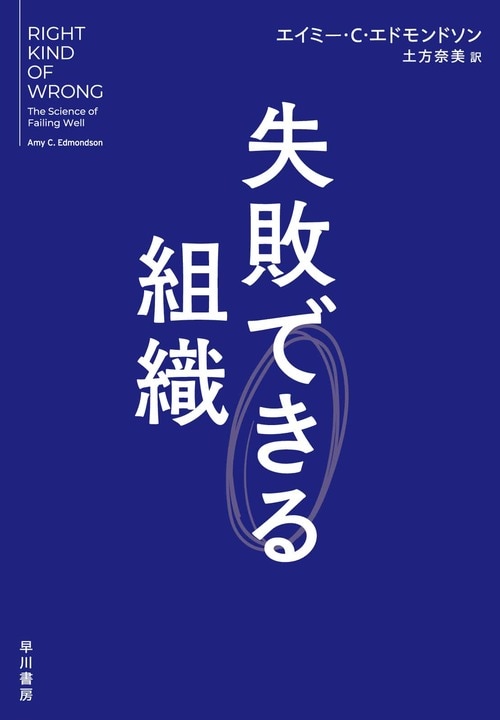 『失敗できる組織』(早川書房)
『失敗できる組織』(早川書房)
「失敗を称える」というスローガンはよく聞く。
だが大手製薬会社、武田薬品工業のバイスプレジデント兼グローバル・ラーニング・ソリューション責任者だったジェイク・ブリーデンと初めて会ったとき、ほとんどの企業では失敗を称えるのは依然として困難だという話になった。
「誰でも自分は成熟した人間だと思いたいが、何かを失敗と指摘されるとシャットダウンしてしまう傾向がある」とジェイクは語った。「失敗は終わりを意味する。それもバッドエンドだ」。だから失敗を称えるというのは心理的に非現実的な話だというのがジェイクの結論だった。
私がインタビューをした2021年12月、ジェイクは「実際に人は失敗をどのように経験するのか」という共感に基づく新たな対応法を見つけたと意気込んでいた。それまでジェイクが働いた企業では、ほとんどのプロジェクトがさらに多くのプロジェクトにつながっていた。
とりわけ失敗したプロジェクトはそうだった。「私たちは日常的に方向転換をしている」とジェイクは説明した。だから失敗を称えるより、方向転換を称えるほうが簡単だ。方向転換を称えるとは、要は次のステップに集中すること、目標に向かって前進する機会に目を向けることだ。後ろではなく前を向くことであり、そこに後悔が入り込む隙はなく、可能性しかない。