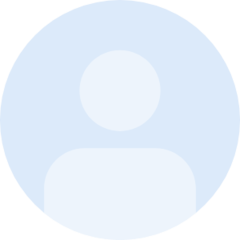NTTと中華電信、IOWNによる台湾ー日本間APN開通式
NTTと中華電信、IOWNによる台湾ー日本間APN開通式写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
今や半導体は経済安全保障の要であり、各国が自国での開発・製造に注力している。水平分業化された半導体産業において、足元ではファブレス(設計)の米エヌビディアとファウンドリー(製造)の台湾TSMCが大きくリードしているが、技術進化は早く、勢力図がいつ一変しても不思議はない。本稿では『日台の半導体産業と経済安全保障』(漆畑春彦著/展転社)から内容の一部を抜粋・再編集。世界の半導体産業と主要企業を概観するとともに、日本の半導体開発の最前線に迫る。
世界に遅れをとった日本の半導体製造は、果たして復活できるのか? その「切り札」とされる2つの先端技術を紹介する。
日本を「大逆転」に導く2大先端技術
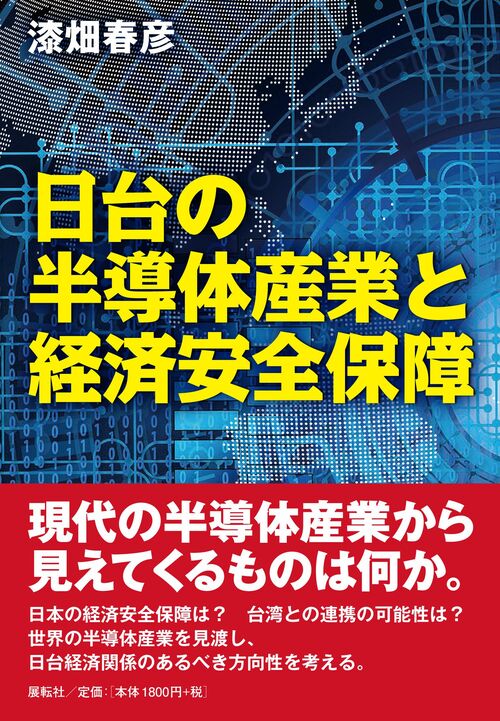 『日台の半導体産業と経済安全保障』(展転社)
『日台の半導体産業と経済安全保障』(展転社)
■ NTTの光半導体「IOWN」構想
日本の製造装置や材料がないと、TSMCやエヌビディアでさえ高い製品クォリティを維持するのは難しい。それほどまでに日本は世界の半導体産業を支えているのだが、半導体そのものを製造する技術は、台湾、韓国や米国に比べて遅れているのは否めない。
日本は1988年には半導体の世界シェア50.3%を誇っていたが、1991年のバブル経済崩壊以降、大手電機メーカーは多額の設備投資を必要とする半導体製造から相次ぎ撤退したことに伴い、そのシェアは徐々に低下した。2019年の日本のシェアは10%、現在のシェアは10%を大きく下回っている。
しかし、日本には現在のところ二つ、劣勢を挽回し大きく逆転する切り札を持っている。一つは「光半導体」である。これまでの半導体は「電気のON・OFF」を担っていた。電気より速いのが光であり、微細な回路に電気ではなく光を走らせる研究が日本で進んでいる。
これが実現すると、2030年には、現在の半導体の125倍もの性能(伝送容量)が実現するといわれている。電気と違い回路を走っても、光ならば熱を発しない。バッテリーがほとんど消耗しないので、光半導体を使ったスマートフォンは年に1回の充電で使用可能となる。離れた場所にアクセスしても、光で通信できれば遅延がほとんど起こらない。光を使えば、より精緻で正確な遠隔手術や自動運転が可能となる。