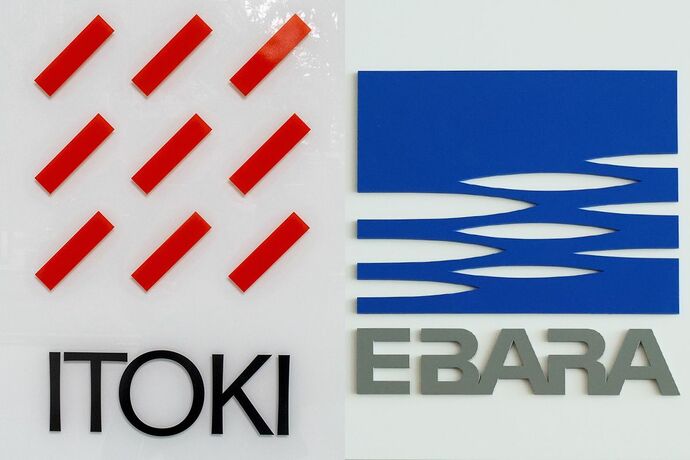写真提供: testing / Shutterstock.com
写真提供: testing / Shutterstock.com
環境負荷を低減した新製品やガラス試作品のスピード開発、年間11万時間の業務削減など、AGCがDXの成果を着実に積み重ねている。原動力となっているのが、同社のDX“人財”だ。その育成のポイントは、各実務を担当する社員がそのドメイン知識の習得に加えデジタルリテラシーを高める、「二刀流人財」という考え方にあるという。詳しい内容について、同社のDX推進を担うデジタル・イノベーション推進部 部長の太田宏志氏に聞いた。
RAG技術を活用し、生成AIで大幅な業務削減
――AGCは30を超える国・地域で事業を展開し、海外売上高比率と海外子会社従業員比率はともに約7割に達しています。グローバル一体で取り組むDXの現状をどう見ていますか。
太田宏志氏(以下敬称略) まだまだ課題はありつつも、少しずつ成果は出ていると感じます。その一例が、当社独自のマテリアルズ・インフォマティクス(MI)プラットフォームによる材料開発・組成開発です。
 AGC デジタル・イノベーション推進部 部長の太田宏志氏(撮影:榊水麗)
AGC デジタル・イノベーション推進部 部長の太田宏志氏(撮影:榊水麗)
ガラスなどの材料開発は、一般的に年単位の長い時間をかけて試行錯誤を繰り返します。当社は独自のMIプラットフォームを導入し、数万点に及ぶデータを活用して高品質な製品の早期提供を目指しています。実際に、MIを活用して当社が開発したフッ素系溶剤は、従来380ほどあった地球温暖化係数を1未満にまで下げることに成功しました。こうした製品を短期間で作っています。
また、新築ビルなどに使用するガラスの仕様を決める際にも、お客さまとの打ち合わせに用いたガラスのシミュレーションデータを生産設備に連動させ、1日で試作品を提供できるようになりました。ニューヨークのハドソンヤードの再開発プロジェクトの受注にもこの仕組みが奏功しました。
ガラス流通の改革も進めています。例えばビル棟を建てる際、使用する膨大な点数のガラスに対して、ゼネコン、工事店、卸売店、当社のようなメーカーがそれぞれ見積もりを作成し、関連会社とやりとりをしていきます。従前のアナログな工程が多分に残っており、ガラス業界を代表する企業としてこの領域を効率化できないかと考えました。そこで共通のプラットフォームを設け、サプライチェーン全体で見積もりデータの連携やそれに基づいた自動作成を可能にしたのです。