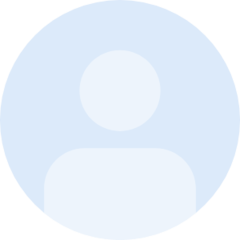写真提供:新華社/共同通信イメージズ
写真提供:新華社/共同通信イメージズ
『論語』に学ぶ日本の経営者は少なくない。一方、これまで欧米では儒教の価値観が時代遅れとされ、資本主義やグローバル化には合わないと考えられてきた。だが最近になって、その評価が変わりつつある。本連載では、米国人ジャーナリストが多角的に「孔子像」に迫る『孔子復活 東アジアの経済成長と儒教』(マイケル・シューマン著/漆嶋稔訳/日経BP)から、内容の一部を抜粋・再編集。ビジネスの観点から、東アジアの経済成長と儒教の関係をひもとく。
今回は、日本や「アジアの四小龍」と呼ばれた韓国、台湾、香港、シンガポールが、1950年代以降に成し遂げた目覚ましい経済成長において、儒教的価値観がどのように作用したかを分析する。
経済成長を支えた「ポスト儒教」
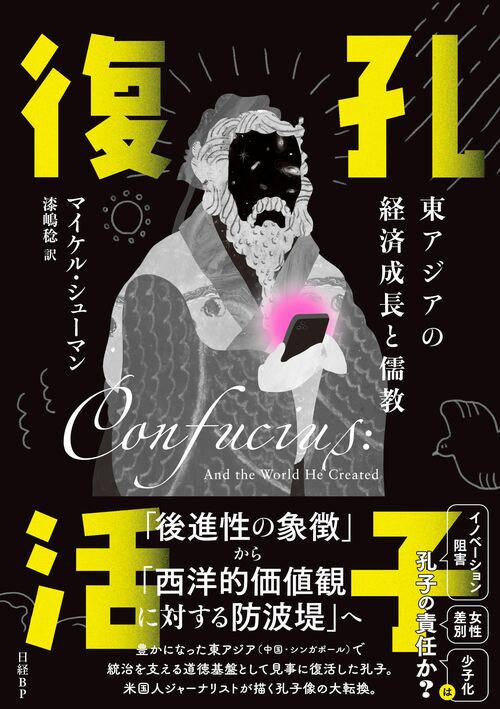 『孔子復活』(日経BP)
『孔子復活』(日経BP)
だが、第2次大戦後、戦災に遭った日本では孔子と資本主義の関係の再評価が契機となり、大きな変化が起きる。日本は産業や国富の再建に向けて、急速な経済発展をめざすことに乗り出し、世界中が啞然(あぜん)とするほどの驚異的な成功を果たす。日本経済は、1960年代に毎年平均10%以上という不可能と思われるほどの経済成長率を示し、1967年にはアメリカに次いで世界第2位の経済大国となる。
自動車、鉄鋼、テレビ、船舶、ファックス、半導体などの輸出を手掛けるようになった日本企業は、世界市場シェアの大半を占めるようになり、過去何世紀かで初めて欧米の優位に挑戦するようになる。「1970年代後半には日本が世界第1位の経済大国アメリカを凌駕(りょうが)するかもしれない」との予測が専門家から出ると、欧米は大いに狼狽(ろうばい)した。
ちなみに、急成長を遂げたのは日本だけではない。東アジア全体を通じ、極貧で戦禍に苦しんだ国々も豊かになっていく。「アジアの四小龍」と呼ばれた韓国、台湾、香港、シンガポールは、製造と輸出の拡大によって日本と似たような経済成長を経験した。これには、経済学者も困惑するばかりだった。