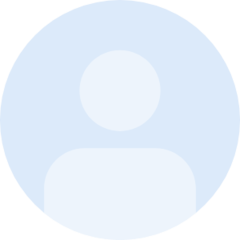写真提供:共同通信社、aphotostory/Shutterstock.com
写真提供:共同通信社、aphotostory/Shutterstock.com
『論語』に学ぶ日本の経営者は少なくない。一方、これまで欧米では儒教の価値観が時代遅れとされ、資本主義やグローバル化には合わないと考えられてきた。だが最近になって、その評価が変わりつつある。本連載では、米国人ジャーナリストが多角的に「孔子像」に迫る『孔子復活 東アジアの経済成長と儒教』(マイケル・シューマン著/漆嶋稔訳/日経BP)から、内容の一部を抜粋・再編集。ビジネスの観点から、東アジアの経済成長と儒教の関係をひもとく。
経営不振に陥った企業、ストライキが行われた企業を立て直した『論語』の力とは?
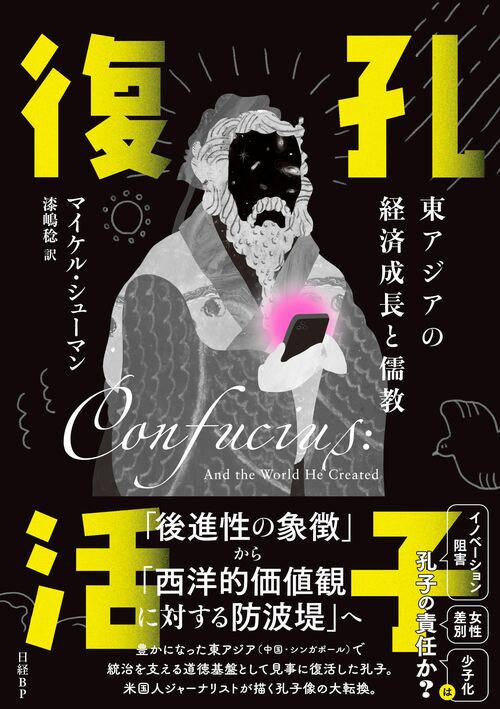 『孔子復活』(日経BP)
『孔子復活』(日経BP)
■ 新孔子と儒教資本主義
山西天下滙宝(かいほう)文化伝媒(でんばい)有限公司の創業者、靳戦勇(きんせんゆう)は疲れ果てていた。同社は山西省の省都太原(たいげん)市で展示やイベントの企画運営を業務とする小さな会社だ。
従業員が仕事を怠けたり、口論が頻発しても、靳は自社が傾いていく様子を絶望的な表情で眺めているしかなかった。
ついには殴り合いが始まるほど、社内の不和は激しさを増していった。このような大混乱のせいで売り上げが低迷し、経営に大きな打撃を与えた。だが、彼には手の施しようがなく、途方に暮れるばかりだった。
あれこれ考えた末、彼は「孔子」を人事コンサルタントとして採用する。
実は、これまで聖人孔子をほとんど知らずに過ごしてきたが、2011年に地元の実業家から儒教を紹介されて認識が変わる。紹介者も自社の経営を立て直すために孔子に頼っていた。