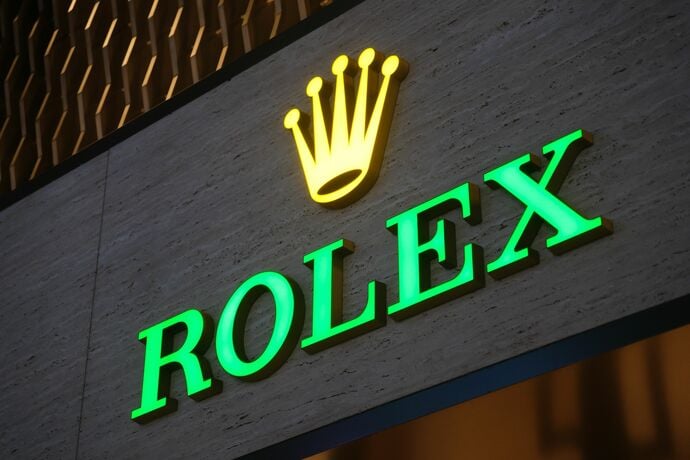日産最新のEV、アリアの前で_初代リーフを開発・市販化した、CVE(チーフビークルエンジニア)の門田英稔氏(撮影:川口紘)
日産最新のEV、アリアの前で_初代リーフを開発・市販化した、CVE(チーフビークルエンジニア)の門田英稔氏(撮影:川口紘)
電気自動車(EV)は内燃機関が電気モーターに置き換わっただけの自動車なのか──。数多くの新EVが発表され、その需要は一段落したとまで言われる今こそ、改めて問い直してみたい。そもそもEVとはどういう自動車だったのか? 世界初の量産型電気自動車「日産リーフ」(以下、リーフ)の開発責任者である門田英稔氏に話を聞いた。(第1回 / 全3回)
世界初の量産型電気自動車・リーフの誕生とその背景
2010年12月、日産は5人乗り普通乗用車として世界初の量産型電気自動車「リーフ」を発売した。24kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、満充電時の航続距離は200km。「走行中CO2排出量0」がうたい文句のこのクルマを購入した多くの人が、かつて経験したことのない自動車体験を味わった。評価は日本だけでなく、米国、欧州でも高かった。
 初代 日産リーフ
初代 日産リーフ
そもそも日産がEVの開発を決断した背景には、何があったのか。初代リーフの開発責任者としてCVE(チーフビークルエンジニア)を務めた門田 英稔氏は、当時の状況を振り返る。
「1990年代にアメリカで始まったZEV規制が、EV開発の大きなきっかけとなりました。この規制により、EVかFCV(燃料電池自動車)を開発せざるを得ない状況になり、各社一斉に電動車の開発を始めました」