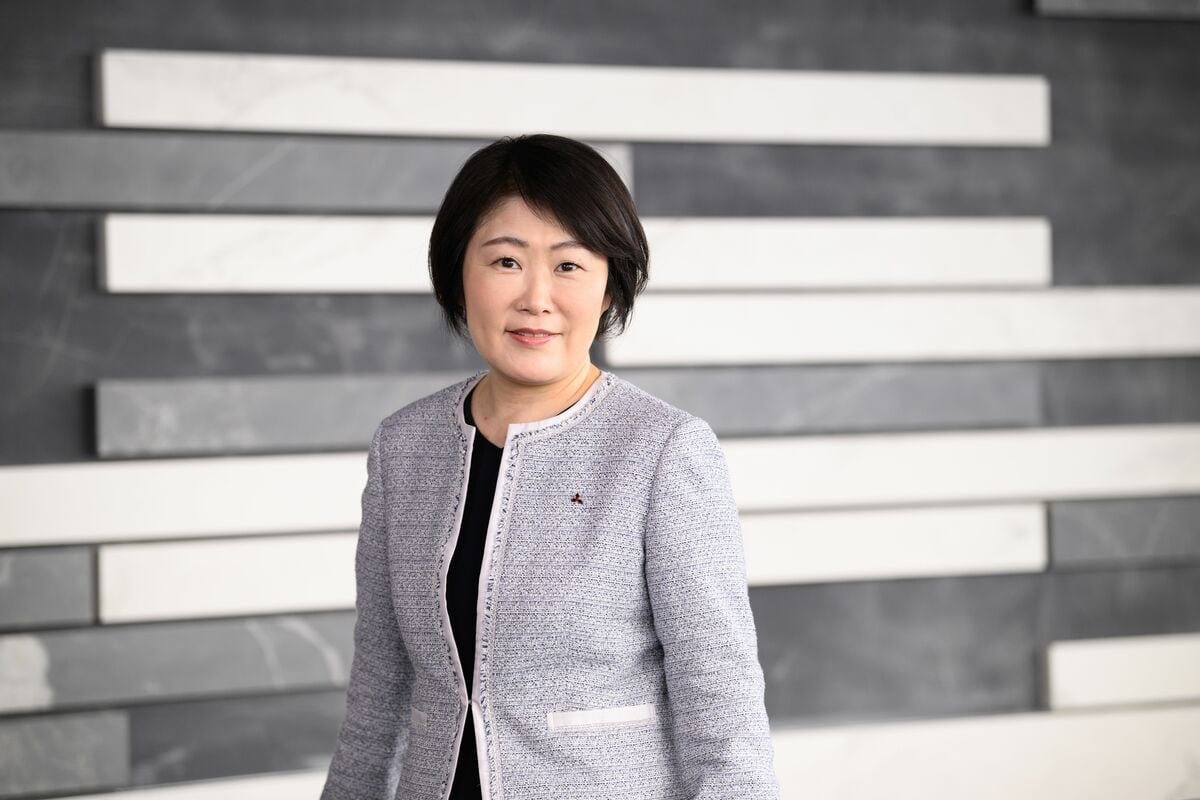 三菱マテリアル執行役常務CHROの野川真木子氏(撮影:今祥雄)
三菱マテリアル執行役常務CHROの野川真木子氏(撮影:今祥雄)
2017年に発覚した品質問題をきっかけに大規模な経営改革を実践している非鉄金属メーカーの三菱マテリアル。改革の中核に据えるのが、2020年以降進めてきている「4つの経営改革」だ。その中の1つ、HRX(Human Resource Transformation、人事変革)でどのような会社に生まれ変わろうとしているのか。旗振り役を務める同社執行役常務CHROの野川真木子氏に話を聞いた。
HRXの中身とは
──三菱マテリアルは2021年から人事変革であるHRXに取り組んでいます。同時に人事の専門家である野川さんを迎え入れ、以降様々な施策を打ち出しています。三菱マテリアルはなぜHRXが必要と判断したのでしょうか。
 野川 真木子/三菱マテリアル 執行役常務CHRO
野川 真木子/三菱マテリアル 執行役常務CHRO一橋大学社会学部卒業後、花王にて営業、人事を担当。2001年ゼネラル・エレクトリックに入社。日本、アジア・パシフィック、中欧・東欧地区において複数事業部門の人事を担当。2012年日本IBM入社。IBM米国本社出向、グローバル・ビジネス・サービス事業担当人事執行役員を経て、2016年3Mジャパン執行役員人事担当。2021年4月、三菱マテリアル 執行役員人事部長に就任、2022年4月より執行役常務人事戦略担当、2023年4月より現職。
野川真木子氏(以下敬称略) 自律的で、風通しの良い組織を作るためです。新卒一括採用、年次管理、ローテーションを基本とした人事制度を続けていては、組織が硬直化してしまうリスクが高まってしまいます。
2017年に発覚した品質問題を機に、社内のガバナンス体制を強化していく中で、「組織の中の風通しの良さ」「自律的な課題発見とその解決を考える力」に課題があることがわかりました。
どんな組織においても、競争力の源泉は「人」です。一人一人の従業員が持っている力を最大限発揮できる環境を整備していかなければ、企業価値の向上は実現できません。
その実現のためには、育成や評価の仕組みを進化させ、一人一人が自律的に自分のキャリア形成を考え、それを行動に移せる選択肢を提供する、そのために職場環境も進化させることが必要となり、人事の変革に着手しました。
──具体的にどのような施策を打っているのですか。
野川 「事業競争力の徹底追求と役割の明確化」と「自律的キャリア形成」の2つの領域を中心に施策を進めました。
前者については、2022年4月に管理職層に「職務型人事制度」を導入しました。従来は職能資格制度を長年運用してきましたが、職務型人事制度ではまず事業戦略の実行のために必要な組織を設計した上で設置されるポジション毎に担う役割と責任が定義されます。その役割と責任を期待されるレベルで果たしているかどうかを評価する仕組みへと変更をしました。つまり、入社年次や過去の評価などに関係なく、「今担っている役割でどのくらい成果を出しているか」が重視される制度になりました。
制度設計においては、それぞれのポジションが担う役割、責任の大きさを職務評価した上で職務グレードを設定し、行動基準も明確化しました。報酬も、外部市場の報酬情報も参考にしながら、個人の成果や会社業績を反映する処遇を目指しています。
職務型人事制度を導入した結果、従来にはなかった人材の登用や配置が可能になり、組織の活性化にもつながってきていると実感しています。
また、HRXの各種施策の進捗確認やその実効性を検証する機能として「人材委員会」も2022年より立ち上げました。この場では、定期的に全執行役と執行役を支援するHRビジネスパートナーが参加し、職務型人事制度の運用状況、次世代経営人材の選抜とその育成計画やエンゲージメントサーベイ結果の報告とアクションプランの共有、DE&Iの取り組みなど、活発な議論を行っています。HRXは全社を横断した取り組みであり、事業成長のためのものですので、その効果やさらなる改良には経営層の関与は必須と言えます。








