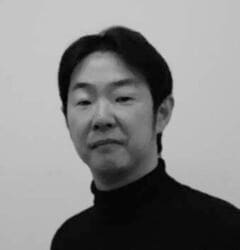化学業界を代表する企業の一つ、旭化成。マテリアル・住宅・ヘルスケア各事業のデジタル変革と、それらに共通する全社的デジタル基盤の強化を図るデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めている。経済産業省「DX銘柄」には2021年から3年連続で選定された。だが、「デジタル化は遅い」と評される日本の化学業界において、同社もその例外ではなかった。デジタル技術の導入から展開、さらに創造へと急速な歩みを遂げる裏には、「指揮者」の着任と様々な試行錯誤があった。
「日本は全然だめだ」遅々としていた化学業界のデジタル化
「デジタルを活用する組織風土が一気に事業活動に染み込み、血肉となっていると感じています。強化されたグループ共通のデジタル基盤をベースに、経営の高度化、そしてビジネス変革を進め、成果発現のフェーズへ進みます」
2023年4月11日。旭化成の2024年度までの中期経営計画の進捗状況説明会で、代表取締役社長の工藤幸四郎氏はこう述べた。同社は言わずと知れた大手総合化学メーカー。従業員は連結でグローバル4万8,897人(2023年3月時点) にのぼる。巨大メーカーがデジタル活用をいかに進めているかは、多くの人びとが注目するところだ。
化学分野のDXとして「マテリアルズ・インフォマティクス」(MI)を思い浮かべる人は多いだろう。人工知能技術を応用して、材料開発の効率を高める取り組みだ。実際、同社は2017年からMIを推進している(これについては次回の第2回で取り上げる)。
しかしながら、日本の化学企業は、専門家たちから「総じて欧米の先行企業よりデジタル化が遅い」と指摘されてきた。背景として、特化した隙間領域を強みとする企業が多く、投資が割に合わないといったことや、デジタル技術なしでも良質な材料・製品を生み出すことができ、デジタル化の必要性が高まらなかったことなどがいわれる。
2010年代後半、旭化成の社内にも、特に国内事業におけるデジタル技術導入の遅れに対する危惧はあったようだ。事業拡大のため米国企業を買収したところ、その企業の従業員たちのデジタルリテラシーの高さや、モノのインターネット(IoT)技術を駆使したビジネスの進み具合に、「日本は全然だめだ」と感じた人物もいた。
そうした中、同社DX推進の「指揮者」に就いた人物がいる。久世和資氏だ。