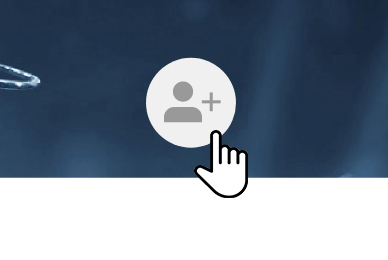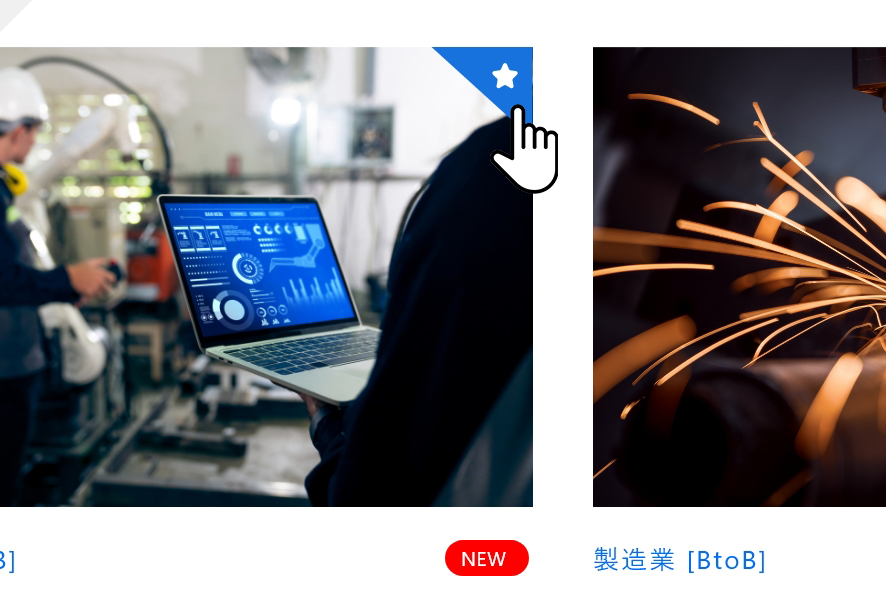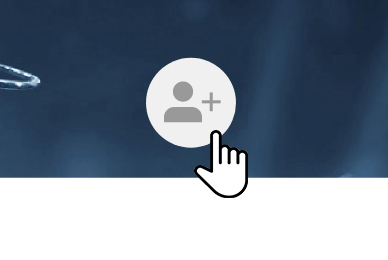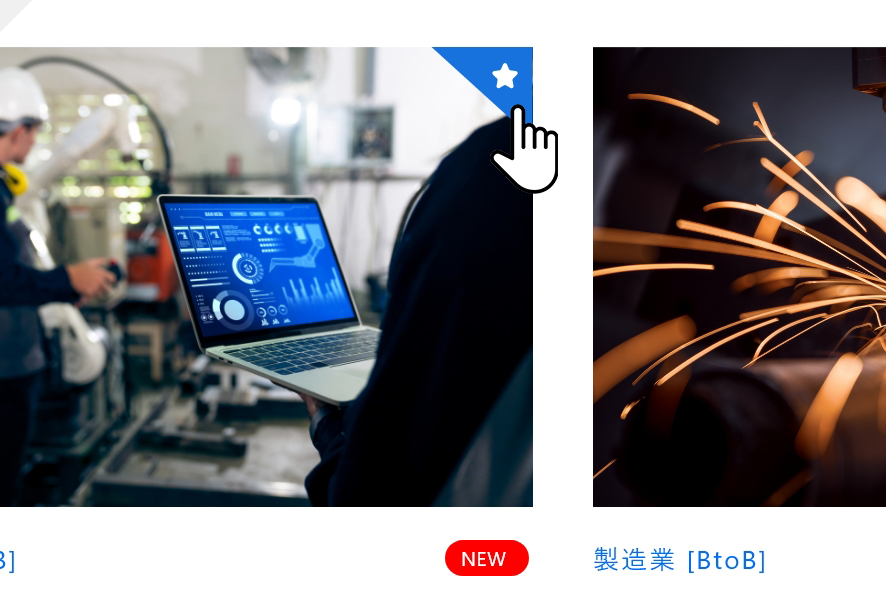京都先端科学大学 教授、一橋ビジネススクール 客員教授。
東京大学法学部、ハーバード・ビジネス・スクール卒業。三菱商事を経て、マッキンゼーで約20年間勤務。デンソー(~2018年)、ファーストリテイリング(~2022年)、味の素(~2023年)、SOMPOホールディングスなどの社外取締役、朝日新聞社の社外監査役を歴任(いずれも現在も)。消費者庁「消費者志向経営賞」座長。ボストン・コンサルティング・グループ(~2016年)、インタープランド、アクセンチュア(いずれも現在も)などのシニアアドバイザーを兼任。『パーパス経営』、『CSV経営戦略』、『企業変革の教科書』(いずれも東洋経済新報社)、『シュンペーター』、『稲盛と永守』、『経営変革大全』(いずれも日経BP)、『コンサルを超える問題解決と価値創造の全技法』、『成長企業の法則』(いずれもディスカヴァー・トゥエンティワン)など著書多数。