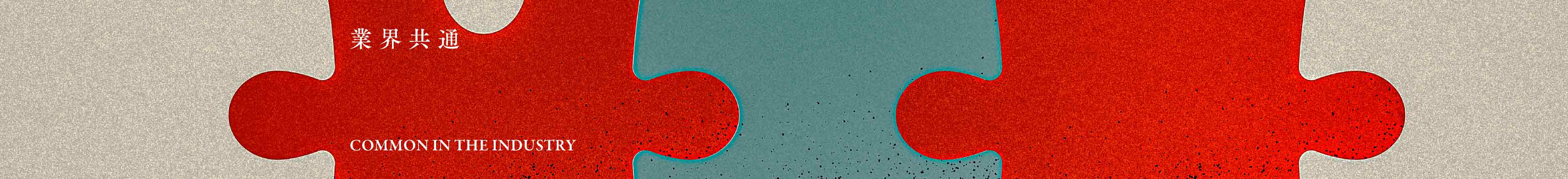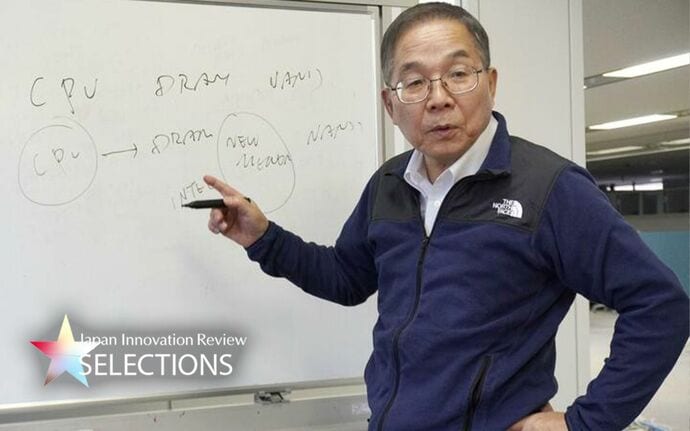JVCケンウッドのような事業領域であればブランドイメージとなるし、材料や部品といったレイヤーの企業であれば自社の「コアコンピタンス」「コア技術」がそれに該当するだろう。
例えば、富士フイルムは12のコア技術とそれがもたらす価値を定義し、外部発信している。この場合、コア技術は「精密塗布技術」のような粒度、提供価値は「光を制御する」という粒度の表現となっている。富士フイルムが持つ実際の要素技術はもう少し狭いものであるに違いないが、このように、根本にある自社の強みや価値観を、一段昇華した言葉で定義することで、現在の要素技術にとらわれない新しい技術や市場の呼び込みを可能としつつ、自社の戦略とのアラインメントも取りやすくなる。
特に、日系企業においては、種々の商業的慣習が足かせとなって、欧米企業のようなポートフォリオ組み換え型の経営アプローチを取りにくく、また、職人気質の国民性に鑑みても、コアコンピタンス経営の適合性が高い。コアコンピタンスを定義し、その中で新しい領域に挑戦するという考え方が重要だろう。
また、戦略的アラインメントに加えて、ある程度「モノ」になるまでのモメンタムの維持という観点で、顧客視点のような形で事業推進の「強制力」を持たせる工夫は有効であろう。
日本企業のパラダイム
このような一見場当たり的に見えるマネジメントは、日本企業には不向きと捉えられるかもしれないが、実は日本企業はこのアプローチの方が得意だ。
一番分かりやすいのは、何らかの買収案件が外部から持ち込まれ、相手先事業を自社の傘下に入れるような場合だ。持ち込まれるまでは、相手先事業とのシナジー等考えたことがなく、そのようなアイデアを発案しても社内的にまず受け入れられないという状況であったとしても、実際にグループ会社になると、途端に相手先の資産を活用することが“オーソライズ”される。また、社内においても、組織を超えた連携は非常に苦手だが、ひとたび組織再編があって2つの組織が統合されると、途端に連携のモメンタムが働く。
つまり、何もないところから事業を構想するよりも、何らかの形で“オーソライズされた”点を起点として線を描く方が得意なのだといえる。
これは、競争優位性の観点でも、有効性の高いアプローチだ。今ある事業を起点とした分かりやすいストーリーは、他社にとっても魅力的なので、多くの場合、競合他社と似たり寄ったりの戦略になってしまう。一方、既存事業と離れたところで生み出された偶発的な点と、既存事業を繋いで生み出されるストーリーは誰にも設計できない。