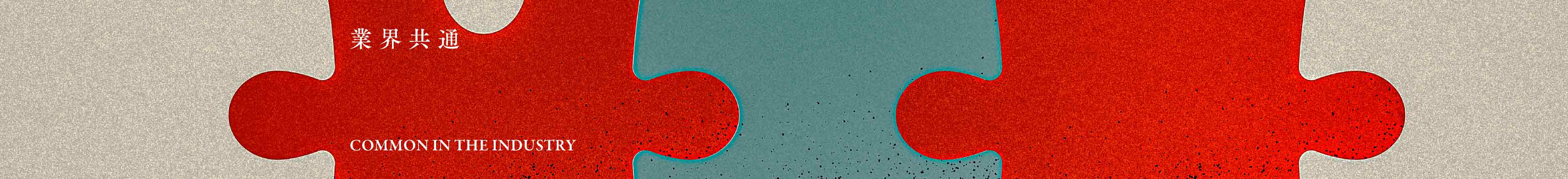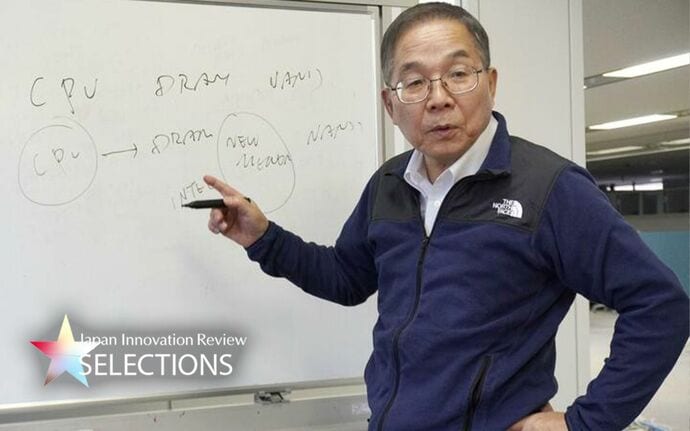前者は、主に社内の起業家候補へのスピンオフ投資機会を提供し、シード企業を次々と生み出すことを志向する。サイバーエージェントのCAJJなどが該当する。後者はレガシー企業に多く、同様にシード投資機会を提供するが、アセット活用やエコシステム構築といった文脈を志向する。KDDIの無限ラボやソニーのSSAPなどが該当する。後半ステージが投資対象になるが、広い意味ではソフトバンクのビジョンファンドも同類だろう。
なお、CVCは投資判断を円滑化する手段でしかないため、共創の組織能力を持たない企業のCVCが形骸化するのは当然だ。超売り手市場のスタートアップにとって、資金を出すだけの企業投資家の魅力は乏しい。
特に、共創を前提とした「戦略シナジー」を追求するアプローチにはさまざまな発展の余地がある。今や、ソニーのSSAPに京セラやライオンが相乗りする時代だ。そのほか、MaaSやXX-techの文脈で、企業を跨いだアライアンスやコンソーシアムの動きが急増している。持続性の課題が喫緊なものとなっている自治体主導の動きも非常に活発だ。
「ベンチャー投資同様、コンソーシアムも昔からあるブームでしかない」と見る向きもあるが、これを機会にぜひ異なる見方をして欲しい。
企業間をまたぐ共創が広がる背景
今般のコンソーシアム急増のトレンドの背景には、デジタル化に伴う業界や事業構造の変化がある。デジタル化の影響についてはさまざまな指摘があるが、その示唆するところは(1)価値提供の主軸が供給側からユーザー側の体験にパワーシフトし、(2)バリューチェーンからレイヤー構造へ移行して行く中で、(3)ネットワーク効果などの経済性が働くポジション獲得を目指すべし、といったところだろう。
本稿ではその各論に触れないが、背景を理解する上で指摘したいのはインパクトの視点である。企業戦略の文脈でオープンイノベーションを語る際、アクセラレータープログラムは成果の規模が小さいといった指摘があるがこれは誤解だ。プログラムが提供するのはスタートアップとの協業案の束であり、共創の組織能力構築の支援であり、あくまで大企業から見た新規事業創出の入り口でしかない。
協業案をより大きな成果に導くのはプログラム開催企業の仕事だが、上記のトレンドを踏まえると、一企業としての戦略シナジーの文脈だけではインパクトに限りがあることは自明である。インパクトを指向すれば企業を跨ぐアライアンスは必然であり、価値あるパートナーやメンバーになるためには共創の組織能力は不可欠だ。そこでは参加企業の規模が大きいか小さいかはあまり意味がなく、それぞれ異なるポジションの取り方がありうるだろう。
もう1つ指摘したいのは、強みは生かすだけでなく新たに作るべきとの視点である。前稿でイノベーションを定義する際に、敢えて「手段と目的の両方を含む」とし、また製造業に特有の強みに対するバイアスについて言及した。オープンイノベーションは手段であって、手段を目的化してはいけない、という指摘が聞こえてきそうだ。しかしながら、今や手段か目的かの議論にはあまり意味はない。