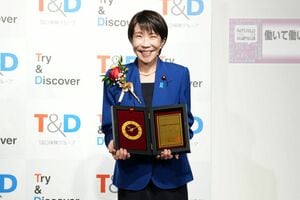日本の大学教育の行く末は。
日本の大学教育の行く末は。
前回までの記事では、各大学によって定められるディプロマ(学位授与)、カリキュラム(教育課程編成・実施)、アドミッション(入学者受入れ)の三つのポリシーが、近年では文部科学省が各大学に教育改革を迫るための格好の道具立てとなってきていることを指摘した。
今回は、そうした形で大学教育改革を迫ることの問題性がどこにあり、そのことが、日本の大学教育をどこに導くことになるのかを論じる。
論点は、本来多岐にわたるが、ここでは大括りに四点に絞ってみたい。
改革の方向性の“遠隔操作”
第一に、文科省による近年の高等教育政策は、形式的には確かに、大学の「自主性、自律性」を「尊重」(教育基本法第7条の2)しているように見えつつも、実質的には、各大学の教育改革が進むべき方向を巧みにコントロールしようとしているように見える。
もちろん、三つのポリシーは、あくまで個々の大学が、それぞれ自主的に定めるものである。そこに文科省が内容的な指示を与えたり、何らかの直接的な評価を下したりといったことは、本来許されない。事実、そこまでのことは、さすがになされてもいない。
しかし、他方で、各大学に対して、そもそも三つのポリシーの作成と公表を義務づけ、それらの一体的・整合的な運用を求めたのは、ほかでもない文科省である。そして、前々回の記事で触れた中教審の(三つのポリシーの)「策定及び運用に関するガイドライン」を通じて、三つのポリシーの書き方や内容項目、作成の際に踏まえるべき点について、こと細かに(実質的な)指示を与えたのも、文科省なのである。
確かに、「ガイドライン」には法的な拘束力があるわけではないが、それに従わないことが、競争的資金への応募や認証評価の際などにどれだけの不利益に帰結するかは、大学側は当然のこととしてわきまえている。さらに言えば、これも前回の記事で触れたが、各種の補助金(競争的資金)などを通じて、文科省が大学に何を求めており、何を実現させたいのかは、大学側にとっては、透明すぎるほどに明らかになっているのである。