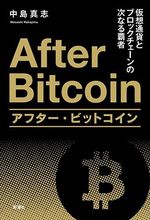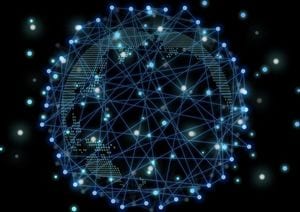スウェーデンは、キャッシュレスが進んでいる国です。日常の支払いは、市場での買い物に至るまで、すべてデビットカードかキャッシュカードで済ませるという社会になっており、人々は財布すら持っていません。実際、GDP(国内総生産)における現金の比率は、わずか1.5%。日本の約20%に比べると、いかに現金が出回っていないかがわかります。
こうなると、市中の銀行も現金を扱いません。銀行の支店に行ってみたところ、現金を扱うカウンターやテラー(窓口係)の姿はありません。あるのは住宅ローンや資産運用の相談を行うためのソファーや会議室だけで、支店そのものがサロンのようになっていました。
ここまでキャッシュレスが進むと、庶民も現金を使わないし、銀行も扱わない。中央銀行による法定通貨の発行が大幅に減少して、通貨の発行による利益(通貨発行益)も減る。スウェーデン中央銀行はそれを懸念して、「eクローナ」の発行を計画しているわけです。
「やるかやらないか」ではない
一方、日本ではどうか。実は1990年頃から、日銀内部で「電子現金プロジェクト」という基礎的な研究が行われたことがあり、私も研究員として加わっていました。中央銀行員のDNAの中には、「電子的な貨幣を発行したい」という願望が根強くあるのです。
歴史的にみると、通貨は、その時々の最新技術を使って発行されてきました。その意味では、ブロックチェーンという技術が出てきた中で、それを使って電子的な通貨を発行しようとするのは「歴史の必然」であるとも言えます。
その意味で、スウェーデン中央銀行の人が言った言葉が、今でも強く印象に残っています。
「デジタル通貨の発行は、やるかやらないかというwhether(どちらか)の問題ではなく、いつやるのかというwhen(時期)の問題なのだ」

中島真志
1958年生まれ。麗澤大学経済学部教授、経済学博士。一橋大学法学部を卒業後、日本銀行に入行。調査統計局、国際局、国際決済銀行(BIS)を経て日銀を退職。決済分野を代表する有識者として、金融庁や全銀ネットの審議会などにも数億参加している。単著に『入門 企業金融論』、『外為決済とCLS銀行』、『SWIFTのすべて』、共著に『決済システムのすべて』、『証券決済システムのすべて』、『金融読本』(いずれも東洋経済新報社)など。
◎新潮社フォーサイトの関連記事
・株式市場にも連鎖したビットコイン「バブル崩壊」の痙攣症状
・マネーはマジックか? 高度のテクニックか?
・バングラデシュから始める「未来の医療」