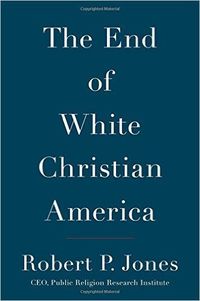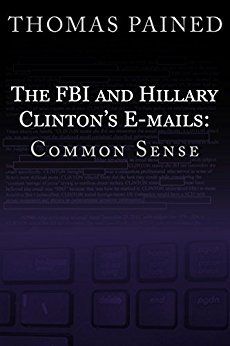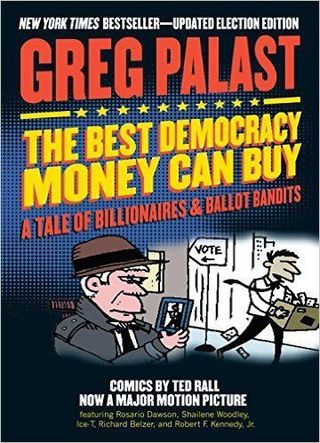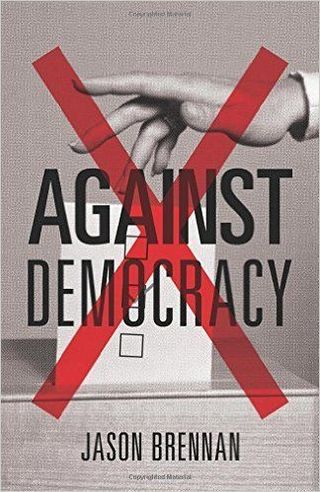米オハイオ州クリーブランドの路上で「真のイスラム教徒は全員ジハーディスト(イスラム過激派)」と書かれたポスターを掲げるドナルド・トランプ氏の支持者〔AFPBB News〕
次期大統領に選ばれて以来、ドナルド・トランプ氏(70)が「神」について触れたことはただの一度もない。
予備選当時、南部や中西部で共和党候補は、エバンジェリカルズ(キリスト教原理主義者)や「ボーン・アゲイン・クリスチャン」(宗教経験で信仰を新たにしたキリスト教徒)といったキリスト教保守の票を奪い合った。
いったい、あのエバンジェリカルズの票は本選挙ではどうなったのだろう。それよりも何よりも米国におけるキリスト教とは何だったのだろう。
歴史を紐解くまでもなく、宗教上の迫害から新大陸に逃れ移り住んだピューリタン(清教徒)が持ち込んだのは「自由と平等」「隣人愛」を尊び、厳しい自然に立ち向い生き抜くための「白人の、白人による、白人のためのバックボーン(背骨)」だった。
それは英国から独立した新国家、「United States of America」の推進力として250年間、アメリカン・カルチャーの主軸として生き続けてきた。
「白人キリスト教国家」の終焉
ところがその「白人キリスト教国家」が終焉を迎えた、と言い切る新書が注目されている。
宗教学者のロバート・ジョーンズ博士の「The End of White Christian America」(白人キリスト教国家・アメリカの終焉)だ。
折しもキリスト教の理念とは相反する人種的偏見をむき出しにし、「隣人愛」などそっちのけの不動産王が第45代大統領に就任しようとしている。
この型破りの次期大統領は、お隣のキリスト教国家・メキシコからの不法移民を追い出し、米国憲法で保障された「宗教の自由」条項を破り捨て、イスラム教徒の入国を厳しく規制することを選挙戦の公約に掲げてきた御仁だ。
外交的には、「自由と平等」の名のもと、世界各地で起こる戦闘や戦争に米国が介入してきた理由づけの1つにキリスト教による正義を実現することにあった。
ナチスや日本帝国主義と戦い、打ち破った大義名分に「白人キリスト教国家」の信ずるキリスト教理念が使われてきた。
そのことはトランプ氏の主張してきた「Make American Great Again」(アメリカを再び偉大な国家にする)というスローガンとは相いれないのではないのか。