『アラビアのロレンス』(1962)の名演で知られるアイルランド人俳優ピーター・オトゥールが亡くなった。
その端正な顔立ちから、ロマンティックコメディ『おしゃれ泥棒』(1966)ではオードリー・ヘプバーンの相手役をこなし、プレイボーイ役の『何かいいことないか子猫チャン』(1965)ではピーター・セラーズやウディ・アレンといった名コメディアンたちと軽妙なコメディ演技を展開した。
その一方で、舞台役者としての経験を生かし『ベケット』(1963)『冬のライオン』(1968)ではともに英国王ヘンリー2世を重厚に演じるなど、幅広い演技力を誇る名優だった。
そんななか、特に際立っていたのが『ラ・マンチャの男』(1972)のドン・キホーテのような矛盾を抱えた癖のある役柄。その真骨頂が、出世作となった『アラビアのロレンス』のトーマス・エドワード・ロレンス役だった。
映画の教科書として多くの名監督が手本に
英国映画の名匠デヴィッド・リーン監督が壮大なスケールで描く70ミリの歴史絵巻は、オトゥールをはじめとした出演者の演技の確かさはもとより、ロバート・ボルトの脚本、モーリス・ジャールの音楽とあいまって、フレディ・ヤングの撮影が冴えわたり、鉄道爆破や戦闘といったアクションから果てしなく広がる砂漠に浮かぶ蜃気楼、照りつける太陽と砂地獄・・・と見どころ満載。
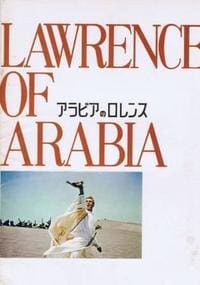 アラビアのロレンス
アラビアのロレンスその大画面を十二分に生かした演出は映画の教科書としてジョージ・ルーカスやスティーブン・スピルバーグなど多くが手本にしているという。
しかし、この作品を価値あるものとしているのは、多くの映画人、批評家たちが歴代ベストに挙げるほどの作品の完成度だけではない。
オトゥール演じるロレンスが第1次世界大戦という歴史舞台で演じた役柄は、「瀕死の重病人」末期オスマントルコ帝国からの独立を目指すアラブ人の気概を利用しようという英国の「手先」。
トルコが掲げるジハードと民族自決との間で揺れ動くアラブ人に、英国は独立を支持するという「フサイン・マクマホン協定」を提示しながら、その裏では、ユダヤ人のパレスチナ国家建設を支援する「バルフォア宣言」、英仏露の戦後の分け前の取り決め「サイクス・ピコ秘密協定」まで存在していた。
実際にロレンスがそんな三枚舌外交の本意をどこまで知っていたかは知るよしもないが、(フィクションが混在するとはいえ)第1次世界大戦が今のイスラム世界混迷の遠因ともなっていることを物語る歴史書に埋もれがちな事実を饒舌に語る教科書ともなっているのである。











