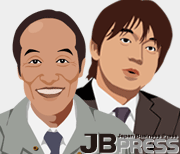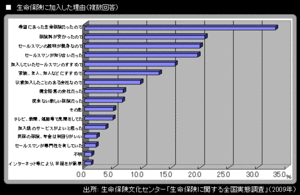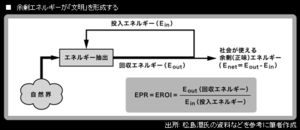石油を「代替」できるエネルギーなど存在しない
原発も自然エネルギーも魔法の解決法ではない
2010.3.16(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
本日の新着

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力
身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点
市ノ瀬 雅人

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】
若月 澪子

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択
大谷 達也

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖
「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費
森田 聡子