 写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
完全な経営戦略論は存在しない。20世紀初頭に生まれた「原形」は、環境変化に応じて改良・派生を繰り返してきた。本稿では『経営戦略全史〔完全版〕』(三谷宏治著/日経BP 日本経済新聞出版)から内容の一部を抜粋・再編集。企業がいかに理論を磨き、生存競争に勝ち抜いてきたかを振り返る。
1970年代、日本の一企業に過ぎなかったキヤノンとホンダ。「無謀」とされた米国市場参入に成功した理由とは?
キヤノンとホンダ「無鉄砲」な日本企業たち
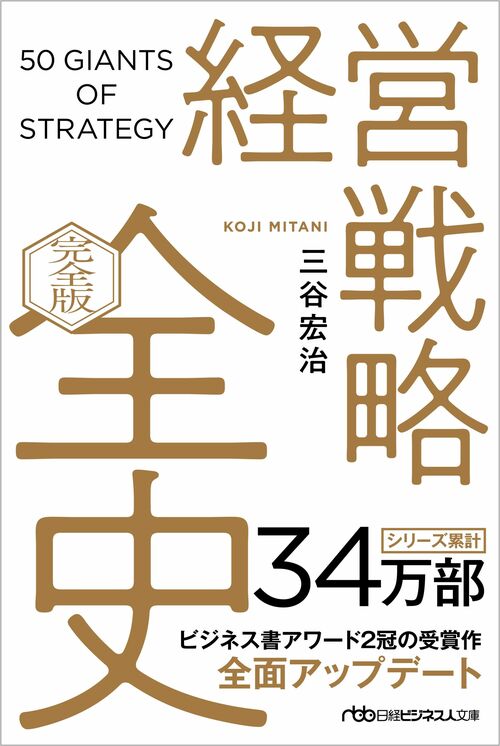 『経営戦略全史〔完全版〕』(日経BP 日本経済新聞出版)
『経営戦略全史〔完全版〕』(日経BP 日本経済新聞出版)
■ 絶対王者ゼロックスに挑んだキヤノン
1970年、キヤノンは遂に普通紙複写機NP-1100を88万円で発売01します。ゼロックスが築き上げた特許の壁を乗り越えての独自方式のものでした。62年に第一次長期経営計画で多角化02を謳(うた)い、たった数名で研究を始めて、8年後の快挙でした。
キヤノンは、ゼロックスの主要顧客であった大企業を避けて中企業に注力するとともに、82年にはメンテナンス不要のカートリッジ方式を採用した3色カラーのミニコピアPC10を24.8万円で投入して、小・零細(れいさい)企業をも顧客として開拓します。
62年当時、普通紙複写機市場でゼロックスは、600件にも及ぶ特許と、従量課金のレンタル方式(大きな資金力を必要とする)をとることで、「20年は崩(くず)せない」といわれた鉄壁のビジネスモデルを構築していました。それを正面突破しようとする企業は、世界中に1社もありませんでした。普通紙複写機市場は、大きく成長しそうな市場で「儲かりうる市場」ではありましたが、「儲かる位置取り」があり得なかったからです。
だからポジショニング派に言わせれば、キヤノンの「挑戦」は無鉄砲な日本企業の「暴挙」に過ぎませんでした。でもそれは成功し、キヤノンをカメラメーカーから事務機器メーカーに変身させ、世界企業へと押し上げました。「ゼロックスの独占市場なのなら、大きなチャンスだ。他が入ってこないのだから、もしうちだけ入れればシェア50%取れるじゃないか」
キヤノンのトップたちは当時、そう考えたそうです。
01 他社からのライセンス技術(RCAからのEF方式)によるものは、1966 年に発売していた。
02 第一弾は世界初のテンキー式電卓キャノーラ130(40万円)だった。








