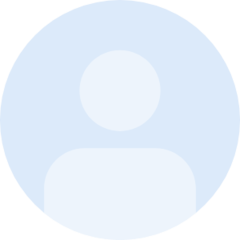写真提供:NurPhoto/共同通信イメージズ
写真提供:NurPhoto/共同通信イメージズ
時代を超えて輝き続ける18社を研究した『ビジョナリー・カンパニー』(1994年発行)は現在も経営者の必読書と言える名著だが、それをさらに進化させた本『愛される企業 社員も顧客も投資家も幸せにして、成長し続ける組織の条件』(ラジェンドラ・シソーディア、ジャグディッシュ・シース、デイビット・B・ウォルフ著/齋藤慎子訳/日経BP発行)が話題を呼んでいる。キーワードは「愛」。企業経営にはおよそ似つかわしくない言葉だが、顧客や投資家のみならず関係するあらゆる人・組織に愛されることこそが経営の本質だと説く。抽出された72社はビジョナリーカンパニー以上の実績を上げており、そこには共通して7つの特徴があるという。本連載では、同書から内容の一部を抜粋・再編集、愛される企業の条件を事例を交えて紹介する。
今回は、「愛される企業」に見られる共通点を解説する。
■「愛される企業」とは?
「愛着」「愛情」「喜び」「誠意」「エンパシー(共感)」「同情」「思いやり」など、愛情を表すことばはいろいろある。少し前までは、こうしたことばはビジネスの世界で受け入れられていなかった。それが変わりつつあり、いまは、こうしたことばを難なく受け入れている企業が増えている。
だからこそわたしたちも「愛される企業」と造語したのだ。愛される企業は、簡単にいえば、すべてのステークホルダー集団の関心事を戦略的に調整することで、ステークホルダーに「愛されている」企業のこと。ほかのステークホルダー集団を犠牲にして利益を得るような集団はひとつもなく、どの集団もみんな同じように豊かになっていく。愛される企業は、ステークホルダーを喜ばせ、愛着を感じてもらい、ロイヤルティにつながるやり方で、すべてのステークホルダーの機能的ニーズにも、精神的ニーズにも応えている。
1990年代、「財布シェア」というマーケティング用語が流行り、顧客関係管理(CRM)と呼ばれる手法で最重要視されるようになった。しかし、顧客を数字としてしか見ない、味気のない、非人間的な見方を示すことばだった。