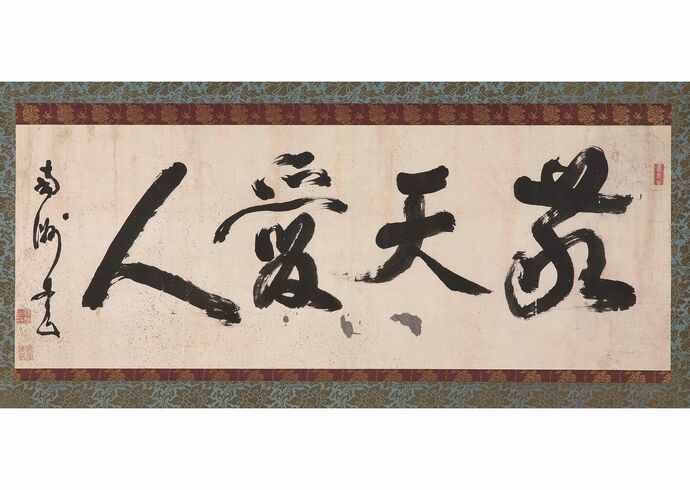東京大学情報基盤センター学際情報科学研究部門教授の山肩洋子氏(撮影:今祥雄)
東京大学情報基盤センター学際情報科学研究部門教授の山肩洋子氏(撮影:今祥雄)写真提供:Shutterstock
ChatGPTなどの生成AI(人工知能)をビジネスの現場で活用しようとする企業が増えている。さまざまなメリットを生む一方で、リスクも指摘される。東京大学情報基盤センターの山肩洋子教授は、生成AIの仕組みを理解するためにアカデミア(学界)との連携も有効だと説く。その活用方法などについて聞いた。
生成AIがビジネスツールへ急成長
――ChatGPTをはじめとする生成AIの普及がビジネスの現場で急速に進んでいます。短期間でビジネスツールとして成長している要因はどこにあるのでしょうか。
 山肩 洋子/東京大学 情報基盤センター 学際情報科学研究部門教授
山肩 洋子/東京大学 情報基盤センター 学際情報科学研究部門教授2007年 京都大学 情報学研究科にて博士(情報学)を取得。2010年から6年間、京都大学で特定講師のち准教授。2015年から日本学術振興会 特別研究員となり、2人の子供を連れて英国サセックス大学にて客員研究員。2019年 東京大学大学院 情報理工学系研究科 准教授を経て、2024年より現職。専門はテキストと画像を対象とした深層学習技術を中心とするマルチメディア情報処理分野。AIによる「食」の支援技術に興味を持つ。
山肩洋子氏(以下敬称略) 人が書いたり話したりする言葉をコンピューターで処理することを「自然言語処理(Natural Language Processing、NLP)」と呼びます。転機となったのは2018年にGoogleが自然言語処理モデル「BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)」を公開したことです。
それまで企業が機械学習を利用しようとすると、データの収集やモデルの学習などを自前で行う必要がありました。つまり、「試しに使ってみる」ということができるものではなかった。ところがBERTには、汎用性が高いという大きな特長がありました。BERTの登場によってそれまでは難しかったことが試せるようになり、機械学習がビジネスに使えるという認識が広がったと思います。
また、BERTを含む自然言語処理モデルにはもう1つ特長があります。「Neural scaling law(ニューラル・スケール則)」と呼ばれるものです。従来、アカデミアの世界では、データを増やしてもある程度の精度まで上がると飽和するというのが常識でした。ところが、自然言語処理モデルの性能は、パラメータ数、学習データ数、および学習にかける時間のべき乗に従うということが発表されました。つまり、無限に精度が高まるのです。これは大きな変革でした。
――ポテンシャルの高さが期待される一方で、リスクを懸念する声もあります。
山肩 オープンAI社のChatGPTなどは、コードが書けない人でも簡単に利用できます。ただし、そこが怖いところでもあります。ChatGPTはソースコードを公開していません。ブラックボックスです。企業にとっては個人情報や顧客情報などが流出するのではないかと危惧するところでしょう。
また、AIには公平性やバイアス(偏見)など倫理面でのリスクもあります。このあたりは文化依存性が強いところであり、他国では容認されているような表現が日本では好ましくないという場合もあります。
政府も「AI事業者ガイドライン」など、AIに関する事業者向けの指針の策定を進めているところですが、国に任せ切りにするのではなく、自社なりのガイドライン化を進めていく必要があります。
いずれにしても、他国のサービスを使い続けることにはリスクがあります。国内のサービスや、オンプレミス(自社所有)のような仕組みを早急に用意する必要があります。