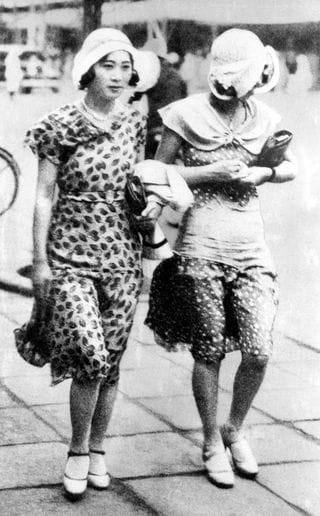それをしないと周囲から失笑を買ったものだが、昨今、銭湯や温泉で周囲を見まわせば、そうした礼儀も、周囲への配慮も希薄になりつつある。
礼儀とは他人に不快感や危懼を与えぬことであり、羞恥は自らの杞憂警戒の心理だが、それよりも自身の開放感が優先されるのは時代の流れなのか。
だが、「銭湯ではイチモツを晒すなかれ」なのだ。
ちなみに「ふんどし」という言葉は外国語由来ということが分かる。もともと日本語には「ん」という発音の言葉は『古事記』『日本書紀』『万葉集』を通じて存在しない。
したがって「ん」と撥ねる音は皆外国語であることに間違いはない。
「ふんどし」にしても同様で朝鮮半島からきた言葉で褌衣はフン・ツ・オスでこの急呼がフンドス、出雲、伯耆方言では「すんぱい」は心配だから「ふんどし」といわず「ふんどす」と発音するわけである。
現在の朝鮮語では褌衣はフン・ツ・オスとはいわず褌(ツルボ)という。ツルボの原義は吊る布の意。
昭和初期まで東北や西日本の一部地域に「ふんどし祝い」という風習が残されていた。
男児が10歳になると叔母さんのところに行って「マラ皮」を剥いてもらい、13歳になると白い布をもって叔母さんが独りだけいる時間帯を見計らい男児が家を訪ねるという風習である。