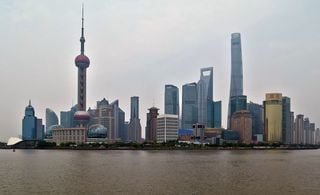都内の映画館「新宿バルト9」では映画『ボヘミアン・ラプソディ』に登場する衣装をロビーで展示している
都内の映画館「新宿バルト9」では映画『ボヘミアン・ラプソディ』に登場する衣装をロビーで展示している
フレディ・マーキュリーの半生を描いた映画『ボヘミアン・ラプソディ』が公開され、伝説のロックバンド「クイーン」が改めて脚光を浴びている。クイーンは数々の世界的なヒット曲で知られるが、隠れた名曲も数多く存在する。クイーンの活動期にリアルタイムでメンバーを取材し、今なおクイーンを愛してやまないラジオDJ、音楽評論家、音楽プロデューサーの今泉圭姫子氏(リフレックス代表取締役)に「フレディを強く感じられる曲」ベスト10を挙げてもらった。(JBpress)
偉大な世界のロックバンドに昇り詰めるまで
11月9日より映画『ボヘミアン・ラプソディ』が公開されている。
フレディ・マーキュリー没後には、「ラヴァー・オブ・ライフ、シンガー・オブ・ソングス」(2006年)というドキュメンタリーDVDが発売になっているのだが、これは子供の頃から亡くなるまでの、短くも華麗な、そして孤独な人生が浮き彫りにされたフレディの映像。彼の周りにいたメンバーはもちろん、スタッフ、友人などの証言によってまとめられたものになっている、まさにリアルストーリーだった。最後は彼が死と向き合いながらも必死にクリエイティヴな活動を続け、フレディ生前最後のアルバム「イニュエンドゥ」(1991年)を作り上げたシーンが収録されていた。このドキュメンタリーを見たクイーン・ファンには、映画『ボヘミアン・ラプソディ』は実際のストーリーと多少異なっていることがわかるだろう。
しかしそれを前提としても、この映画は見応えがあった。洋楽ロックの全盛期を築き上げたクイーンという大英帝国が誇るバンドが、どのようにして偉大な世界のロックバンドになっていったか。その背景にあるバンドとしての苦悩、周りの人間との関係性、お金には変えられない名声との闘い、さらには、なんの保証もないロックミュージシャンが、大好きな音楽をやり続けていく青春ストーリーでもあった。そしてフレディが差別を受けながらも、容姿を指摘されても、ヴォーカリストとして圧倒的な自信をもち歌い続けていった姿が映画の大きなテーマなのではないかと思う。
フレディが「王子様」だった
私にとってのクイーンは、洋楽を聴くきっかけとなったグループだ。それまでは西城秀樹のファンクラブに入り、「ヒデキ、ヒデキ」と騒いでいた。ヒデキのコンサートは、洋楽のカバーが多かったのだが、初めて耳にする曲は後から調べて、自分なりにヒデキ推薦の洋楽を楽しんでいた。ある日、新御三家(西城秀樹、野口五郎、郷ひろみ)がTV番組に出て洋楽カバーを披露していた時、郷ひろみがクイーンの「ストーン・コールド・クレイジー」を歌っていた。そこでクイーンを知り、その後はどっぷりクイーンの世界へ入り込んだ。
初めての日本武道館は、もちろんクイーンのコンサートだった。彼らにとって2度目の日本ツアー(1976年)の時だ。武道館の天井に近い席で見たクイーンは、高校生の私にとって新鮮な驚きだった。こんなロックの世界があるのかと。美しく、気高く、気品のあるロック。いつかもっと近くで見るんだ、と夢を膨らませた。その時の思いは、いつのまにか湯川れい子先生のラジオ番組のオーディションを受ける勇気に変わった。そしてクイーンが大好きだということだけで、オーディションに合格し、この世界に入ることになった(合格の真相は今もわからない)。そしてクイーンとの出会いは、人生の導きとなり、今こうして音楽業界で仕事をしている。
なぜフレディだったのか・・・それは言葉に表わすのが難しいのだが、この人だ、というトキメキ! しかない。堂々としていて、背筋がピシッとして、会場に響きわたる歌声。そして優しい瞳。私にとっての王子様だった。高校生だったのだから。この仕事を始めて、4人揃ってのインタビューはなかったが、それぞれ何度かインタビューをさせていただいている。仕事なのだから、と言い聞かせながらも、「クイーンがいたから、私はここにこうしています」と口に出さずとも、その思いをもってインタビューに臨んでいた。