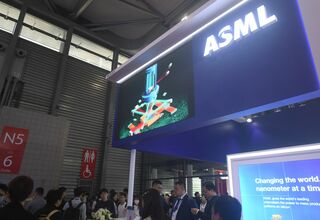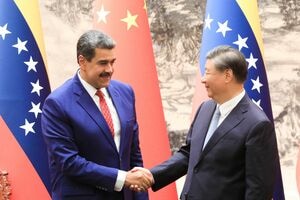かつて国民党政府のリーダーの1人だった戴季陶氏(1891~1949年、1905年に日本留学)は自らの著作『日本論』の中で、「日本の書店に行けば中国に関する研究書がたくさんあるのに対して、わが中国では日本に関する研究書がまばらだ」と記していた(筆者訳)。
20世紀初期、戴氏が日本で目にした中国研究の豊富さは今も変わっていない。否、当時より今の方が量的にもっと増えているはずである。
だが今の日本の中国研究は深刻な問題を抱えていると思われる。それは、書店の中国関係コーナーを見れば一目瞭然だが、中国脅威論(日本にとっての悲観論)と中国崩壊論(楽観論)に二極化していることである。
いかなる研究も、まず求められるのは客観性である。そのうえ、建設的でなければならない。しかし、今の日本の中国研究の多くはいずれも欠如しているように思われる。
確かに中国という国は巨大な象のような存在である。だからといって中国研究者は群盲となって象をなでるように中国を「ウォッチ」すべきではない。木を見るようなミクロの研究も必要だが、同時に森も見なければならない。木しか見なければ、研究は単なる研究者の趣味になってしまう恐れがある。
飛躍的に質が高まった米国の中国研究
20年前、中国研究者は中国の正確な経済統計を入手することはできなかった。もちろんインターネットなどなかった時代だったため、中国の統計を入手する唯一の方法は、毎日「人民日報」(海外版)をチェックすることしかなかった。だが人民日報に載っている統計は不正確である。そこで、数字を補正するためにできるだけ現場へ足を運び、国有企業などを見学してインタビューを実施することが必要だった。