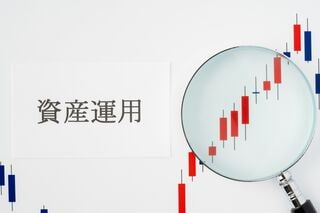バングラデシュは、中国語で「孟加拉国」と書いて「モンジャラグオ」と発音する。日本人同様、中国人にとってもこの国のイメージは曖昧で、どこにあるのかも知らない人が圧倒的だ。イメージと言えば、「中国よりさらに遅れた途上国」という程度である。
だが、そのバングラデシュでは目端の利く中国人たちが静かにビジネスを始めていた。背景には「走出去」という、中国資本の海外展開という政策の支持がある。加えて、中国拠点だけにとどまるのはリスクだと感じた中国人経営者が、自発的にシフトしているという要因もある。
中国人にとって「バングラデシュは近い」
上海発・昆明経由ダッカ行きの東方航空に乗った。134人乗りのB737型機は、人と荷物でスシ詰め状態だった。中国人もいればバングラデシュ人もいる。中国人の荷物のほとんどは“商品サンプル”で、機内の座席には「省エネタイプの電球」や「バスの模型」などが箱詰めで置かれていた。
筆者の右隣の席には、ダッカのアルミニウム工場に管理職として出稼ぎに行く四川省出身の民工が座った。中国ではもはや条件のいい職にはありつけず、バングラデシュ行きを「いい収入になる」と喜ぶ。今や民工も空を飛ぶ時代になったのだ。ちなみに、中国資本のこのアルミ工場は、すでに十数年前から稼働しているらしい。
左隣には、チッタゴンで漁業をする父の事業を継ぐという中国人の高校生が座っていた。確かに、バングラデシュはエビの一大輸出国だ。彼はチッタゴンのインターナショナルスクールでベンガル語も勉強中だというが、跡継ぎとしてバングラデシュに行かなければならないことを「運が悪い」と嘆いていた。
機内の中国人は、四川省出身者が多かった。彼らは異口同音に「バングラデシュは近い」と言う。確かにその通りで、上海からでも昆明を経由してダッカまで5時間足らずで到着する。筆者はこの近さに驚いた。しかも、航空運賃は往復1460元と安い(燃油サーチャージは別)。日本からは、バンコクあるいはシンガポール経由で12時間近くもかかるため、「遠い国」という印象はなかなか払拭できない。
筆者にとって興味深かったのは、バングラデシュに飛ぶ中国人たちが、英語に関してはからきしダメだったことだ。筆者の周りに座った中国人はみな入国カードの記入に手間取り、誰もが30分近くも格闘していた。
「バングラデシュには数十万人の中国人がいる」(右隣の中国人)という。彼らは街に出ることはなく、ほとんどの時間を工場と宿舎で過ごしているようだ。