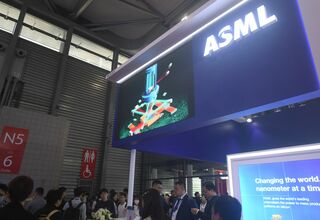グルジア出身の映画監督オタル・イオセリアニは、1979年にソ連から西側に出て以来、フランスのパリを拠点に映画作りを続けている。
最新作の『汽車はふたたび故郷へ』(2月18日(土)より岩波ホールほか全国順次公開)は、自伝的要素を材料としつつ、ソ連とフランスとの体制の違いを超えて存在する映画製作の不自由をめぐる寓話である。
映画製作の不自由さを描いた自伝的作品
最初の舞台はソ連時代のグルジア。主人公のニコは映画監督をしている。
子供の頃から、教会から絵を盗んだり、隠れて煙草を吸ったり、大人に酒を飲ませてもらったりしながら育ったニコは、映画監督になってからも、自分の好きなように映画を作ろうとして、周囲や上司と対立している。
その結果、出来上がった映画は上映許可を得ることができず、公開は棚上げになってしまう。
友人の協力でフランス大使に会ったニコは、上映禁止となったフィルムを夜中にこっそり持ち出すが、その行動は当局に筒抜けで、ニコは逮捕されて暴行を受ける。
ニコはワインを片手に、共産党幹部と会いに出かける。幹部から「お前が外国に出るのが、お互いにとって最良の策だ」と言われたニコは、出国を決意し、汽車に乗ってフランスのパリへ出る。
パリには、ロシア/ソ連からの亡命者の大きなコロニーがある。そのコロニーの一員である祖父の友人を頼って住む場所を確保したニコは、新しい映画のシナリオを書き始める。
当局の監視もソ連大使の計らいでゆるくなる。コネを活用して映画の製作資金を出すプロデューサーも見つかる。
しかし、プロデューサーはニコが何を撮ろうとしているのか理解できず、撮影にも編集にも口を出す。伝書鳩に託した故郷への手紙では「こっちでも同じようにすべてが最悪だ」と愚痴るニコだが、やっとのことで映画を完成させる・・・。