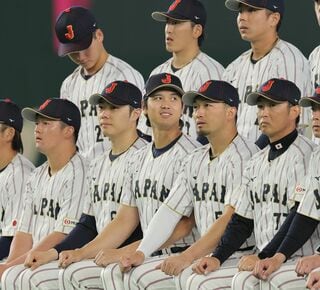日本の自動車産業には、独特の「型」がある。いや、ここでもまた「あった」と過去形で言わなくてはならない状況に陥りつつある。
その「型」とは、自動車というプロダクトを企画し、開発し、最終組み立てを行う「自動車メーカー」と、そこに組み込まれる様々な部品を製造する「部品メーカー」、今日流の言い方では「サプライヤー」との、密接な連携。
自動車メーカーの技術者は、例えば製品企画の担当者であれば「次にどんなクルマを創ろうか」と様々に思いを巡らせる。それは決して商品としてのイメージや、マーケットの中でのポジショニングなどにとどまるものではない。そのアイデアを実現するために必要な技術要素を1つずつ考え、移動空間としての自動車の形を組み上げる。これが、トヨタ自動車では以前「主査」と呼ばれた開発主務者が最初に取り組むことだった。
個別の要素技術、例えば足回り、エンジン、駆動機構、車体、さらに製造プロセスなどを専門にする技術者たちも、いつも「次の時代の自動車はどこに向かうか、そこではどんな技術が必要になるか」を考え、世界の潮流を把握し、そこから先に思いを巡らせ、具体的な技術像を描き出す。
なにしろ自動車は、新たな製品として世に出してから何年も造られ続け、そこから送り出されたクルマたちはそれぞれ10年以上も道路を走り続ける。つまり、開発作業をどんなに急いでも、時に最近の日本のように途中のプロセスを省略してまでその期間を縮めたとしても、最初の構想段階から十数年先までにわたったユーザーの生活に密着し、その命を預かり、社会と関わり続ける「工業製品」なのだ。
さらに基幹技術ともなれば、開発着手から実際に市販車に組み込まれて世に出るまでに最低でも数年はかかり、そこから多くの車種に展開されてゆくものだ。したがって技術者も、もちろん製品企画に携わる者、さらに企業の舵を取る者まで全てが、10年以上のスパンで自分たちのものづくりをイメージし、取り組む必要がある。これが自動車産業の原則。
自動車メーカーとサプライヤーが一体となった「日本流」ものづくり
かつて、トヨタをはじめとする日本の自動車メーカーの中でも、そうやって「自分たちが生み出すもの」を考える自動車企画のプロフェッショナルたるべく研鑽を積む人々がいた。我々、取材者の側もそういう人々に「鍛え」られた。
そうした人と組織が紡ぎ出した「次の製品」と、そこで実現すべき(実現したい)資質、性能、機能のコンセプトから、「個別の技術アイテムとして何が必要か」が描き出される。
ここで、日本の場合は自動車メーカーと部品メーカーとの連携作業が動き出す。自動車メーカー自身が技術要素の開発を主導し、そこに部品メーカーも参画する。部品メーカーの人材を開発チームに加えて作業を進めることも多かった。そこで形づくられた新しい技術アイテムの内容、設計をどう量産するか、部品なり、製造設備の形で具体化するかが、部品メーカーに任される。とはいえ実際の製品に組み込むところまで、自動車メーカー側の技術者もずっとアテンドする。そうやって生み出された技術が数多くある。
一方で欧米、特にヨーロッパの自動車開発の中では、部品メーカー側の独立性・自立性が格段に高い。機械部品、電気電子部品、製造設備などそれぞれの分野に専門企業があり、次の世代で必要になる技術要素も、彼らが開発し、提案してくる。部品を作る側も、それができるだけの「自動車のプロフェッショナル」なのである。