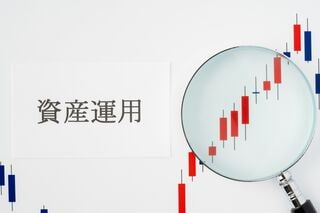'Cool Japan' は、トニー・ブレアが英国首相に就任して打ち上げたスローガン 'Cool Britannia' をそのままなぞってできた標語で、日本型ライフスタイルやポップカルチャーのアジア内外における先進性や優位性――と信じられているものを指す際、もっぱら使われてきた。
本家英国産とその派生物いずれにも、巧まざる歴史の皮肉としかいえない要素がある。
本家'Cool Britannia'の顛末
大英帝国を女性として人格化する際、これを Britannia と呼んだ。そしてビクトリア女王の治世下、帝国が女王とともに栄華の頂点を極め世界の海を支配していた頃、ブリタニアに向かって帝国建設者たちが望むことはただ1つ、'Rule, Britannia(統べよ、ブリタニア)' だった。同名の愛国愛唱歌もあり YouTube で聴ける。
Cool Britannia とは言うまでもなくこれに韻を踏ませてできた言葉で、英国のポスト・コロニアリズムに仕上げの一刷毛を与える意味合いを帯びていた。英国は強くて畏怖される帝国でこそもはやないかもしれないが、お洒落な若い国に再生したのだとする自己主張が、そこには託されていた。
皮肉というのは第1に、そんな歴史的暗喩を感じ取れたのはまずもって英国国民であり、次いで恐らくインド辺りの知識層に過ぎなかっただろうから、標語は本来の向きと異なり、すぐれて内向きに――すなわち自己「主張」であるより多く自己「確認」に――奉仕する役目を果たさざるを得なかったという点である。
ところがイラクとアフガニスタンに米国を除くと最も深い関わりを始めた英国には、一転、刺々しく武張った印象が固着していく。若い宰相ブレアは、ジョージ・ブッシュのプードル役を進んで買って出るリスクをむしろ選び、それとともに標語は人の口に上ることをやめた。皮肉の2だ。
日本の卓絶よりアジアの台頭を象徴する'Cool Japan'
'Cool Japan' の場合、これが日本の卓絶よりは、むしろアジアの台頭(より正確にはアジア消費階級の勃興)をこそ象徴するバズワードだというところに歴史のアイロニーがある。
外務省とは日本について何か売れるものはないかと二六時中探し回る性(さが)の持ち主であって、自分もその一員だった時、このクールなジャパンなるものの売り方を考えたものだった。