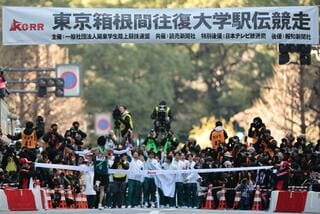2011年9月11日はニューヨークやワシントンD.C.で起きたいわゆる同時多発テロから10年の節目であり、日本でも多くの報道がなされた。その後のアフガニスタン、イラクなど世界各地への軍事侵攻による莫大な軍事費が米国を現在経済的に苦しめている。
黒煙を上げる世界貿易センタービルと2機目のハイジャック機〔AFPBB News〕
歴史をひもとくと、実はアフガニスタンという土地は、巨大な帝国にとって鬼門である場合が多かった。
例えば30年ほど前にさかのぼれば、ソ連崩壊の要因の1つになったのがアフガニスタンへの軍事介入だった。
19世紀の大英帝国しかり、アフガニスタンはユーラシアを掌握しようとする諸帝国にとって、「帝国の墓場」とすら言われていたのである。
さらに歴史の針を戻すと、今からちょうど300年前の1711年秋、アフガニスタンで起こった出来事が「帝国崩壊」を引き起こしている。サファヴィー帝国(サファヴィー朝イラン)が崩壊するきっかけとなったこの出来事については次回詳しく述べるが、ここには小国ながら、実はグルジアとコーカサスの動向が複線的に絡んでいたことに注目したい。
アフガニスタンをめぐる安全保障問題は日本にとっても決して他人事でないうえに、グルジアは米国軍が大規模な撤退計画を発表するなかで来年から派兵の大幅拡大を計画中だからである。グルジアとアフガニスタンをつなぐ歴史エピソードを知っておいて損はない。
忘れられた「色つき革命」
十年一昔という。対テロ戦争の是非について議論が盛んになっているのも、「歴史検証作業」と言えるかもしれない。しかし、対テロ戦争を仕かけたジョージ・W・ブッシュ政権が同時に推し進めた「民主化革命ドミノ」の方は意外に忘れられている気がする。
当時、イラクはパープル革命と呼ばれた。レバノンは杉革命。そして、旧ソ連ではウクライナのオレンジ革命、グルジアのバラ革命、キルギスのチューリップ革命。
対テロ戦争が泥沼化し、ブッシュ政権が民主化の目玉としたイラクやアフガニスタンの混迷ぶりはこの10年、目を覆うばかりであった。そして、パキスタンの不安定化など、むしろ危険の種は増大している。
その一方、こうした米国の強硬路線にすり寄り、援助を引き出して、王様のような統治者とその一族が蓄財に励んでいたアラブ諸国で「アラブの春」と呼ばれる民主化の波が、まさに米国による指導力にかげりが見えるなかで、押し寄せているのは皮肉な事態である。